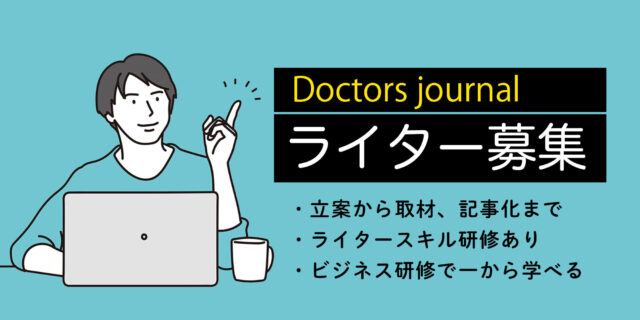#02 EBMに基づいた治療は統合医療においても必要だと考えます
連載:西洋医学と東洋医学、自然療法を結集した統合医療によって心身をトータルケアする
2020.10.09
データに基づく科学性の検証で普及を目指す
朱院長は2005年に、オリエンタル・アロマセラピー・カレッジを立ち上げ、理事長兼講師を務める。
校長の小山めぐみ氏は、救命救急センターで朱院長を一緒に働いていた。小山氏が看護師時代に英国で学んだアロマセラピーについて聞き、朱院長は癒しの治療として統合医療に取り入れられるのではないかと考えた。
しかし、そこには科学的な検証が無く、医療側として納得のいく最低ラインまで科学性を引き上げなければ、医療で普及していくのは難しいとも思われた。それでもアロマセラピーを医療に役立てたいと思う看護師も増えてきていた。その意識は広がっていくだろうと、朱院長は推測したのである。
そうしたなかでオリエンタル・アロマセラピー・カレッジが設立され、教育とともに研究や臨床によって検証が進められていった。
現代医療ではEBM(Evidence Based Medicine)が強く求められている。統合医療でもEBMにもとづいて治療がなされていかないと、単に癒しやアメニティと捉えられ「あったほうが良い」という世界で終わってしまい、絶対に必要であるという位置づけにまで至らないのである。
安全な品質であるという精油の評価も検証データとして必要になる。精油を科学したアロマセラピーを追求していき、現場で普及していくために、朱院長は学校とクリニックの両方で奮闘している。

情報を集めて、良い方法を探っていく
患者は、どの診療科目にかかったら良いのか判らないことがある。病院に行っても薬を処方されるだけの事もある。しかし、精神的なものから発生する不調は、薬を服用しても完治しないことも多いのである。
理由を探っていくと、小さい頃の心の傷が積み重なって不調を起こしていることがわかったりする。その解決の糸口になるのは決して薬ではない。どうしてか、どうしたいのか、どうするのか。そういう根本的なことから話をしていかないと、患者も理解し、納得できない。その作業は大変で、時間もかかる。
「開業当初から患者さんで混むであろうと予想していました。なぜなら、基本的に人が望んでいることは、心身の不調を何とかしたいのであり、薬を使わないで治していきたいと思っているからです。トンネルから出たいのです。それに対応していく必要がある。しかし、それにはいろいろなことに対応できる幅の広さが医療側になければなりません。」
心の不調でいろいろな症状が出て、胃が痛くなることもある。胃腸科で診てもらったら、胃炎だと診断される。胃薬を処方されて服用しても、なかなか胃の調子がよくならない。
そういう患者の話を聞いていくと、生活上の悩みを抱えていて、それが胃痛の原因になっていることもある。
ウツ病の患者に話を聞いていくと、小さいころに悲惨な体験をしていた。親から愛されていないという重い心の傷を背負っていることが判った。
判ってからどうするかが問題である。親の代わりになることもできない。朱院長は、家族や兄のようなしゃべり方をして、少しでも身近に接していくアプローチ方法をとる。
「大事なことは、医療者としてどうするか、どういう治療の方法を設定するかです。薬以外で解決する方法もいろいろ考えなければならない。以前に、学校に行けない子どもの患者さんがいました。そのお子さんに何ができるかを検討し、スクールカウンセラーに意見を聞いたりしました。或いは友だちと野球をすることができない子がいました。この場合、野球をするのではなく、ボールの受け渡しから始めていくようにしました。とにかく情報を集めて、その人にとって何か良いのか、その方法を探っていくことが大切なのです。」
統合医療は絶対に必要であるという信念
統合医療は絶対に必要であるという信念が欠かせない。そうでないとスタッフをまとめて、大きく育てていくことができない。スタッフも誰でもよいというわけにはいかない。また始めた人が5年、10年と続けられるかどうかもわからない。
朱院長は、開業時から軸となる2名のスタッフをそろえ、全面的に信頼を寄せてきた。スタッフにも、同じような統合医療観を共有し合うことが大事となる。しっかりした統合医療観をもつ医師を育てることも課題になっている。
統合医療は定義づけが明確でなく、それぞれに統合医療観が異なる。それでも、なぜ今の西洋医学だけではいけないのかをきっちり押さえておくことが欠かせない。そこで何が足りないかを考えたときに、その方法論は明確にすることが求められる。
大病院とのプロジェクトも進行中である。統合医療観にもとづいたリハビリ空間を計画し、アロマセラピーを取り入れる。大病院で実現すると、新しい場として人びとの目に触れる機会も多くなり、意識改革となって医療が変わっていく。朱院長はそこに大きな期待を寄せている。