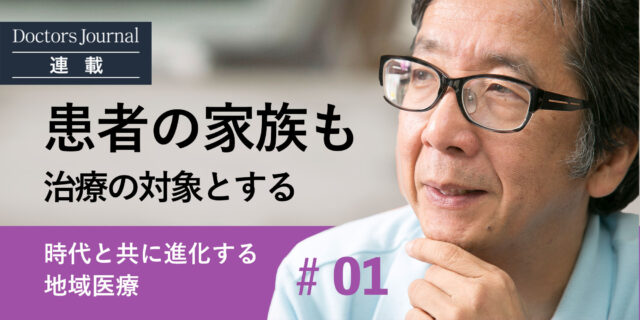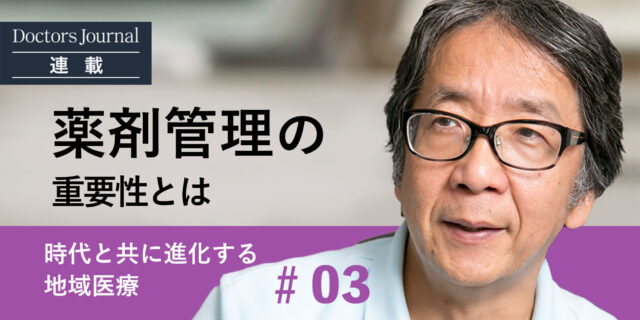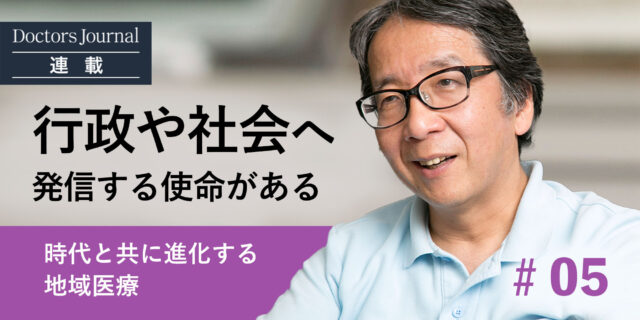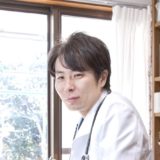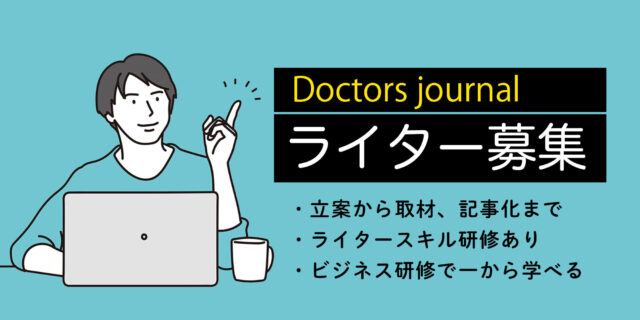#05 高齢化社会の実態を、行政や社会全体に発信する使命がある
2024.12.28
前回記事「地域包括ケアにおけるシステム・スタビライザーの役割」に続き、本記事では認知症医療に関する様々な取り組みについて伺いました。
(記事内容は2021年に公開されたものです)
NPO法人オレンジアクトで「認知症に備えるアプリ」を無料配信する
髙瀬義昌氏が理事長を務める、認知症の早期対応・備える努力を啓発するボランティア団体、NPO法人オレンジアクトは2015年8月6日に、家族など身近な人に認知症の疑いがないかを簡単に判定できるスマートフォン、タブレット端末用の無料アプリ「認知症に備えるアプリ」をリリースした。
認知症は早期発見が重要です。そのための認知症の簡易スクリーニング調査を開発しようと考えました。
認知症は本人が検査を受けることを拒むことも多く、発見の遅れも多い。「認知症に備えるアプリ」は本人だけでなく、周りの身近な人も利用できる認知症チェックアプリです。
本人が検査を怖がる場合はそっと見守り、早期の受診や認知症に備えるために、多くの人に利用してほしいと思っています。
「認知症に備えるアプリ」は、大田区の3つの医師会で検診の際に行っていた家族アンケートとHDS-Rスケール(長谷川式簡易知能評価スケール)を元に開発しました。そして、両者を同時測定し、家族アンケートの中からHDS-Rで「要検査」となる可能性に影響する因子を測定しました。
東京大学准教授(現)の五十嵐中先生にお願いして、その中でも特に有意な質問項目の「複数の仕事・作業を並行して行えない」、「お金等の計算ができない」、「季節にあった服が選べない」、「同じものを何度も買ってくる」の4項目で認知症の疑いを判定できるようにしました。
これらの項目に年齢・性別にこの4項目を加え、構築した認知症スクリーニングの感度は93.9%、特異度は82.1%と高い値を示しています。
それをオレンジアクト事務局長の倉橋絢也氏が、誰でも簡単に使えるアプリにしたのが「認知症に備えるアプリ」です。但し、本アプリの結果が医師の診断に変わるものではなく、認知症の有無を断定するものではありません。

このアプリは認知症の早期受診だけではなく、行政支援の目的も兼ねています。行政の福祉担当者が交代しても、このアプリを使えば認知症に関する知識を得ることができる仕組みになっています。
地域包括支援センターの連絡先など認知症の予防や介護に必要な地域の情報を提供する機能もありますし、地域の弁護士や司法書士とつながることもできるようになっています。
また、認知症になった時に備えて近くの後見人無料相談窓口を紹介し、任意・成年後見人制度の普及を促進しています。
「認認介護」の現状を最初に訴える
2008年に私は認知症予防協会で、「認知症の人が認知症の人を介護しているという現実がある。」という報告を「認認介護」というネーミングを使い発表しました。
その内容が、2008年7月6日の朝日新聞に、『「老老」から「認認」介護に変化』という記事で載り、世の中に「認認介護」という言葉が広まりました。
当時の朝日新聞によると、高齢者同士でお互いを介護する「老老介護」が社会問題化していた中、すでに夫婦ともに認知症になる「認認介護」の事例も出てきていました。
将来の人口推計からみても、独居または夫婦ともに高齢者の家庭の割合は確実に増加するとされています。高齢化と核家族化の影響で、「認認介護は今後もっと増える」との指摘があります。

在宅医療は常にフロントラインです
在宅医療は常にフロントラインです。そこからは多くのことが見えます。同時に、在宅医療は新聞やマスコミよりも早い時代のセンサーだと考えています。進みつつある高齢化社会の実態を、行政や社会全体に発信する使命があると思っています。
2007年には、現代のエスプリNo.484「在宅医療―そのミッション・ビジョン・ゴール」で、高校時代からの友人で現在は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の香取照幸氏などと一緒に在宅医療の方向性について執筆しました。
在宅医療に携わる中で、これからますます大きな課題となる認知症に対して、家族も行政も納得できる解決策を見つける必要があると感じました。
最近では、認知症の当事者の方々が自ら声を上げ、世の中の認知症への理解を深め、生活しやすい社会を築くための取り組みが始まっています。
医師は、単なる医療提供者ではなく、社会的存在として求められていくのではないでしょうか。

今後は、医療提供者の真のヘルスプロモーションの能力が問われる時代です。
在宅医療に携わる私たちが提供するのは、在宅医療のフィールドを使ったハイパフォーマンスヘルスケアだと思っています。
それを考えて具現化し評価する。そして次の世代につなげていく。この取り組みが、これからのテーマと考えています。