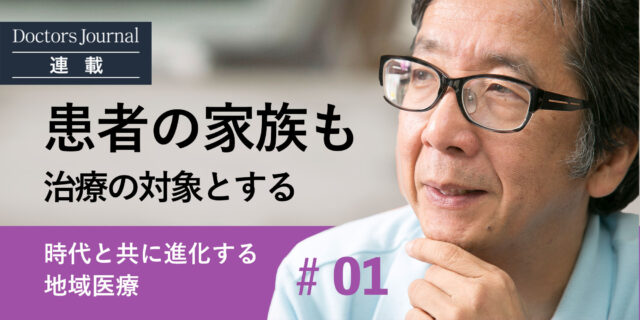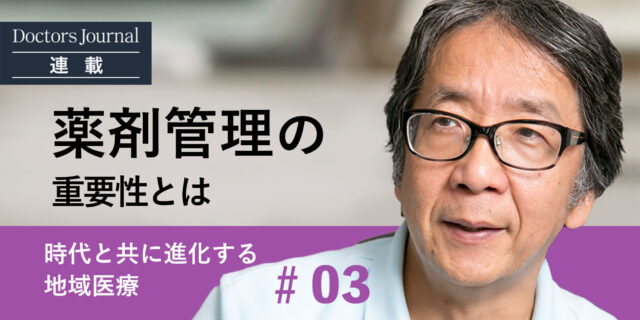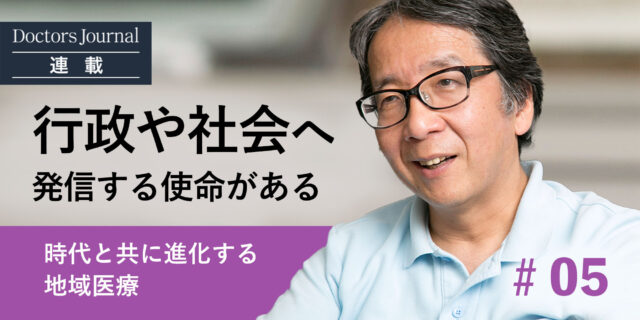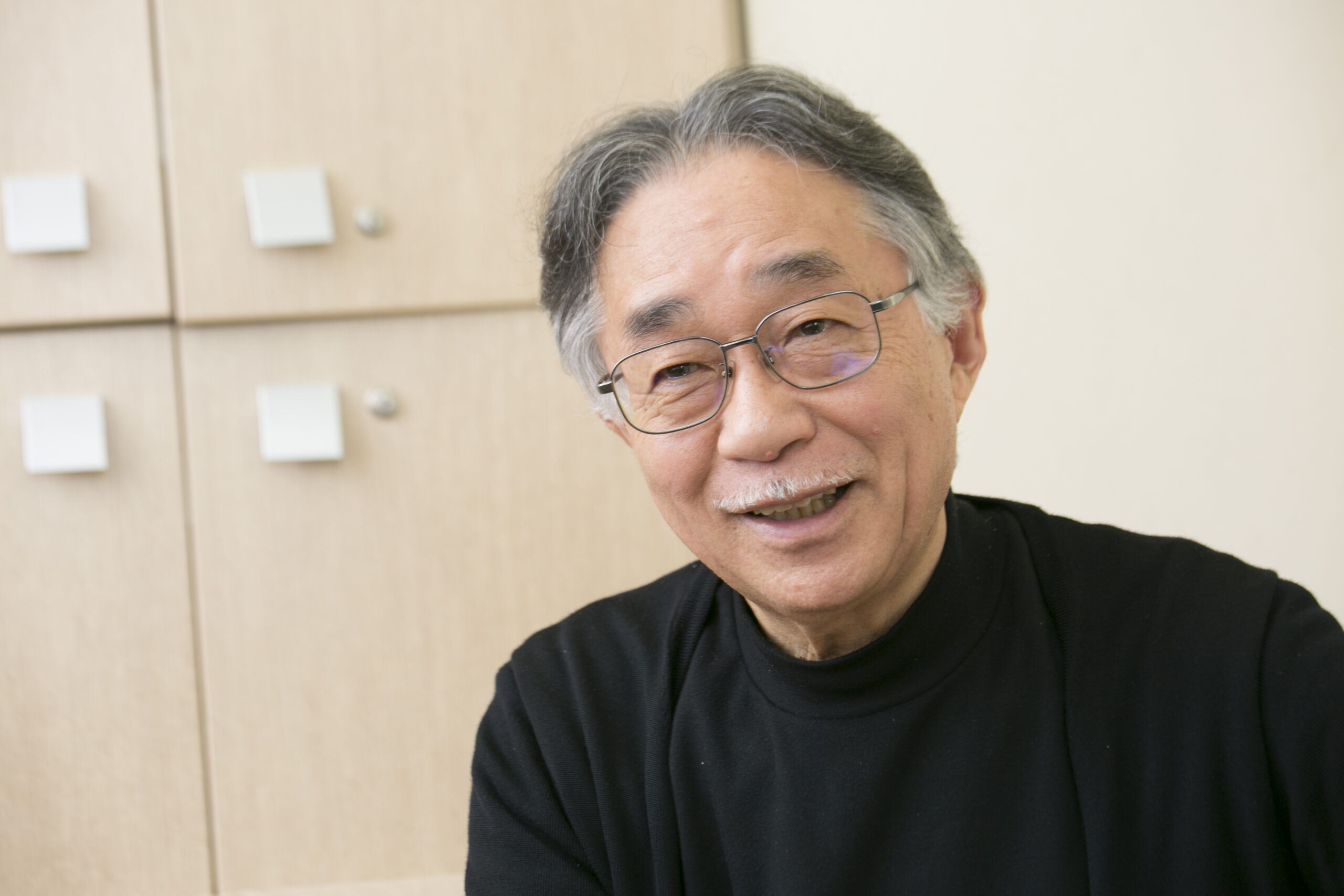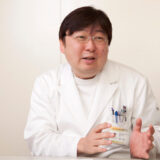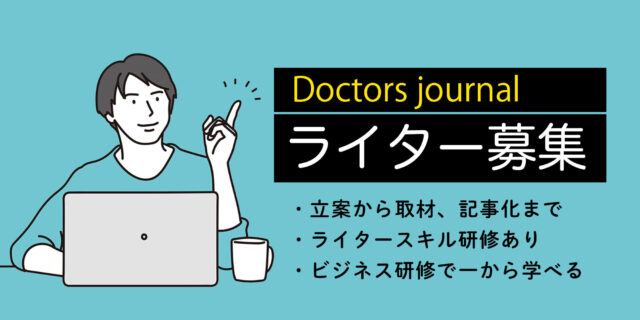#01【高瀬義昌氏】患者の家族も治療の対象として考える
2024.11.30
東京都大田区で訪問診療を中心に取り組む「たかせクリニック」院長の髙瀬義昌氏は、臨床医学の実践経験や家族療法の経験を生かし、「高齢者が安心して暮らせる街づくり」に取り組んでいます。 本記事では、高瀬氏に家族療法との出会いについて伺いました。
(記事内容は2021年に公開されたものです)
取材協力:高瀬義昌氏
- 医療法人社団至髙会理事長、医学博士、認知症サポート医
- 1984年、信州大学医学部卒業
- 東京医科大学大学院修了、医学博士
- 麻酔科、小児科研修を経て、包括的医療・日本風の家庭医学・家族療法を模索
- 2004年、東京都大田区に在宅医療中心の「たかせクリニック」を開業
- 在宅医療における認知症のスペシャリストとして厚生労働省推奨事業や東京都・大田区の地域包括ケア、介護関連事業の委員も数多く務め、在宅医療の発展に日々邁進している
- 『はじめての認知症介護』『自宅で安らかな最期を迎える方法』など著書多数
「調和」「医療」「家族」というキーワード
私は思春期に趣味でロックやジャズバンドなどの音楽演奏に熱中していました。それは、中学時代から、実は医学部を卒業するまで続きました。
常に音楽的な環境の中にいたので、漠然とではありますが、音楽におけるアンサンブルや調和は医療に活かせるのではないか、などと考えていました。
例えば、ジャズバンドではそれぞれの楽器の役回りは違いますが、全員の演奏が一致することで調和のとれた、お互いに感性を高め合えるような空間や環境が生まれます。
大学時代には、慶応大学精神科医の小此木啓吾先生による信州大学での講演や、中学の先輩である北杜夫さんなどの影響もあって、精神科医療に興味を持ちました。ですから精神科の啓蒙書なども相当読んでいました。
最初は精神科医に進むつもりでいましたが、途中いろいろな経緯があって麻酔科医の道に進みました。
ところが麻酔医として勤務をしていた最中に身体を壊してしまったことが、「本来自分がしたいことは何だったのか。」という原点に立ち返る機会となりました。
その時の私にとってのキーワードが「調和」(これは音楽的な環境に象徴される)「医療」「家族」でした。

家族療法の基本「システムズ・アプローチ」と出会う
当時、心理学の新しい流れであるトランスパーソナル心理学という考え方があり、その中の『パラダイムブック』という本に出会い、「家族療法」という精神療法に夢中になりました。
この家族療法の基本は、「システムズ・アプローチ」と呼ばれる考え方です。
誰もが他者との関わりの中で生きています。このような関係性のまとまりをシステムと見なし、様々な問題に対処するための考え方が「システムズ・アプローチ」です。この考え方は、日本のTQC(Total Quality Control)とも共通する部分があります。
手術室での麻酔医の役割は、外科医が手術を行いやすい環境を整えるために、看護師と協力して全体の調和を保つことでもあります。
手術は専門家のチームによって行われるため、ある意味では一つの組織の運営と言えます。麻酔医の仕事は、経営管理にも通じると感じていました。
ですから家族療法にあるシステムズ・アプローチという考え方は、私にとっては非常に共感できるものでした。
そんな時に、小児科医として家族療法をしてみないかというお誘いがあり、小児科診療に進みました。
【家族療法】
家族療法は、心理療法の一種で、家族全体を対象とします。アメリカで1950年代に始まり、歴史のある治療法であり、「家族カウンセリング」「家族セラピー」「ファミリー・セラピー」とも呼ばれます。患者の心の問題が家族の問題によって引き起こされる場合があり、その背後にある家族の問題を解決することで、患者の心の病気の治療を行います。特に親子関係に問題を抱える児童や思春期の患者に有効で、不登校や行為障害、家庭内暴力、反抗挑戦性障害、薬物使用などの治療に適しています。
【システムズ・アプローチ】
システムズ・アプローチとは、問題や症状そのものにアプローチするのではなく、家族を個々が互いに影響を与え合う一つの集合体(システム)と考え、全体から問題を捉え解決するという考え方です。もともと「システム理論」や「経営工学」などから発展してきたもので、企業や医療機関、教育機関など、さまざまな組織や団体の問題を解決し、よりよいシステムを実現するための方法論でした。家族療法においても家族をシステムとして捉えることで、問題行動の原因や結果の悪循環を理解し、解決に取り組みます。
(続く)