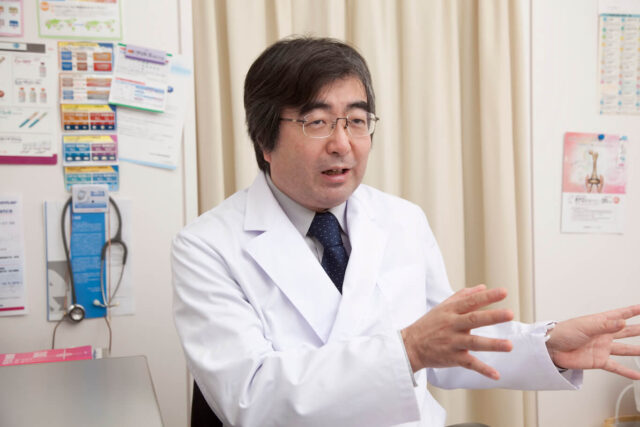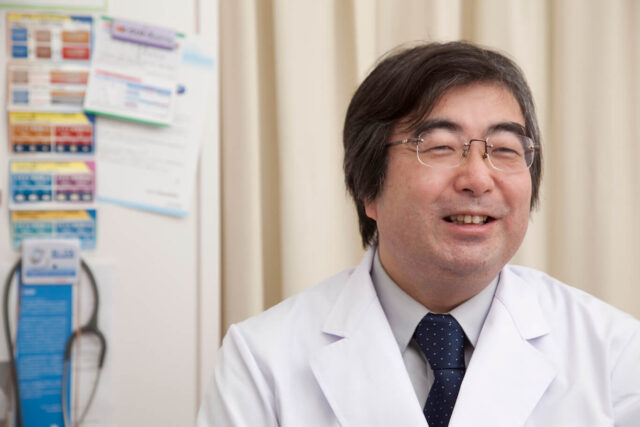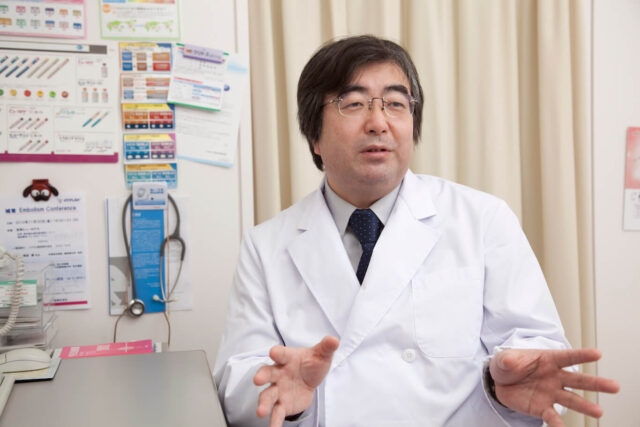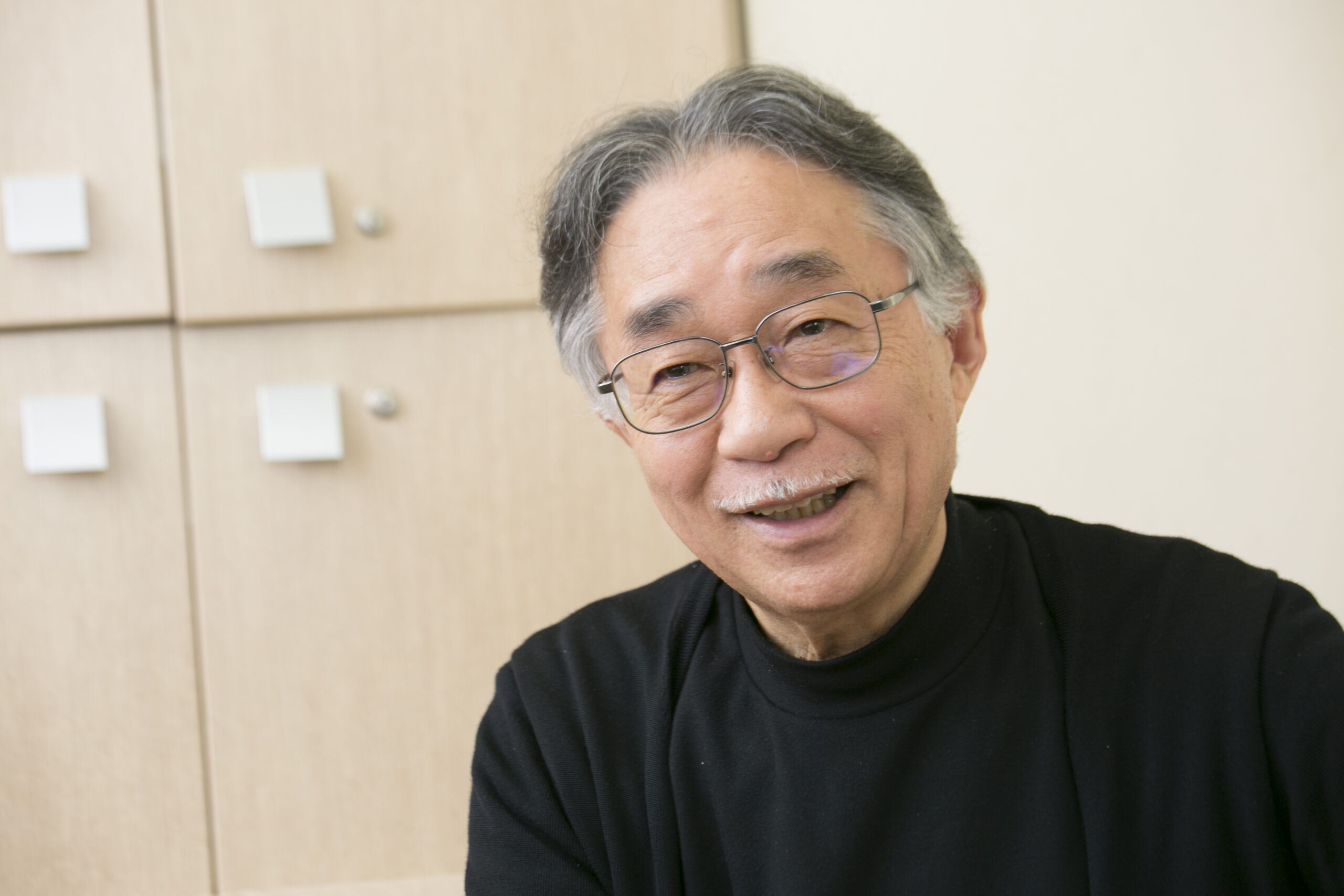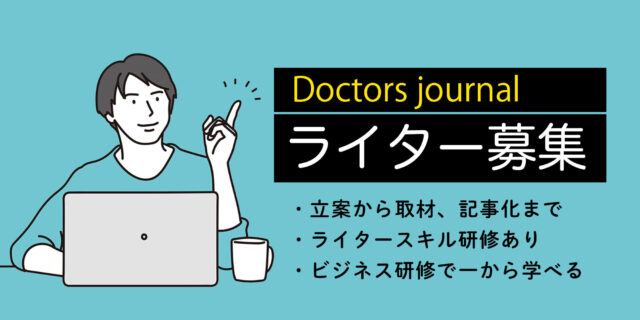#04 免疫療法が、呼吸器感染症や重症のアトピー性皮膚炎の治療にも利用できないかと考える
連載:NPO法人を設立し、アレルギー・呼吸器疾患の予防および診断・治療の普及に取り組む
2021.11.25
自己NK細胞免疫療法
蔵前内科クリニックでは手術のできない進行がん・末期がん・手術後のがん再発防止を目的とする患者さん等に、第四の癌治療として活性化自己NK細胞治療に力を入れています。
体内のがん細胞を攻撃するものとして、リンパ球中のキラーT細胞(細胞障害性T細胞)とNK細胞(ナチュラル・キラー細胞)が知られています。
蔵前内科クリニックでは、体外において、独自のNK細胞多量培養方法により培養NK細胞比率90%以上という高い培養技術でNK細胞を増やすことに成功しました。現在、この技術を活用し、自己免疫力を高めながら、各臓器における種々の癌に対する治療を試みております。
蔵前内科クリニックの特徴は、専用の培養施設を有し、院内でNK細胞の培養を行っているということです。クリニックにおいて独自でNK細胞の培養を行っているのは珍しいと思います。
その培養方法は、患者さんから採取した血液を、科学的な培養技術で細胞を刺激、活性化し、約2週間無菌状態で NK細胞(キラーT細胞も含まれています)を増殖させます。
自己NK細胞免疫療法とは、増殖させたNK細胞を再び患者さんの体内へ点滴静注にて戻すというものです。1回量で約10億~50億個のNK細胞を投与できます。
通常健康人の場合、体内に流れる血液量を約4~5Lとして、約5~10億個のNK細胞が存在します(がん患者の場合はより少ない状態です)。したがって、自己NK細胞免疫療法の1回の投与量は、約10人分のNK細胞数に相当するとも言えます。
しかも、本人の免疫細胞なので 、拒絶反応・副作用がありません。自己NK細胞免疫療法は、がん治療の新しい選択肢であり、これから第四のがん治療法として期待されます。
自分の免疫力で戦うということ
私は、この活性化自己NK細胞治療が肺癌同様、呼吸器感染症および重症の喘息やアトピー性皮膚炎患者さんの治療として利用できないかと考えています。これは十分根拠のある新しい取り組みだと思っています。
また、季節によってインフルエンザが流行ってきますが、重篤な呼吸器感染症、例えば鳥インフルエンザやSARSのような、現行の治療法では有効性が確立されておらず、強力な毒素に対して治療薬がないという厳しい状況の中では、自分の免疫力で戦うしかありません。
そのような緊急時には、NK細胞免疫療法が有用だと考えます。NK細胞は、癌細胞にも、ウィルスにも有効ですので、根治治療の他に、事前に投与する事で予防効果が得られると考えています。
しかし先にも述べたようにNK細胞の培養には2週間の時間が掛かります。事前に培養した自己NK細胞の投与によるウィルス感染予防は可能ですが、いざ罹患してからでは、2週間の培養期間は手遅れとなってしまう可能性も危惧されます。
現在、患者さんの血液サンプル(単核球)を冷凍の形で事前に採っておき、必要な時に応じて、NK細胞を培養できる仕組みが整い実行しています。
今後は培養したNK細胞の感度を落とさず、保存できるシステムが確立すれば、緊急時の治療も可能になり、さらなる発展に繋がると思います。