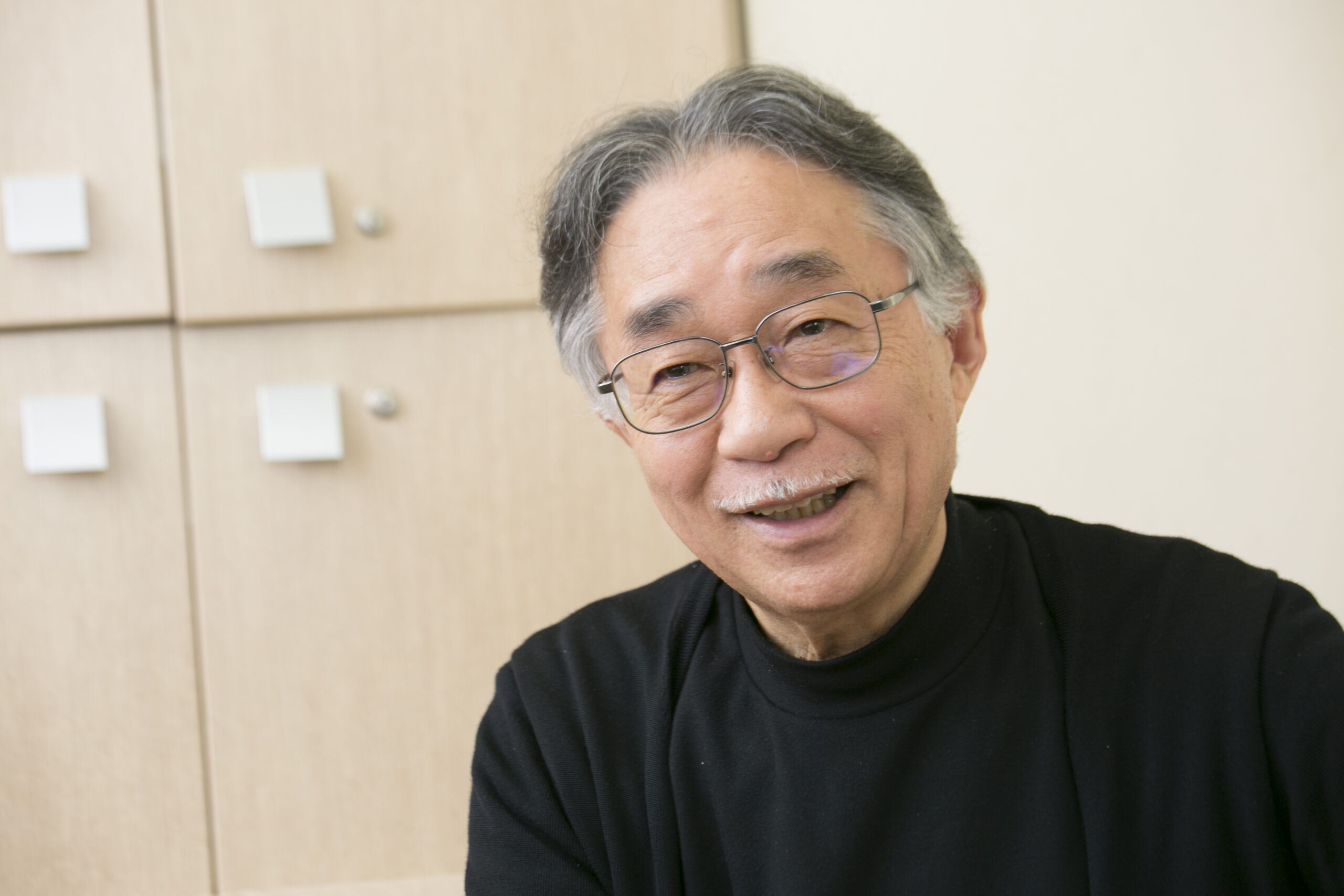#02 最初の頃は、ホスピスケアはなかなか理解されなかった。
連載:ホスピスケアをムーブメントと捉え、 患者の権利が基本の在宅ホスピスケアに取り組む
2021.02.26
病院から脱出した患者さんが駆け込んでくる
現在は、地域の連携病院と良好な関係の下で、多くの患者さんが病院からの紹介で来院されますが、最初の頃は、私がおこなっているホスピスケアは、病院や開業医、患者家族からもなかなか理解されませんでした。
初めの頃は、患者さんも少なく、病院から脱出してくる患者さんがパラパラと駆け込んでくるというような状態でした。
時には患者さんや家族から相談されて、私がそれを手助けすることもありました。
― エピソード.1 ―
小笠原医師がペインクリニック小笠原医院を開業してまもない頃、病院に入院している膀胱がんの大手術を行った50歳代の男性患者から、「のたうちまわるような痛みがあるのに病院の医師がまったく痛み止めをしてくれずとても辛い思いをしている。」という相談を受けた。
小笠原氏は、知り合いだったその患者の主治医に対して、患者の痛みの緩和を求めるが、主治医は極めて弱い鎮痛剤を1錠出したのみだった。当然、痛みは取れなかった。
手術から半年以上もそんな状態に置かれていて、本人が退院したいと訴えても、「こんな状態では帰せない」と主治医は認めない。
なんとしても自宅に戻りたい。最期は自宅で迎えたい。という、その患者の懇願を受けた小笠原氏は、患者の知人や家族と協力して、夜明け前に患者をワゴン車に乗せて病院から強制的に退院させた。いわば病院からの脱走ともいえる。
自宅に戻った患者に翌日からモルヒネを投与すると、2日目にはほとんど痛みがとれ、それから最期を迎えるまでの2カ月間を、奥さんと2人だけの生活を楽しみ、「2度目の新婚生活です」と、とても喜んでもらえたという。
山村のへき地医療を守り抜いた叔母の姿
私の叔母は新潟のへき地で開業医をしていました。
夫が結婚1年足らずで亡くなってしまうのですが、その後も、雪深い新潟の山奥の山村の医療を50年間、75歳で引退するまで一人でずっと守っていました。高校時代からその叔母の跡を継いでほしいとは言われていたのですが、理科が嫌いでしたでの、大学は経済学部に進みました。
しかし経済学部を卒業した後の、自分の将来像にやりがいや興味が見いだせずに悩んでいた時に、へき地医療で地域住民に貢献した医師だった叔母のことを思い出し、親にわがままを言って、群馬大学の医学部に入り直しました。
入学当初から、私にとっての医師のイメージとは、病院などで先端医療などに取り組む医師ではなく、叔母のような地域医療に取り組む医師でした。
1976年に群馬大学医学部を卒業した後は、麻酔科に入りました。当時はまだ総合診療科などはなかった時代で、麻酔科であれば幅広くトータルに患者さんの病気や病状を見ることができ、そこで数多くの現場を経験しておけば、将来自分の目指す医療に役に立つのではないか、という考えがあったからです。

緩和ケアに取り組むひとつのきっかけ
麻酔科にいたときに、麻酔科医としてがんの患者さんの痛みを何とかしてほしい。という要請がありました。つまり、麻酔科医だから痛みを何とかしてくれるだろうと思われていたわけですが、当時のわたしにはそんな経験は殆どありませんでした。
その後1982年に長野県の総合病院に初代麻酔科医長として赴任しました。そこには、上顎洞がんの痛みで苦しんでいて、麻酔科の専門医が来るのを待っていた、という患者さんが入院していました。
それまでの日本では、モルヒネを経口で飲ませるなど、とんでもないことと考えられてきましたが、ちょうどその当時、モルヒネの経口投与がイギリスから日本にやっと伝わった時期でもありました。
そこで、病院の薬局でモルヒネを処方させ飲ませたところ劇的に効果があり、その患者さんから大変喜ばれました。そんな経験から、疼痛の治療にやりがいを感じ始めました。それが緩和ケアに取り組むことになったきっかけの一つです。
麻酔医を続けることに疑いや迷いを持った
もう一つのきっかけが、当時多く行われていたがんの外科手術に疑問と憤りを持ったことです。病院で麻酔科医に要望されることとは、あくまでも手術のための麻酔です。
麻酔科医が手術の患者さんに麻酔をかけるということは、麻酔をかけて手術中を安定的に経過させ、術後無事に覚醒させ、良い状態で帰してあげる。ということが役割であり、またそれが麻酔科医のやりがいにもなるわけです。
しかしそれはあくまでも、手術が患者さんのために必要で役に立っているということが大前提としてあるわけです。
その頃、それまで難しいとされていた内臓のがんの手術が、あれも取れる、これも取れるということで、肺がん、食道がん、肝臓がん、すい臓がんなどが、どんどん手術の対象となっていきました。
私は当時のことを、がん外科のバブルの時代と呼んでいます。しかし、食道がんの術後の患者さんの中には、病棟に帰ることもなくそのまま亡くなってしまう術後死の人も多くいたのです。
にもかかわらず、執刀医はそのことに疑問すら感じていない。外科医の中には、自分で切りたい。執刀症例を増やしたい。と考えている人が多くいます。
当時は、そのような手術の症例が論文や学会で取り上げられ始めていた時期でもあり、彼ら医師たちの生きがいは、症例を集め論文を発表することだったのです。
このような状況の中で私は、この実状は決して患者さんのためになっていない。と強い怒りを覚え、このまま麻酔医を続けることにも疑いや迷いが膨れ上がってきてしまいました。
ホスピスケアで患者さんの役に立ちたい
そんな中での一人のがん患者さんとの出会いが、ホスピスケアの分野で患者さんの役に立ちたいと思った出発点でした。
― エピソード.2 ―
一人の70歳代後半の胃癌の患者さんがいました。
着実に弱ってきてはいましたが症状もさほどでなく外泊を希望され週末になると二泊三日、家に帰り過ごされていました。
しかしそれが何回か続いた後、とうとう家に行ったきり戻ってこなくなってしまいました。仕方なく看護師を訪問にやり、私も週一回往診をして見守っていました。
家にいる患者さんの顔は病院で見る顔とは全く違うものでした。のびのびとわがままで笑い声の絶えない暮らしぶりで、ああこれがこの方の本来の姿なんだと、入院中は様々な制約の中でさぞかし不自由な思いをしていたんだろうなと納得したものです。
結局その方はそのまま自宅で最期を迎えられ、私の自宅看取り第一号となったのです。それ以来、人はどんな状態でも住み慣れたところにいるのが一番いいんだ、と日々思い続けてきました。( ホームページより )