#04 緩和ケアは、末期がんの患者さんに限ったものではありません。
連載:ホスピスケアをムーブメントと捉え、 患者の権利が基本の在宅ホスピスケアに取り組む
2021.03.03
多くの病院医療者が緩和ケアを誤解している
私は、緩和ケアは特にがんの患者さんに限った治療ではないと公言しているのですが、来院される患者さんはがんの人が多く、結果的に緩和ケアを必要とされる末期がんの患者さんを多く診るようになりました。
多くの病院医療者は、緩和ケアは末期がんの患者さんが対象と思っています。
そのために、他の疾患で緩和ケアを必要としている患者さんの病院からの紹介は、なかなか増えません。
その背景には、他の疾患の場合は、がんのようにこれ以上の治療は無理ですという線が引きづらい。という理由があります。
肺気腫とか慢性心不全などでも、これ以上の病院治療は無理という一線があるはずなのですが、現実には病院はその判断をしません。その患者さんたちを緩和ケアの対象と考えません。
いまだに病院ではぎりぎりまで治療を行う
また、がんも早期からの緩和ケアが必要といいながらも、いまだに病院ではぎりぎりまで治療を行います。
もう打つ手がないというところまでとことん治療を行い、ぎりぎりまで来てから、後は緩和ケアということになります。
その結果、私どもに紹介される患者さんも、ほとんどが末期がんの患者さんということになります。
患者さんは、このまま緩和ケア病棟に移るか、それとも在宅緩和ケアを受けるかの選択を迫られ、在宅緩和ケアで当クリニックを紹介されて来院される、というというパターンが多いのです。
入院で病状がさらに悪化することがある
人にとって、入院することは非日常の際たるものです。帰るあてのない入院は、本人にとって本当につらいはずです。
しかも、病室の中の狭いスペースで他の入院患者さんや医師や看護師に気を使い、日常を全て管理されるわけです。そのような環境に置かれればいろいろな影響が出てきます。
特に今は高齢の患者さんが多い。高齢の患者さんは容易に「せん妄」を引き起こします。そうなると拘束されてしまいます。
また、家族からの要望で、「せん妄」を起こす患者さんを入院させるという事例もよくあるのですが、多くの場合、さらに「せん妄」が悪化してしまいます。
「せん妄」にとって一番の悪化因子は環境の変化です。入院することでさらに病状が悪くなることもあります。
患者に一番プラスの影響を与えるのは家の力
患者さんが自分の家に帰ると痛みの訴えが減ります。それから笑顔を取り戻します。
当クリニックに来る研修医を在宅緩和ケアに連れて行くと、自宅で患者さんが笑ったり、冗談を言ったりしている姿を見て、彼らは一様に「末期がんの患者さんが、あんなに笑顔でいられるのですか。」と、とても驚きます。
彼ら研修医が普段病院で見ている末期がんの患者さんたちは、暗い顔をして、うつろな目で天井を眺めている人たちばかりです。
それが彼らの持つ末期のがん患者さんのイメージなので、全く違う姿にとても驚くのです。
自分の家には自分の暮らしがある
患者さんに一番プラスの影響を与えるのは家の力だと思います。自分の家には自分の暮らしがあるからです。
患者さんが自分の居る場所が定まり、そこが居心地の良いところであれば、それでもう穏やかに最期を迎える心は定まるのだと思います。
これは在宅医療に携わっている医師でないと分からないことです。
逆に、病院のマイナスの力も大きいといえます。
病院の緩和ケア医は、どちらかといえば病院の医師と同じメンタリティーを持っていて、緩和ケア病棟では、患者本位よりは、医師主導の緩和ケアが行われるからです。

病院には自分の暮らしがない。
私が診た緩和ケアの患者さんで、緩和ケア病棟と在宅緩和ケアの両方を経験している患者さんが何人もいます。
その方たちに、一般病棟での治療と自宅での治療のどちらが良いか聞くと、皆さん当然自宅のほうが良いといいます。
では緩和病棟はどうかと聞くと、限りなく一般病棟と変わらない。というのです。中には緩和病棟よりも一般病棟のほうが良いと答えた患者さんもいました。
これは何を意味しているのでしょうか?
また、緩和ケア病棟で「せん妄」を起こしてしまった患者さんがいました。
対処に困り果て、医師からは、もう眠らせるしかない。という話が出た時に、家族が「かわいそうだから、それならば家に連れて帰ります。」ということになりました。
ところが家に帰った翌日から、その患者さんの「せん妄」が無くなったのです。
おそらくメンタルな面が大きく、私はこれを「入院せん妄」だと思っています。
患者さんからのSOSで病院から家に連れ戻す
ある患者さんの事例ですが、この方は病院に入院していた80歳代の男性で、「せん妄」を起こしているということで拘束されていました。
しかも誤嚥の可能性もあるということで、経口での食事はさせてもらえず、そのような状態が1週間ほど続いていました。
見かねた奥さんから私はSOSを貰い、半ば強引にその男性患者さんを病院から自宅に連れ戻しました。
自宅に戻られたその患者さんは、家族にありがとうと感謝しながら、おいしそうに水を飲み、翌日には気持ちよさそうに訪問入浴も受けていました。
私は、そのような病院から自宅に戻ってきた患者さん達の笑顔をたくさん見てきました。
緩和ケアは、患者さんの痛みをとるだけと思われがちですが、決してそうではありません。行き過ぎた医療に対するアンチテーゼでもあるのです。
大きく変わってきている最近の家族の在り様
当初、病院から連れ戻していた患者さんの特徴は、本人や家族の意識が高く、家族関係が非常に良好で、経済力もある、仲の良い夫婦とか、関係が良い3世代家族で高齢者の面倒を見る家族がいる、というような恵まれた人達でした。
しかし今は大きく変わってきていて、家族関係も実に様々です。
また驚くべきことに、在宅医療をしていて、中年の引きこもりの子供がいる家庭が実に多いということに気付きます。
彼らはロスト・ジェネレーション世代で、特に障害とかがあるわけでなく、人生のどこかで失敗して社会に出らなくなっている人たちです。
それと貧困層の多さも最近の特徴です。
さらには高齢者が増えているので認知症も増えています。今、在宅医療では認知症は避けて通れなくなってきています。
中には介護者が認知症というケースもあります。
例えば高齢者の夫が認知症で入院している場合、本人が家に帰りたいと言っても、家にいる介護者の妻に軽い認知症があったりすると、自宅での介護は無理と判断し患者さんを退院させません。
病院が考える家族の介護力とは、看護師の代わりを行うようなイメージですが、そんなことは決してありません。
そのような環境でも、在宅ケアがきちんと関与することで、患者さんの生活が上手くいくこともあるのです。












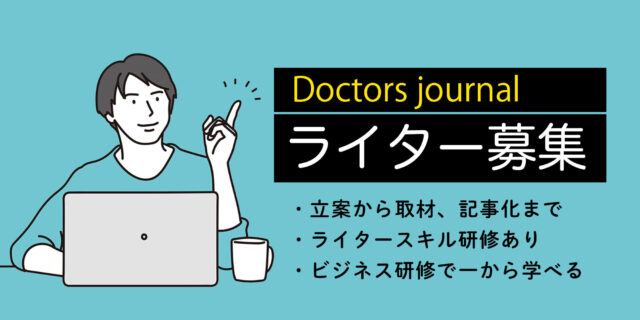


























森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター