まるでこだわり農家。患者のNK細胞ごとに最適化されたANK療法とは。
連載:【可能性の扉をもう一つ】リンパ球バンク社のがん治療法「ANK療法」とは?
2022.09.15
今回取材を引き受けてくださったのは、リンパ球バンク株式会社の代表取締役社長の原田広太郎さんと、広報担当の斎野千栄子さんのお二人です。
原田さんのお父様は悪性リンパ腫で余命宣告を受けた際、当時はまだ京都大学で研究段階にあったANK療法を受け、その効果を実感。他のがん患者や開発医師たちと共にこの治療を普及させる目的でリンパ球バンク株式会社を創業しています。
現在は原田さんがその思いを受け継ぎ、患者目線に立ち、がん患者本人が治療を選択できる社会を目指していきたいとの思いでANK療法の普及に尽力されています。#1ではANK療法がどのような治療法か、科学的な見地から教えていただきました。

ANK療法とは
——ANK療法とは、どのような治療法ですか?
原田さん(以下、敬称略):がん患者さん由来の、活性化させながら増殖させたNK細胞を体内に戻し、がん細胞を攻撃させるがん治療法です。まず、患者さん本人の血液5~8Lを体外の装置に循環させ、リンパ球を取り出します。それらを2~4週間培養し、リンパ球の中のNK細胞だけを活性化させながら増殖させます。活性化と増殖の両方を実現することを、私たちは「増強された(Amplified)」と呼んでおり、ANK療法のAはその頭文字です。

原田:ANK細胞は静脈への点滴で体内に戻され、主に3つの仕事をします。
1つ目の仕事は、がん細胞を正確に認識・攻撃することです。標的を覚える学習プロセスは必要なく、また、正常細胞は傷付けない能力を持っています。
2つ目の仕事は、元々体内にあるNK細胞を活性化することです。がんは自身にとって厄介なNK細胞を眠らせながら増殖するため、進行がん患者さんの体内のNK細胞の活性が下がっていることがあります。ANK細胞はそのようにして活性が低下したNK細胞を叩き起こすように、免疫刺激系のサイトカイン類を大量に放出します。
3つ目の仕事は、活性化されたNK細胞が放出する免疫刺激物質を介してT細胞の一種であるCTL(キラーT細胞)を活性化することです。その中から体内のがん細胞を攻撃するタイプのものが増殖してくることが期待されます。
——免疫細胞には複数の種類がありますが、どうしてNK細胞のみを増強させるのでしょうか?
原田:がん細胞を傷害できる免疫細胞は主にNK細胞とCTLですが、CTLはがん細胞への攻撃にMHCクラスⅠ分子を必要とします。また、CTLはMHCクラスⅠ分子にある微細な型が自分の持つ型と合えば、相手ががん細胞か正常細胞かを問わずに傷害します。一方、適切に活性化されたNK細胞はMHCクラスⅠの有無に関わらず、がん細胞を傷害できます。さらに、活性化させたNK細胞とCTLを比較すると、前者の方が明らかに傷害能力が高かったのです。

——取り出されたリンパ球の中からNK細胞だけを活性化させながら増殖させるというのは、難しそうに思えます。何か工夫があるのでしょうか。
原田:確かに難しいです。取り出されたリンパ球には、T細胞の方がNK細胞よりも多く存在し、かつT細胞の方が増殖スピードが速いため、通常の培養方法では、培養器のほとんどがT細胞で埋め尽くされるという事態になります。
ANK療法では、血液を5~8L循環させてそもそもの採取量を増やし、数が少ないという問題を克服しています。また、NK細胞の増強に最適な環境とするため、熟練の技術者が毎日顕微鏡で観察し、状態を把握、頻繁に最適な培地に交換しています。患者によってその細胞も異なるため、培養条件をプロトコル化することはできません。
——毎日観察……、大変ですね。特殊なプロトコルがあるのかと思っていました。まるでこだわり農家のようですね。
原田:このように活性化と増殖の両方を実現させることで初めて、がん細胞を圧倒する戦力を用意することができるのです。
開発の経緯
——ANK療法はどのように開発されたのでしょうか?
斎野:1984年に米国国立衛生研究所NIHが、免疫細胞療法の大規模な臨床試験を行いました。先ほどの話にあったように、NK細胞は培養が難しいため、大量に採取すればいいというわかりやすい発想のもと、一人の患者さんから3日もかけて延べ数十リットルもの血液を体外に循環させ、リンパ球を取り出しました。その後、3日間高濃度のインターロイキン2で刺激したリンパ球を患者の体内に戻すLAK療法が行われました。
すると、抗がん剤が効かなくなった進行がん患者さん数百人全員に、大きな腫瘍組織が一気に消えるなどの何らかの効果が見られました。しかし、大きな腫瘍が一気に壊死するとき、大量のカリウムが飛び出し、心停止する危険があります。そのため、治療はICU(集中治療室)を占拠して行われ、非現実的なコストがかかってしまいました。
——有効性があることもわかったが、実用化には課題があることもわかった、ということでしょうか。
原田:はい。その後、現場で臨床試験を指揮していたNIHのロッテ医学博士は当社創業者である勅使河原計介医学博士に「NK細胞の活性を高め、その活性を維持しながらNK細胞だけを選択的に増殖できればがん治療は変わるのだが、その培養は難しい」と悩みを打ち明けました。勅使河原博士は日本に帰国後、大久保祐司医師と共同で、複雑な培養技術を組み合わせたANK療法を完成させました。
——NIHが行ったLAK療法では、大きな腫瘍組織の壊死が心停止のリスクをもたらしたとのことでしたが、ANK療法ではこの課題も解決できたのでしょうか?
斎野:はい。一度に細胞を戻すのではなく、週2回を原則として、12回に分割投与することで強い治療強度と安全性の両立を実現しています。この分割投与は危険性を排除するだけでなく、6週間NK細胞の活性を有効域に保つことも狙いとしています。
お問い合わせ
次回の記事では、ANK療法の副反応や標準治療との併用についてお伝えします。
リンパ球バンク株式会社:https://cell-therapy.jp/




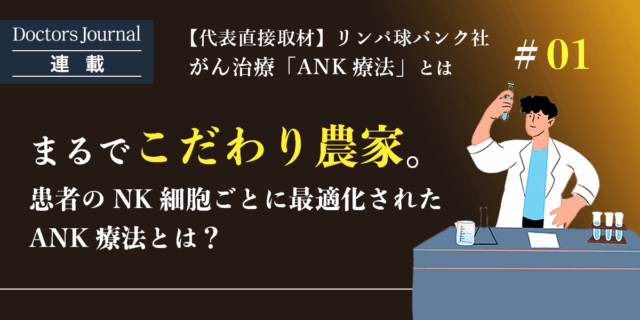
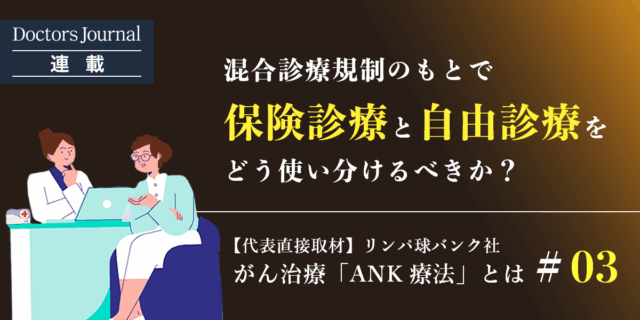





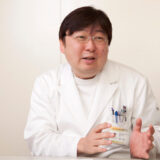






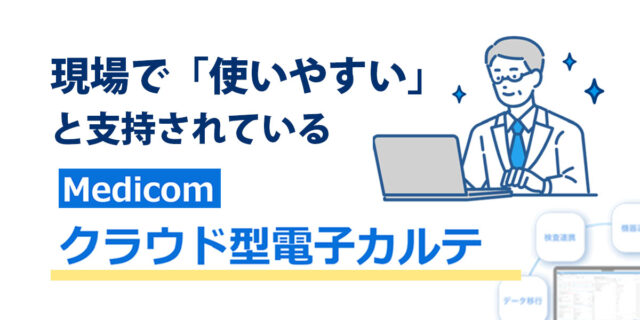























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)
