増強された細胞を投与したとき、体はどう反応するのか。
連載:【可能性の扉をもう一つ】リンパ球バンク社のがん治療法「ANK療法」とは?
2022.10.13
#2ではANK治療に伴う副反応や臨床での活用についてお聞きしました。広報担当の斎野さんは、実はANK療法を治療に取り入れた経験があるとのことで、生の声をお届けします。また、抗がん剤や分子標的薬との併用についてもお聞きしました。
ANK治療を受けての感想
——ANK細胞を点滴した後、現れる症状は主に発熱と悪寒とのことですが、斎野さんが治療を受けられたときはどうでしたか?
斎野:7年前、乳がんを患ったときにANK療法を併用しました。NK細胞は手術前にとっておき、手術後にANK細胞を投与しました。点滴数時間後から発熱が始まりましたが、その間は、電解質を含む水分を摂取して寝ておけば大丈夫という感じでした。眠気があり、ぼーっとすることはありましたが、それ以外に違和感はなく、食欲も変わらずありました。週2回点滴しなければなりませんが、1回を土曜日に、1回を平日に、という感じでした。私は平日1日のお休みをもらって、それ以外は普段通りに生活できていました。
——原田さんのお父様もANK療法を受けられていたとのことですが、当時お父様はどのような感じでしたか?
原田:点滴後、30分程度悪寒が続き、その後発熱が続いていました。でも、スポーツをした後のような汗のかき方でしたね。斎野が言うように、発熱している数時間は寝てしまえば大丈夫だと思います。ただ人によっては3~4日程度の微熱が続くことがあります。腫瘍熱が混じっている可能性があるので、一概にどこまでがANKによる副反応かは断定できません。
——そのような発熱や悪寒はどうして起こるのでしょうか。
原田:ANK細胞が放出するインターフェロンなどの免疫刺激物質によるものと考えられます。患部痛、吐き気、腫瘍部位の痛みが起こることもありますが、これらの副反応を工夫して乗り切ることが大切です。1、2回目を乗り越えられるかどうかが鍵で、数回繰り返すうちに和らいでくることも多いです。車椅子で来ていた患者さんが歩いてきたときは驚きましたね。

標準治療との併用
——多くのがん患者は標準治療を受けていると思いますが、それらとANK療法の相性について教えてください。
原田:標準治療と併用する場合は、まずリンパ球を採取してから標準治療を受け、その後ANK細胞を点滴で戻すという流れが理想です。
抗がん剤とANK療法を併用する場合、抗がん剤の投薬後3日~10日程度空け、体内の抗がん剤濃度が低下したタイミングでANK療法を行います。その理由は、抗がん剤は活性の高いNK細胞もターゲットになってしまうためです。更に、抗がん剤で肝臓の細胞がダメージを受け、それをNK細胞が異常細胞と認識して攻撃するリスクを避けるためです。抗がん剤とANK療法を併用する際は、ANK通常量の半分量を点滴するという方法を推奨しています。
リンパ球採取は抗がん剤の影響が少ない内に行った方が有利です。抗がん剤はがん細胞だけでなく、NK細胞を含む通常の細胞にも取り込まれます。抗がん剤は細胞が分裂するタイミングで作用します。そのため、抗がん剤を取り込んだNK細胞を活性化したとしても分裂の段階で死んでしまうことが考えられます。その結果、活性の高いNK細胞の数を揃えることができなくなります。
斎野:局所にある腫瘍組織に対する外科手術や重粒子線、また、増殖の活発ながんに対する抗がん剤や放射線療法は、初期の打撃力は絶大であることは確かです。しかし、生き残ったがん細胞が暴れて再発・転移となったらお手上げになってしまいます。
一方で、ANK療法は少ないがんにとどめを刺すのは得意ですが、がんの数が多いと治療回数が多くなって費用がかさみます。標準治療を割り算に、ANK療法を引き算に例えるとわかりやすいですね。割り算でざっくり削った後、引き算でゼロにする。割り算である標準治療よりも前にNK細胞は採取した方が良いので、がんとわかったらすぐに相談していただくのがベストです。
——ANK療法と相乗効果を発揮するような治療法はありますか?
原田:分子標的薬がANK療法と相乗効果を発揮すると期待されます。分子標的薬の概念は抗がん剤と異なり、がん細胞を直接傷害するのではなく、がん細胞の増殖にブレーキをかける、もしくは血管新生を阻害するなどして、免疫システムががん細胞を排除するのを待つことです。NK細胞は一部の抗体に結合する性質を持っているため、分子標的薬の中でも抗体医薬品は、NK細胞ががん細胞を効率的に見つける手がかりとなります。このような抗体を介したがん細胞への攻撃をADCC活性と呼びます。

原田:例えば、トラスツズマブ(*商品名:ハーセプチン)は乳がんに適用されているから「乳がんの薬」というイメージを持たれがちですが、実際はHER2というタンパク質を発現しているがんに対してなら効果を発揮すると考えられます。そしてHER2は食道がん、前立腺がん、肺がん、大腸がんなどでも、高い確率で過剰発現しています。薬は保険診療の中では適用が認められている場合にしか用いられませんが、自由診療においてはその限りではありません。HER2陽性かどうかは血液検査で調べられるので、簡単です。もちろん、こうした分子標的薬の利用は治療の援軍になると考えられる場合のみ推奨されるもので、ANK療法受診の必須条件ではありません。
お問い合わせ
次回の記事では、保険診療と自由診療の使い分け・組み合わせという実践的な治療設計についてお伝えします。
リンパ球バンク株式会社:https://cell-therapy.jp/



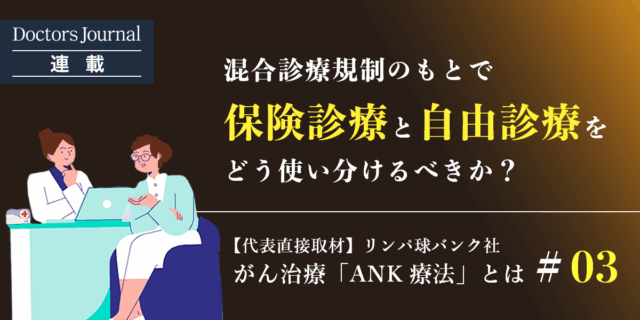
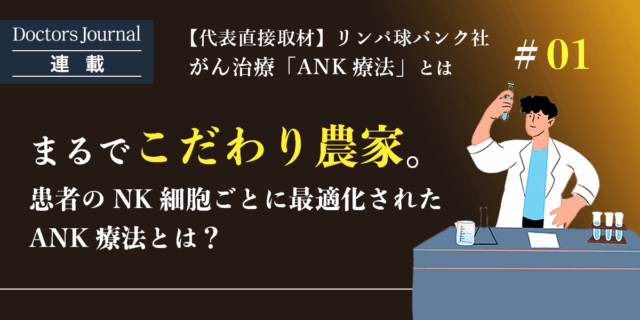
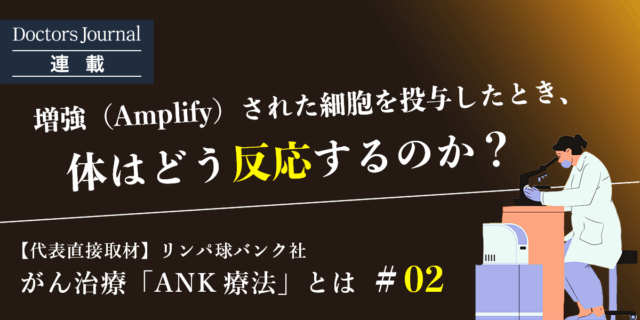
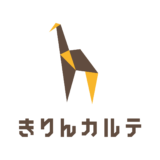



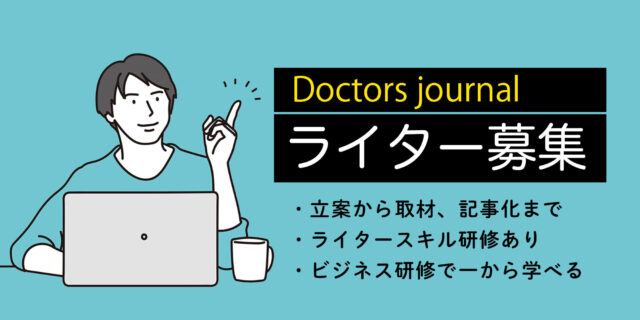


























森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター