#02 国内初の認知症本人による「日本認知症ワーキンググループ」
連載:―認知症レポート―「私たちはいかにして『声』を獲得したか」
2020.07.24
日本のオレンジプラン
一方、日本においては、2012年年6月18日に厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチームが発表した「今後の認知症施策の方向性について」と同年9月5日に発表された「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)において、従来使われていた「認知症患者」が「認知症の人」に、「認知症対策」が「認知症施策」と改められました。
遡れば、その前には痴呆と呼ばれていた時代が長くありました。
これに関して当時、のぞみメモリークリニックの木之下徹医師は、「今回、厚生労働省の発表の中で、「認知症患者」ではなく「認知症の人」、「対策」ではなく「施策」という言葉が使われていますが、これはとても大きな意識変革だと思います。
何気なく使っている言葉であっても、その背景にある意識や思想を考えたときに、言葉の選択というのはとても重要です。言葉が変わると、考えや行為が変わってくるのです。」と語っています。
認知症と診断された当日から始まる支援
2009年には、最大の成果としてスコットランドの認知症戦略の策定に参加し、「認知症と診断された当日から始まる支援」を実現させました。
これはスコットランド政府が、認知症の診断を受けた本人やその家族に対して、認知症のリンクワーカーによる支援を1年間保証するという制度です。
認知症医療の現場では「早期診断・早期絶望」と言われるような状況が多くあります。早期に認知症と診断されると、絶望でうつになる人も多い。かつてのマキロップ氏もその一人でした。
この制度は、そのような人たちに生きる希望を与え、認知症と診断された後も、より良い生活を続けることができるように支援することを、国が保証するというものです。
最初からワーキンググループの活動が順調に進んだわけではなく、当初は多くの無理解や差別から拒絶されたことも多かったといいます。それでも彼は諦めずに、気付いてくれるまで根気よく社会に対して門をたたき続けました。
彼らは活動の手法を、主張する事よりも、理解して同意してもらうことに重きを置いてきたといいます。
「あれをしてくれ!と声高に叫ぶのではなく、こうしてみては如何でしょうか?こんな選択肢もあるのでは?と合理的に訴えかけていきました。すると次第に私たちを受け入れ、耳を傾けるようになっていったのです。」とマキロップ氏は語ります。
2007年には、ヨーロッパ・アルツハイマー協会に対して認知症当事者グループの設立を提案し、2013年にはヨーロッパ認知症ワーキンググループが設立されました。その結果、多くの認知症の当事者たちが声を上げ始めました。

「日本認知症ワーキンググループ」
日本では2014年10月11日、佐藤雅彦氏、中村成信氏、藤田和子さんの3人が共同代表となって、国内初の認知症本人による全国組織「日本認知症ワーキンググループ」を設立しました。3人とも若年認知症の当事者です。
日本認知症ワーキンググループは設立趣意書の中で、「認知症の人本人をメンバーとし、認知症の人と社会のために、認知症の人自身が活動していく日本初の独立した組織です。
海外で先駆的な活動を進めている各国の「認知症ワーキンググループ」と連携し、国内の認知症関連の諸団体と友好的な関係を築きながら活動します。」と謳っています。
藤田和子さんは2014年11月に日本で行われた「認知症サミット日本後継イベント」のスピーチの中で、このように述べています。
「認知症についての偏見は残念ながらいまだ根深く、日常生活の中で 私自身も経験します。(中略)「認知症になったら何も分からない」「何も出来ない」という偏見は認知症と診断された人自身を蝕み、生きる気力を奪います本人だけでなく、家族も、社会から孤立します。診断を受けるのが怖くて、病院に行けず苦悩する人が大勢います。(中略)認知症の本人が声をあげるには、認知症による生きづらさや不安、偏見などさまざまな障壁があります。周囲の理解と協力が欠かせません。私たち認知症の本人が、それぞれの人生を「ひとりのひと」として生き抜くために、行政や他の人にお任せして頼りきるのではなく、私たち自身が、頑張らなくてはならない。認知症を考える人たちと、一緒にやっていきたい。困難な道を拓く決意をし、最初の一歩を踏み出したのは、そう、考えたからです。」(3つの会@webより抜粋転載)
希望と尊厳をもって暮らせる社会の実現にむけて
2014年10月23日には、日本認知症ワーキンググループは塩崎恭久厚生労働大臣に提言を行いました。
その「認知症施策の推進に向けた認知症本人からの提案~ 希望と尊厳をもって暮らせる社会の実現にむけて ~」の中で、以下の3点を提案しています。
- 認知症施策等の計画策定や評価に、認知症本人が参画する機会の確保
- 認知症初期の「空白の期間」解消に向けた本人の体験や意見の集約
- 認知症の本人が希望をもって生きている姿や声を社会に伝える新キャンペーン
長年にわたり、若年認知症の診療に取り組んでいる南魚沼市ゆきぐに大和病院の宮永和夫氏は、「若年認知症の当事者が抱える苦労の典型例として、
- 精神疾患同様に差別や、周囲の理解が乏しい。
- 家族が理解していないので、虐待や放置、閉じ込めが行われる。
- 医療の無理解、誤診の多さとその後の治療先がないこと。
- 福祉の無理解、対応の困難さと拒否。
- 行政の無理解、社会保障制度の利用制限や申請制限。
などが挙げられます。ボランティアなどの社会活動の場や、自己実現できる場、社会参加の場があることは、診断されてからも長い期間を生きなければならない当事者にとって生きる張り合いになります。」
と指摘しています。
今や認知症は、他人ごとではなく自分事です。
今まで認知症について語られる場合、多くは医療側や介護者側からの発信であって、当事者の言葉に耳を傾けることはありませんでした。
認知症のケアといっても主に介護者の視点に立った支援であり、必ずしも認知症の本人が望むケアとは言えない状況がいまだに多くあります。
そこには、社会の認知症への無理解や偏見、スティグマがあるからです。
その上、認知症の人達の発言に対して、時には嘘つき呼ばわりや否定されたりすることも事実としてあります。
しかし、認知症による生活のしづらさや苦しさを一番感じているのは介護者以上に、認知症の当事者の人たちです。
今や認知症は、他人ごとではなく自分事です。平均寿命が伸びれば、必然的に認知症の人も増えていきます。
認知症になったとしても、人としての尊厳を保ち続け、人として生きてゆける世の中作りが、認知症の社会的テーマといえるのではないでしょうか。
今、認知症の本人たちが自ら前面に立って発言することで、世の中の意識変革や国の認知症施策が進むきっかけになると期待されています。
マキロップ氏は講演の最後に、
「確かに認知症は大変な病気ですが、たとえ認知症になったとしても、新たにそれなりの幸せな生活を送ることはできるはずです。良い支援も必要ですが、認知症の皆さんの新しい人生は、皆さんが自らの手で作るものです。自分に自信を持って、必ずできるという信念を持って欲しい。皆さんの未来と、日本認知症ワーキンググループの成功を強く祈っております。」
と会場の参加者にエールを送りました。














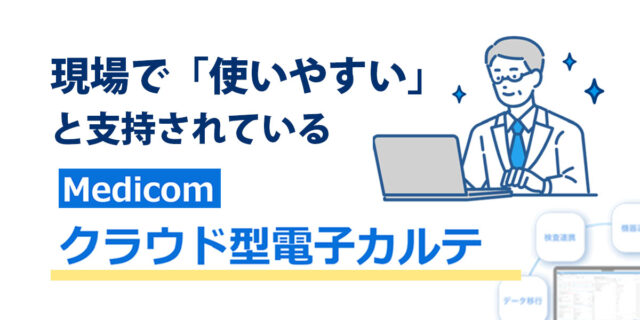























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)
