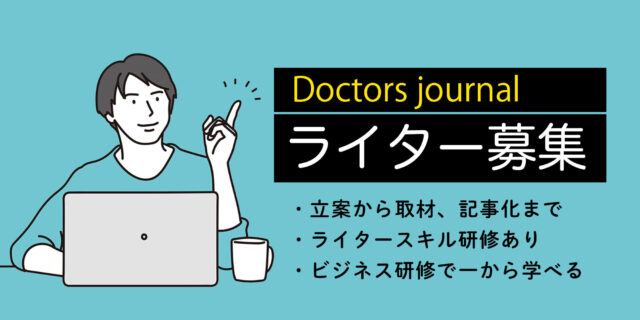#02 樋口直美氏「悲しみ、悔しさ、孤独、不安、絶望を、認知症の本人になって初めて知りました。」
連載:認知症を巡る問題の多くは、病気そのものが原因ではなく、人災のように感じています。
2020.08.05
私は幻視を精神症状ともBPSDとも思いません。
幻視は、本物にしか見えません。透けてもぼやけてもいませんから、消えない限り、本物との区別はつきません。私の場合は、意識も思考力も精神状態もまったく正常な時に不意に現れました。
誰でも目の前に不審者が現れたら、怖いし、驚いて叫びますよね。レビーでは思考力があって、本物にしか見えないものが見えるから、それに対して正常に反応しているのです。それを精神症状とかBPSDと呼ぶのは、適切でないと思います。
家族や周囲は、幻視に対する言動を狂人扱いします。BPSDと決めつけられて抗精神病薬を出されることもあります。幻視は、医師にも誤解されている症状だと思います。
幻視を狂人扱いされる悲しみ、悔しさ、孤独、不安、絶望を、認知症の本人になって初めて知りました。
希望を失うことで症状も悪化してしまいます。
私が何で苦しんだかと言うと、この病気を疑った最初の頃、医療者の情報は「認知症は悪化する一方。余命は10年以内。」という残酷なものしかなくて、そこにはひとかけらの希望もなかったことです。
若年認知症と診断されて、そのままうつ病になって引きこもり、認知症が相当進んでしまったという例が多いと聞いています。絶望の原因は医療情報です。病は気からと言いますが、ヴィクトール・フランクル著「夜と霧」の中に、希望を失ったとたんに死んでしまう人々の姿が描かれています。
たとえ癌であったとしても、気持ちの持ち方で予後は変わってくるでしょう。気持ちは想像以上に大切だと思います。
認知症になったら悪化する一方、BPSDを起こし、何もわからなくなると思っている医師が多いと感じますが、良いケアをしている家族はそうではないことを知っています。医師は診察室の中の姿しか見ていないから、認知症の真の姿を知らないと感じます。
社会の誤解と偏見も認知症の人を追い詰めています。
これから超高齢化社会になります。今は、認知症は最もなりたくないものと思われていますが、認知症と老化は重なっている部分が多く、誰しも高齢になれば認知機能は衰えていきます。高齢化社会では認知症はマイノリティーではなくマジョリティーという知人の言葉に同感します。
認知症になっても大丈夫な社会を作っていくことが大切なのだと思います。
認知症でも、銀行がATMでなくて窓口であったらお金は下せるでしょうし、駅も窓口であれば切符が買えます。昔の日本だったら困らなかったことに、今はたくさんの人が困っています。これは、認知症の問題ではなく社会の在り方の問題です。
本の中で、認知症を巡る多くの問題は人災だと書きました。アルツハイマー型認知症になっても、レビー小体型認知症になっても穏やかに生活していけるのに、それを「困った人」にしているのは、不適切な医療と限りなくアウェイな環境であると思います。
例えば晩年のカントは、認知症で重い記憶障害があっても、周囲からは偉大な哲学者として敬愛され続けたことで、BPSDも起こさず最期まで威厳を保っていたと本で読みました。
もし世の中の人が皆、認知症を正しく理解して人として普通に接することができて、医療も適切であれば、記憶障害などの障害があっても病気とともによりよく生きていくことは必ずできると思っています。
診断は画像頼りではなく問診を重視し柔軟性が欲しい。
問診でレム睡眠行動障害とか、うつや幻視とか幾つかの特徴的な症状が出ていたら、一度レビーを疑ってみて微量の抗認知症薬を処方して様子を見てみる。効果が出ればレビーの可能性が高いという判断を下す。と言うような柔軟な診療ができることを望みます。
私の場合、MRIやスペクト、心筋シンチという高額な画像診断を受けても、診断も治療もされませんでした。
本当に苦しくて助けてほしいから受診したのに治療を受けられなかったことは、命綱を切られた思いでした。
多くの医療者にこの病気を正しく知って頂きたいと切実に願っています。
この病気は初期には記憶障害が目立たないなど認知症らしくない特徴があるため、「診断が難しい」とどこにも書かれています。でも薬剤過敏性など他の病気にはない様々な特徴がありますから症状を正確に理解さえしていれば問診で見つけることは決して難しくないはずです。
小阪憲司先生は「この病気は認知症症状が出る前に早期発見早期治療をすることが何より重要。そうすれば認知症に進行することを予防できる可能性がある」と言われています。
この病気ほど医療がその後を左右するものはありません。適切な診断、治療で患者を救って頂きたいと切実に願っています。(※取材 2015年10月)