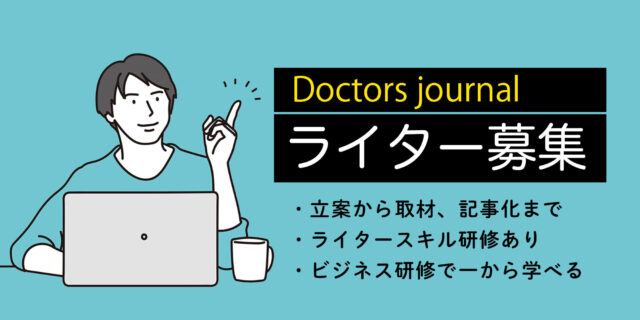#03 トム・キットウッドが提唱した17の悪性の社会心理
連載:「パーソンセンタードケア」と「地域における連携ケアの重要性」
2021.07.15
早期発見・早期絶望と早期発見・早期希望
勝又: 今は認知症を予防できない。認知症になったら一時的に薬で進行を遅らせることは出来たとしても治らない。治すことが無理な上に、本人の生活のしづらさが益々増してくるのであれば、生活をどう続けるのかを支援することが認知症医療における大切な要素ですね。
木之下: 「生活をどう続けるのか」という点において、ある認知症の人は「早期発見・早期絶望」と言っています。
医療の視点では、最初は早期発見、早期治療といい、いまは早期対応という言葉になりました。でも対応される対象と面と向かって言われると、恐らく誰でも傷つくでしょう。そこで私は早期発見、早期支援がいいなあ、と考えました。
ところがクリスティーン・ブライデン氏がある人に宛てた手紙に、「早期発見・早期希望」と書いています。私は、はっとしました。当事者である自分の視点で見たら、支援ではありません。希望ですね。絶望に対峙する言葉です。
だとすれば「本人の希望」をさがす旅に我々も出て、おつきあいすればよいのだと。クリスティーンはそこには沢山の宝物があるというのです。

元永: 認知症と生きる中の希望というのは大事な考え方ですね。病気を治療するのではなく、人の価値観とか考え方を軸に、人の暮らしを大事にしてゆくというケアのあり方がパーソンセンタードケアと言えます。
パーソンセンタードケアという考え方を提唱したイギリス人のトム・キットウッド氏は、認知症の人のケアのあり方を観察していて、よろしくない関わり方が非常に多くなされていたということを発見するわけです。
それを悪性の社会心理(MSP)として17の事象にまとめ、それが認知症の人の存在を脅かして、更に悪い状態に追い込んでゆくことを実証しました。
それに対して認知症の人にプラスとなる相互作用を、人を中心にした関わり方を整理して、ポジティブパーソンワーク(PPW)としました。そのような関わりがあれば、認知症になっても希望をもって生きてゆける。時には、周りの人が認知症の人から希望をもらうこともあると言っています。
ところで、このように考えることで、認知症の人に関わっている自分をより豊かにしていると思えるのでしょうか?また、認知症の人の生を豊かにしているのでしょうか?

木之下: 例えば、騙すとか、子ども扱いするとかという悪性の社会心理は、我々が小学校で習った道徳のテーマと同じで、誰でも言われればそれが悪いことである、とわかります。
しかし、敢えてこのようなことを言わなければならないのか、という問題と、勝又氏が取り組まれているコンセンサスメイキングの難しさとは、根を同じくしていると思います。
理由は、それが善意や、親切心で行われているから。悪いことと意識して行っている人はいない。だって、そんなこと分かれば誰もしないでしょう。
しかし、なぜか目の前で起こっている現実がそうであることに気づけないのです。行為が悪性の社会心理と解った瞬間に誰もがその行為を止めるでしょう。
しっかりとしたコンセプトがあればこの気づきが促され、気づきがあれば間違った行為は無くなるでしょう。そのコンセンサスを如何に創り上げてゆくのか。行政が先陣をきる姿に心うたれます。我々も、一緒に取り組んでゆくべきテーマだと思います。
今回の、人々に気づきを与えるような理念型の施策は、とても大切だと思います。
認知症の人は勿論、ケアする人も人である。
本多: 私は認知症の在宅ケアに十数年携わってきました。その関わりの中で、在宅医療の看護的な目を養うばかりに、認知症の当事者の方や周囲の人々の視点に気づけなかった時間も多くあったのではないかと感じるようになりました。
在宅診療に携わる中で接するようになった、ご本人、ご家族、地域の方々、他職種の方々が私に求めてくる内容が、いままでの医療のものとは別の内容に変わってきたのです。
医療面よりもむしろ、生活の中で困っている事柄に関係する相談が次第に増えていったのです。そのうち、それらの気づきと医療とケアを上手く繋げない限り、受診者のためにならないと考えるようになりました。
医師が医療だけにこだわり、看護師は看護師の仕事だけとか、各々が自分の職域にこだわっているようではだめで、各々がもっといろいろな目を持たなければならないと思います。
気づきを与え、医療とケアと福祉を近づけ繋げるためのものがパーソンセンタードケアの考え方だと思いますし、それを理解して実際の行動に反映させていくことが重要だと思います。

木之下: 認知症のテーマ性とは、限られた誰かが語るのではなく、全員が問題意識を持たざるを得ないのです。何故ならば、誰もが認知症になる可能性があるからです。
パーソンセンタードケアのパーソンとは、認知症の人のパーソンであり、これから認知症になるかもしれない私たちがパーソンでもあり、ケアする人もパーソンでもあるという、全ての人を指していると考えられます。
勝又: パーソンセンタードケアは認知症のケアの基本になり、その人中心のケアと言えますが、今の流れでその人中心のケアと考えると、認知症のケアだけでなくて全ての人に対する医療にも言えることですね。
糖尿病の人にも言えるでしょうし、病気で無い人にも、普通の人間関係にも言えますね。その中でも特に認知症には象徴的と言えるわけですね。
木之下: その通りだと思います。「パーソン」は「人」です。なので、パーソンセンタードケアを「その人中心のケア」と訳すのは間違いだと思っています。
「人中心のケア」がパーソンセンタードケアの直訳であろうと。
「その人」中心の視点は、まず前提とするべき大切なことです。しかし、それが行き過ぎ周囲の人を抑えつけるような、本人至上主義はおかしい。それでは周りは疲弊します。
イギリスの臨床のガイドラインでは、「Supporting people with dementia and their carers in health and social care.」と表紙に書かれています。
認知症の人はもちろん、ケアする人も人である。人を考える。人として関わっていく。我々も人として生きていく。そういうことをパーソンセンタードケアのコンセプトは与えてくれるのだと考えます。
認知症が切り拓く明日の日本の姿
元永: 最近の傾向で言えば、悪性の社会心理とは教育現場でのいじめのラインナップともいえますね。そこには一方的な関係性が存在し、それが人を傷つける結果を生んでいる。
但し、いじめは、悪い行い、または少なくとも後味の悪いことという認識がありますが、認知症医療やケアの現場では、専門家は良かれと思ってやっているのに、このようなことが起きてしまうという点に問題の深刻さがあります。
木之下: これからの認知症の現場では、関係者がそのような意識から脱却することが求められています。
コンセンサスを広く作り上げるためには、整備しなければならない事柄も多いですね。我々はどこに向かうのか、国としてどのような社会を目指してゆくのかを考えることはとても重要です。
今回、厚生労働省の発表の中で、認知症患者ではなく認知症の人、対策ではなく施策という言葉が使われていますが、これはとても大きな進歩だと思います。
何気なく使っている言葉であっても、その背景にある意識や思想を考えたときに、言葉の選択というのはとても重要です。言葉が変ると、考えや行為が変ってくる。
勝又: 現状を見るに、パーソンセンタードケアという考えは医師の中にはまだ十分に広まってはいない様に感じますが、その点はどうなのでしょう?
木之下: パーソンセンタードケアが記されたトム・キットウッド氏の著書は1996年に発表され、日本では2005年に翻訳されて発表されました。確かに現状はまだ十分に広まってはいないかもしれません。
私は、特にパーソンセンタードケアという言葉自体にこだわるつもりはありません。言葉よりも、考え方に重きを置きます。
語り方はいろいろあります。例えば認知症対策とか認知症患者という言葉を使ってゆくのか、本人の意思を尊重するとか、認知症の人と言うのかの違いで十分に伝わるものはあります。
2008年のランセットのパーソンセンタードケアについての論文の中で、パーソンとは平等な価値を有する人と定義されていますが、もっと単純にパーソンとは、あなたのことですよ。人ですよ。ということでも十分に伝わると思います。
認知症になっても希望を持って生きていける文化になっていくことを望みます。何故ならばそれは自分のためにでもあるからです。
本多: 在宅認知症ケア連絡会が隔月で行っている研究会では、パーソンセンタードケアとか、悪性の社会心理、ポジティブパーソンワークなどの言葉を投げかけることで、連絡会に参加者されている皆さんの、気づきのきっかけ作りになっているように感じます。
木之下先生は在宅認知症ケア連絡会で常に、認知症ケアの方向性を参加者の皆さんに一緒に考えてもらいたいというスタンスで取り組まれています。
その中でパーソンセンタードケアなどのテーマの投げかけが、私たちの実際のケアの現場でいろいろなことを気づかせてもらえる種になっています。
司会: とても多くの示唆を含んだお話を伺えたと思います。認知症ケアとは、まずその根底に「人は認知症になっても人としての尊厳は失われない。家族の一員、社会の一員、友人、そして国民の一人として、最後まで人生を全うする権利を持っている」ということを共有し、全ての人が当事者のテーマと捉え、認知症と共に歩み、生きていく社会をつくり上げてゆくことだと思います。