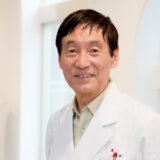#02 私たちのことを、私たち抜きに決めないで
連載:認知症とともに生きる私 ―「絶望」を「希望」に変えた20年
2020.10.26
私たち抜きに決めないで
『認知症とともに生きる私「絶望」を「希望」に変えた20年』を貫いている思いは、原著のタイトルである「Nothing About Us, Without Us!(私たちのことを、私たち抜きに決めないで)」(Jessica Kingsley, 2016)という言葉に集約されるといっても過言ではないだろう。
この考え方は、古くはハンガリーのニヒル・ノビ法(1505年)に由来し、もともとは、国王といえども議会上下両院の同意なくして法律を布告することはできないと定めた文言であったという。
それはやがて民主主義の規範のひとつとして後世に受け継がれ、時代がずっと下って1990年代になると、障害者運動を担うスローガンとして世界に波及した。
1995年、クリスティーンが認知症の診断を受けたのは、ちょうどそのような時期であった。
国際会議の舞台で
2004年、京都で開かれた国際アルツハイマー病協会(ADI)国際会議に、認知症の本人として参加した彼女は、このスローガンを表題とする発表をおこない、その後の世界の動きに多大な影響を与えた。
認知症の人自身が声をあげることで、他者にとって「目に入らない、目に見えない存在(透明人間)」から「目に見える存在」になり、認知症に対する偏見をみんなで一緒になって取り除いていくことができる、と訴えたのである。(第四章に全文を収録)。
クリスティーンをはじめとする当事者からのこのような働きかけによって、認知症に関係することには認知症の人自身が参加すべきである、という意識が広がっていった。
このスローガンは、国際認知症権利擁護・支援ネットワーク(DASNI)から国際認知症同盟(DAI)に引き継がれ、現在は国連と連携する認知症の人の権利擁護運動(アドボカシー)に発展している。
その成果のひとつとして、世界保健機関(WHO)では、今年から認知症に関するグローバル・アクション・プラン(十ヵ年計画)が始まった。

認知症の私はどう感じているか
2001年以来、折にふれてクリスティーンの言葉に接してきたが、今回再び彼女の言葉を翻訳するにあたって、あらためてその大切さについてしみじみと考えた単語があった。
それはfeel(感じる)である。本書を読むとおわかりいただけると思うが、彼女は講演をおこなうたびに、「私はどのように感じているか」「認知症があるのはどのような感じか」を説明している。
実際に日本に来たクリスティーンが講演で原稿を読み上げるときも、「アイ・フィール」と強調することがあった。
当たり前だと思われるかもしれないが、この言葉を使ってそう語ることができるのは、認知症がある人だけであり、そこにまぎれもない当事者性がある。
その明白な事実と、本書の随所に埋めこまれたこの言葉の重みを、私たちは忘れないようにしたい。(訳者あとがきを一部加筆)
訳者:馬籠久美子 まごめくみこ
通訳・翻訳者。1986年、津田塾大学英文科卒業。米国マサチューセッツ州のスミスカレッジでアメリカ研究プログラムを修了、同州立大学アムハースト校大学院で教育修士号取得、博士課程に学ぶ。
認知症関連の翻訳書に、クリスティーン・ブライデン著『私は私になっていく❘認知症とダンスを』(共訳、クリエイツかもがわ、2004年)、エリザベス・マッキンレー他著『認知症のスピリチュアルケア』(新興医学出版、2010年)、認知症当事者の会編『扉を開く人―クリスティーン・ブライデン』(クリエイツかもがわ、2012年)。2003-2004年の来日講演などの通訳を務め、クリスティーン・ブライデンを取り上げた番組制作に携わる。