#05 本人だけでなく周囲の人も納得のいくターミナル・ケア
連載:住民参加型の地域包括ケアを志向し、 コーディネーターとして住みやすい街づくりに尽力する
2019.08.30
ターミナル・ケア(死生観)の恩師 キューブラー・ロス博士との出会い
平成2年のアメリカのホスピスツアーでは、ターミナル・ケアの先駆者であり、世界で最初に命を看取るケアを訴えたエリザベス・キューブラー・ロス博士にお会いする機会を得ました。ご自宅の牧場を訪問した時に、博士は手作りのケーキでもてなしてくれました。
そこで受けたターミナル・ケアのレクチャーの中で、博士はご自分が作られた「蝶のさなぎ」のぬいぐるみを取り出し、腹部のファスナーを開けてその中から蝶を取り出されました。
「さなぎは人間の肉体です。そこから出てきた蝶は魂です。死ぬということは、肉体というさなぎを脱ぎ捨てて精神が自由になるということです。肉体は滅びても魂は永遠に生きて、飛び立っていきます」と話され、私は、「肉体は死んでも魂は生きる」という、ターミナル・ケアの死生観を学びました。この経験は、私のその後の人生に大きな影響を与えました。
『ダギーへの手紙』
訪問時に、博士の数ある著書の中から『ダギーへの手紙』という小冊子が目に留まり、その場で原書を2冊購入しました。
本書では、9歳で余命3ヶ月と診断された小児がんのダギー君が、博士に手紙で、「いのちって、何?」「死って、何?」「どうして、小さな子供たちが死ななければならないの?」と3つの質問をしています。それに対して博士は、「この世でやらなければいけない役割が全部終わったら、人生という学校を卒業し、体に閉じ込められていた魂が解放されて痛みもなくなり、悲しいこともなく、自由になるの。それが「死」なのよ。そして愛する人達とまた会えるの。ダギー君は一人ぼっちではないのよ。」と、美しい手書きのイラストを添えて愛情をこめて優しく答えています。ワシントンへ帰るバスの中で夢中になって読みました。涙が止まりませんでした。手紙をもらったダギー君はその後4年も生きたそうです。
研修医として国立小児病院に勤務していた当時、まだ25歳という若さで自分の中に確たる死生観も確立できていなかった私は、子どもたちからダギー君と同じような問いかけを感じながらも、彼らに精神的なケアができなかったという辛い思い出があります。
子供といえども、死に直面して真剣に苦しんだり悩んだりしています。
ターミナル・ケアでは、大人も子供も関係なく、患者が死の直前に伝えたい貴重なメッセージにしっかりと耳を傾けなければなりません。最後まで愛情をこめて真摯に寄り添うことの大切さを知りました。
本人だけでなく周囲の人も含めた納得のいくターミナル・ケア
看取りでは、残された家族には必ず大なり小なりの後悔はあるのですが、それでもあえて言えば、笑顔で看取りができるということが一番だと思います。
それは、周りの人も含めた納得のいく看取り、自分も出来る限りやったと納得できる看取りということです。
私の在宅の患者さんで、心不全のお母さんがおられました。三人の娘さんが交代で介護をされていたのですが、ある日亡くなられたと連絡を受けてご自宅に伺ったところ、娘さんが「先生、記念写真を撮りましょう」というのです。
三人の娘さんと私と訪問看護師が、亡くなられたお母さんを真ん中に写真を撮りました。みんなでピースサインです。そんな経験は初めてでした。
娘さんたちは、最後まで納得のいく介護ができたのだと思います。お母さんも安心して旅立って行けたのだと思います。残された家族にとってその満足感や経験はとても大事なことだと思います。
ターミナル・ケアの最後はグリーフワーク
私がグリーフワークを大事にしている理由は、ターミナル・ケアの最後はグリーフワークが決め手になると思っているからです。
親しい人の死別を経験した人のその後の人生に寄り添えるのは、かかりつけ医です。
かかりつけ医として、亡くなられたご本人の生き方や考え方は全部分かっているから、残されたご家族に伝えられることもあるのです。時には、子供達には言えないことも、かかりつけ医の私には話せるということもあります。
大切な人を失った後の悲しみやショックから乗り越えてゆく過程を精神的にサポートしていくことも、かかりつけ医の大切な役割だと思っています。











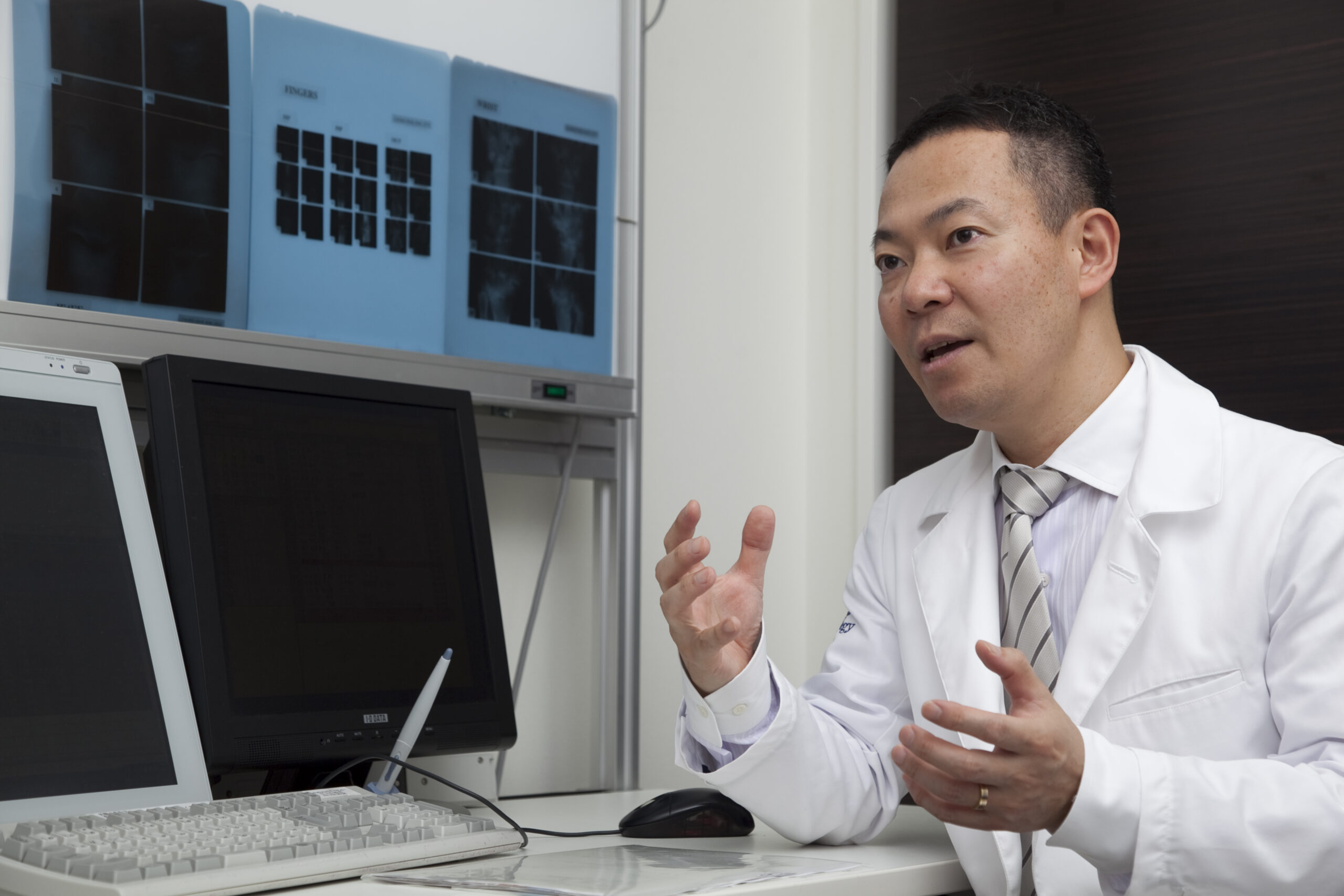






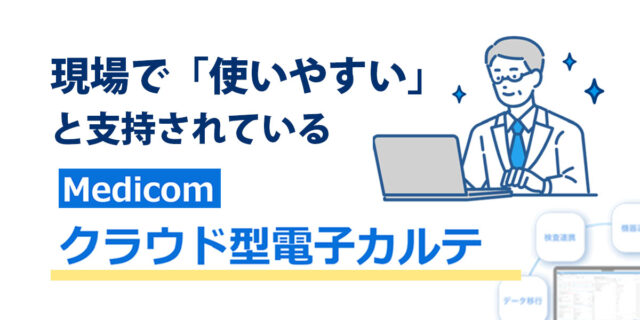























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター