#05 ホスピスケアが目指すべき姿とは、患者の人権擁護をまず基礎に置くこと
連載:ホスピスケアをムーブメントと捉え、 患者の権利が基本の在宅ホスピスケアに取り組む
2021.03.05
ホスピスと緩和ケア
ホスピスは、必ずしも末期がん患者を対象として生まれたものではなく、貧困、差別、孤独の中で死にゆく人に寄り添うものでした。これがホスピスの源流です。
がん患者を対象として見るようになったのは、20世紀中ごろになってからで、それに最初に気付いたのがシシリー・ソンダースでした。このような歴史を踏まえた中にホスピスはあります。
一方、緩和ケアの歴史は、20世紀後半になってできた概念で、病院内での一つの技術として生まれました。歴史が全く違います。最近の緩和ケアは技術に偏重してきてしまって、ホスピスケアの根本にあった人権という観点を置き忘れてきてしまっているように感じます。
いろいろな医学の領域があり、そこで業績を上げてその道で名声を上げたいという意欲を多くの医師は持っていますが、緩和ケアもその一分野になってきてしまっています。
いろいろな薬を使って、いろいろな症例を集めて云々という、そういうものになってきてしまった気がします。ですから私は、ホスピスという言葉にこだわりたいのです。
ホスピスと在宅ホスピスの違い
病院システムにおけるホスピスは医師が主体です。在宅ホスピスは、患者さんの暮らしが主体です。
日常生活ではいろいろなことが起きます。良いことも時には悪いこともあり、笑うこともあれば怒ることもあります。それが人の暮らしです。
完備された緩和ケア病棟の日常には変化がありません。優しい看護師はいるかもしれないけれど、そこに暮らしはありません。
人はどんな状態でも住み慣れたところにいるのが一番良いのです。「生きる」とは息をしているだけではなく「暮らす」ということなのです。
患者さんは家では闘病だけをしているのではありません。好きな時に好きなものを食べ、ふろに入り、家事をしたり、家族と喧嘩したり笑いあったり、近所の家にお茶を飲みに行ったりと、たとえ動けなくなっても、それなりにいろいろと考えたりしたりすることはあります。
ただ死ぬのを待っているだけということではありません。
ホスピスの理念から今の問題を考える
ホスピスの理念から今の問題を考えると、
- がん以外の緩和ケアに取り組まなければならない。
- 緩和ケア病棟に入れない認知症や精神疾患の患者の問題。
- PCUに入る経済的な余裕のない人の問題。
- 介護施設にいる人の在宅緩和ケアをどうするのか。
- ホスピスケアの主役とは誰か。
などの課題が山積しています。
ホスピスケアの主役は医師ではなく、看護師です。その看護師とは「天使とは、美しい花をまき散らす者でなく、苦悩する者のために戦う者である。」とフローレンス・ナイチンゲールは訴えています。
不適切な医療に対しては、医療者は戦わなければならない、というのが私のホスピス観です。

ホスピスケアとはムーブメントです。
私が考える今後のホスピスケアが目指すべき姿とは、患者の人権擁護をまず基礎に置かなければならないということです。そして今増えている「がん」と「認知症」の人、あるいは「がんで認知症」の人を排除しないということ。
現状では認知症の人は緩和ケア病棟に入れないことが多い。一般病棟も嫌がります。がん患者を福祉施設は嫌がります。結果としてその人たちの行き場がありません。
さらには、「孤独」「貧困」「被災」などの困難の中で、死に向かっている人に対応することと、「体と心とくらしを支える」地域のチームケアとして活動することです。ホスピスケアとは生々しいものです。社会運動で、ムーブメントです。
これが私のこれからのホスピスケアの考え方です。残念ながら、技術に偏重している今の緩和ケアには、その要素が失われてきていると感じています。
古民家を改築したミニホスピス・和が家
1999年に、養蚕農家の大きな木造2階建ての1軒屋を借りあげ、自宅でなくても在宅ホスピスケアを受けられるミニホスピス「和が家」を立ち上げました。
「和が家」の特徴は、医療が主体の場ではなく、暮らしを優先とする場であること。がん末期だけでなく、いろいろな病状の人が暮らしている場。療養者自身の生活のリズムを尊重した日々の運営が行われていること。場所自体が癒しの力を持っている。というものでした。
この「和が家」が持つ、生活とともに大切に使い込まれた家だけがもつ独特の空気のようなものを、私も入居者の人も大変気に入っていました。
残念ながら、東日本大震災で大きな損傷を受けたため、その後移転して、新たに立て替えて現在は、特定非営利活動法人在宅福祉『かんわケア大地』として活動しています。
地域全体をホスピスにしたい
2008年3月に設立した、私が代表を務める高崎地域緩和ケアネットワークがあります。これは、がんに限らず「住み慣れた場所で最後まで過ごせること」を支援する多職種協働の地域ネットワークです。
高崎市を中心に必要とされる地域を対象地域とし、地域の開業医へのアプローチ、患者・家族への療養に関する情報提供、医療者への地域緩和ケア連携の情報提供を目的としています。
現在は10以上の多職種が参加していて相当な広がりを見せており、高崎では、どんな方でも家で最後まで暮らしたいと願えば、多職種が共同してケアする体制ができています。
私はこの地域ネットワークをもっと広げていき、地域全体をホスピスにしたいと思っています。それが、人が安心して暮らせるための社会インフラの最たるものでもあると考えているからです。
もし東京直下型地震が起きた時には、大勢の被災者が群馬県に来るはずで、最初に受け入れるのは高崎になります。
その時に、被災者を受け入れられるのは、この高崎地域緩和ケアネットワークです。震災の時には、我々が緊急発動できるようにしていよう。と常々言っています。








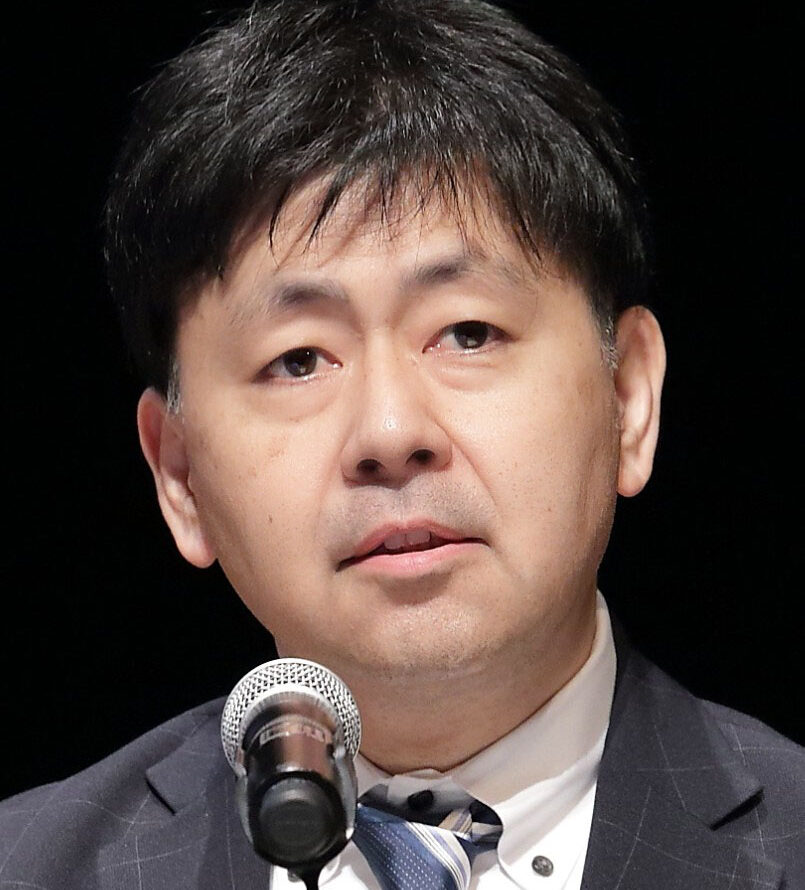







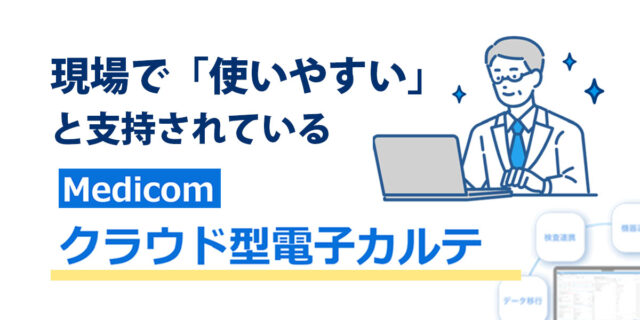






















![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)



![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)