#01 在宅医療こそが、私がイメージしていた医師の姿だと強く思いました
連載:あえて治療をしないという選択ができることも、在宅医の条件だと思います。
2021.01.06

高橋壮芳
三鷹あゆみクリニック院長。東京都出身。2002年名古屋大学医学部卒業。2011年三鷹あゆみクリニック開業。 在宅療養支援診療所として24時間連絡が取れ、適宜対応が可能な体制で、膝が痛くて通院できない、麻痺があり歩行困難で通院ができない、認知症で定期的な通院や体調管理ができないなどの患者さんから、癌の末期、在宅酸素、中心静脈栄養など様々な在宅医療のニーズに応えている。心理的に垣根が低く気軽に病気のことを相談できる窓口となり、患者や家族の希望を聞きながら、患者一人一人に適したオーダーメイドの医療を提供することを心掛けている。
医学部で感じた大学病院に対する違和感
私は東京都三鷹市の出身です。当初は、医師を目指していたわけではなく、文系への進学を目指していました。ただ尊厳死や脳死というものに興味があり、当時、山崎 章郎氏の著書「病院で死ぬということ」や柳田邦夫氏の「犠牲(サクリファイス)わが息子・脳死の11日」などを読んでおりました。
高校生の時に同居していた祖父の寝たきりの介護を手伝っていました。それなりに元気だった祖父が徐々に足腰が弱くなり、その後寝たきりで臨終に至るまでの姿を身近に見ていて、家族でありながらも何もできないというもどかしさを痛感し、医者ならばその思いをしなくてもよいのではないかとの思いが私を医学部に進ませました。
今思えば、私が現在在宅医療に関わっている原点は祖父の在宅ケアの体験にあるのかもしれません。
高校までは地元で、大学は名古屋大学医学部へと進みました。実家は医師の家系ではありませんでしたから、それまでの私にとって医師といえば、いわゆる町のお医者さん、あるいは片田舎で一人奮闘するというイメージでした。
医学部に入って、まず最初に感じたのは、患者さんの見えない医学部の授業であったり、大学病院という雰囲気に対する違和感でした。それは在学中もずっと続いていました。
さらには大学医学部のヒエラルキーにも馴染めませんでした。このままでは自分のイメージする医者にはなれないと、ずっと感じていました。
私は、目の前にいる患者さんに対して何ができるのか、そこにこそ医師としての存在意義があると思っていました。さらには漠然とではあったものの、入学当初から無医村に行きたいという思いを抱いていました。
研修医期間は無医村に行くための準備期間
先々は無医村での診療に携わることを志していた私は、幅広い経験を積もうと思っていましたので、大学病院などでの専門の診療科目よりは、今でいうところの総合内科のような方向に興味がありました。ですから、最初から研修先はその視点で教育をしてくれる病院にしようと決めていました。
北海道から九州、沖縄まで全国をいろいろと探した結果、東京都北区の中規模総合病院を研修先として決めました。その病院では地域に根差した患者さん本位の医療に取り組んでいたからです。名古屋大学医学部の同期の仲間から見ると特異だったと思います。
研修医時代はいろいろなことを経験させてもらいました。整形外科の患者さんから、脳こうそく、糖尿病の患者さん、教育入院の患者さんまで広く一通りの疾患を診ることができました。
また、入院患者さんだけでなく外来患者さんの診療も行いました。当時研修医で外来患者さんを診ることは非常に珍しかったと思います。そこには約7年間勤務しました。
専門科を特には持っていませんが、コモンディジーズは一通り診たことがあるので、その経験が今の私にとっては非常に役立っています。
元々は外科志望であったことと、無医村では外科治療の経験も必要であると思い、その病院で3年ほど外科の治療にも携わらせて頂きました。
そこの外科はドクター同士のチームワークが良く、今でも楽しかった思い出として残っています。
例えば小さなキズの縫合から、現在の全身状態から見た手術の危険性や、術後の廃用の可能性とかも念頭においた上で治療方針を検討できるようになったことなど、その時の外科医としての経験が今の在宅診療に非常に役立っています。
ちなみに、同じ法人内にある新百合ヶ丘あゆみクリニックの院長は研修医先での同期で、当時からいつか一緒に診療所をしたいと話し合っていた仲間です。

紆余曲折して在宅医療にたどり着く
研修医当時の私は、在宅医療には全く興味を持っていませんでした。地方の無医村に行くことを視野に入れていたので、研修先の病院で7年間経験を積んだ後に、いよいよ無医村に行こうと考えました。
しかし実は私は東京出身なのでいわゆる地方の故郷というものがありません。どこに行くとしても全く縁もゆかりもない土地ばかりです。しかも一度そこに赴任したらその後は簡単に辞めるわけにもいきませんから、いい加減な気持ちで赴任するわけにはいきません。
自分の故郷が無医村ということであれば思いも格別でしょうが、東京生まれの私にとっては、それだけの情熱と責任感を持って診療に臨める場所がはたして見つかるのか、探せるのかということが課題でした。
そんな折、学生時代から自転車旅行で旅していた北海道なら多少の縁もあるので、まずは一旦、札幌以外の道内地方病院に勤務し、その後に赴任先の無医村を探そうと考えました。
旭川、帯広、釧路、苫小牧などで病院を探し、ある病院で内定も受けていたのですが、妻の出産と赴任の時期が重なったために、結局はしばらくの期間は東京での勤務医を続けることとなりました。
今までと同じことをしても意味がないので、いずれは役に立つであろうと考えて、これまで経験したことのない在宅医療の世界に飛び込んだわけです。しかし当時は在宅医療についてはほとんど知りませんでした。
在宅専門クリニックで在宅医療を経験する。
中野区の在宅診療専門のクリニックに2年間勤務しました。そこは施設系の在宅診療は行っておらず、個人宅の訪問診療のみで、在宅で点滴も輸血も、人工呼吸器管理も行っているようなクリニックでした。
実はそれまでの私の在宅医にたいしてのイメージは、あまりポジティブなものではありませんでした。
病院の勤務医時代に夜間救急で搬送されてくる患者さんの中には、日常は地域の在宅医に掛かっていてもいざという時には病院に運ばれてくる方が多かった。「いざとなったら病院に行ってください」という、在宅医の患者さんへの関与はその程度に思っていました。
しかしそのクリニックでは全く違っていました。それまでの在宅医に対するイメージは完璧に覆させられました。
そこでは医師は患者さんや家族と相談して最良の方向を決め、一緒になって治療に取り組みます。そのクリニックでの2年間は自分を成長させるには最も良い環境で、在宅医療について非常に多くのことを学べました。
在宅医療に従事してみて、これこそ私がイメージしていた医師の姿だと強く思ったのです。それは医学部を目指した時から抱いていた医師のイメージに非常に近いものであり、医師としての満足感や充実感も非常に高いものでした。









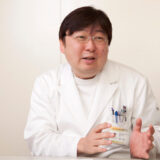


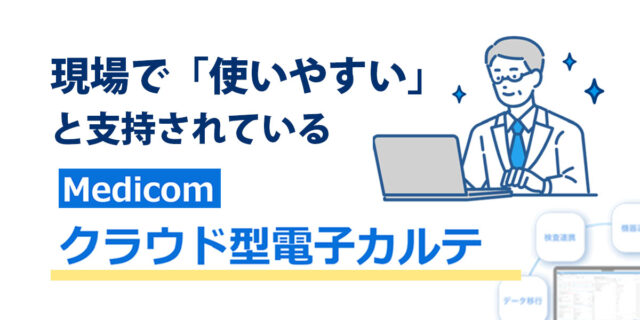


























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター