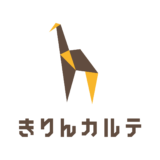#02 在宅医療では、病院の在宅医療に対する理解と連携が絶対に必要です
連載:あえて治療をしないという選択ができることも、在宅医の条件だと思います。
2021.01.08
在宅医療の取り組みで感じる魅力と課題
患者さんにとって在宅医療では治療の選択肢も多く、また制限も少ないので、そこは医師にとっても非常に魅力的です。
医療行為は、医療従事者か本人とその家族には許されています。極論を言えば在宅では手術もできるし、逆に何も施さないという、通常、病院では許されないことも可能です。
在宅医療ではありとあらゆる選択肢の中で患者さんが最も納得できる方向を選択できるのです。
私は医療とは、医者と患者さんという関係ではなくて、人と人との関係の中で一緒に取り組む共同作業だと思っています。患者さんが納得し満足してもらうこと、それこそが患者さんやご家族にとって最も大切だと思うのです。
これは在宅医療の世界に入って強く感じていることです。同時にそれに対応できる医療提供者になりたいと思います。
病院医師の多くは在宅医療の知識が少ない
また病院の医師の多くは在宅医療についての知識が少ない。かつての私もそうでした。病院から退院する時に、患者さんを家に帰すという選択がなされることが非常に少ない。
我々から見れば、この患者さんであればどう考えても家に帰すことができ、転院や施設ではご本人や家族もかわいそうだ。と思えるケースも少なくありません。
しかし、在宅医療でもある程度までの医療行為ができることを知らないために、「酸素をしているならば家には帰れない。」「点滴するならば家には帰れない。」「一人暮らしならば家には帰れない。」となって転院や施設入所ということになってしまうことが多くある。
病院にとっても転院先を探すことは容易ではないから、結局入院期間も長くなる。新たな患者さんも受け入れられない。という負のサイクルに入っている側面もあるのではないでしょうか。
実際の在宅医療ではいろいろな対応や受け入れができ、もっと広い世界であることがもっと理解されれば、医療は今よりはうまく回ると思います。医療行政もそれを目指しているのではないかと思います。

最終段階で在宅医療を依頼されるケース
末期がんの患者さんが、具合が悪くなった最終段階で我々に紹介されるケースがあります。そのような場合、患者さんとの信頼関係を作る時間的な余裕もないままに患者さんが急変し、我々としても十分な治療や対応ができないことがあります。結局病院に戻ってしまうことになったりします。
がんが宣告された時点で我々に紹介が頂ければ信頼関係を作る余裕もあり、患者さんやご家族にとって納得のできる在宅診療が開始でき、看取りも安心して自宅で迎えられるのではないかと思います。そのためには病院の在宅医療に対する理解と連携が必要です。私はそれを地域において何とか構築したいと思っています。
一方、我々在宅医側の課題もあります。在宅療養支援診療所として24時間対応をきちんとしなかったり、安易に救急要請をしたりと在宅医側の意識にも浅深があります。
団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年問題や、地域包括ケアへの取り組みが進もうとしている時に、在宅医療の受け入れ体制が十分整っていません。
全体的に医師不足といわれている状況下で、24時間365日という負担などもあり在宅に関わる医師はさらに少ない。特に受け入れのキャパシティの問題は今後深刻となると思います。
患者さんのわがままは信頼関係の証
医師にとって病院はホームグラウンドですが、在宅は患者さんのホームグラウンドなので、そこでは医師はいわばアウェイです。そこに抵抗を感じる医師もいるのではないでしょうか。
とにかく在宅診療では、患者さんはわがままを結構言います。病院の中ではまずそのようなことはないでしょう。
しかし私は、患者さんのわがままは信頼関係の証だと思っていますので、わがままは言ってもらったほうが良いと思っています。ましてや、在宅の患者さんの多くは高齢者で、私たち若輩は人生の先輩として敬うことを心掛けるべきだと思っています。
ですから当院では全医療スタッフに対して、患者さんとご家族に礼を失するような態度は厳しく戒めています。