#01【越川貴史氏】医学教育では教わらなかった現場の実態にショックを受け緩和医療に進む
連載:がん難民をなくすために、緩和ケアに専門特化した自院完結型の連携医療に取り組む
2021.06.10
衝撃的ながん医療の現場を目の当たりにする
― 末期がん患者の緩和医療に特化した専門病院は全国でもまだ少ないと思われます。越川先生のご経歴と、緩和ケアに取り組まれるようになった経緯をお聞かせください。―
越川病院は、私の父が1958年に東京都杉並区に産婦人科・越川医院として開設し、1975年に現在の地に越川病院として移転してきました。
その後2001年に私が引き継ぐ時に、現在の緩和ケアに特化した専門病院 医療法人社団杏順会 越川病院となりました。
当初は後継者として産科を継ぐという道もあったのですが、私としては医学生の頃から全身管理を行う診療科に進みたいという考えがありましたので、産科ではなく内科医を志しました。
さらには医師になった暁には、できれば人の生死に関わるような医療の仕事がしたい、やがては高齢化社会を迎える地域医療に貢献したい、という思いもありました。
大学病院での消化器内科の研修医時代に、衝撃的ながん医療の現場を目の当たりにしたことが、私の将来を決定づけました。
消化器内科には、がんを患っている患者さんが非常に多くいます。その患者さんが手術後、抗がん剤治療を受けていても、大学病院では最後まで看る仕組みになっていません。多くの末期がんの患者さんが転院を余儀なくされているわけです。
医学教育では教わらなかった医療現場の実態に大きなショックを受けました。私にはそのことが理解できませんでした。ではこのがんの患者さんはこの後どこに行ったらよいのか?
当時ではホスピスに行く患者さんはほとんどなく、系列の病院に行くことが多かったのですが、そこで緩和医療としての専門性を活かせた治療がなされているかというと、現実には必ずしもそうではありませんでした。
そうであるならば、いずれ戻ることになる家業の越川病院で、地域の末期がん患者さんのために専門性の高い取組みができないだろうか。
そのような動機から、私が帰ってきて院長となった2001年、それまで産科であった越川病院の診療科を変更して「がん難民をなくし、末期患者さんのための緩和ケアと在宅支援」に取り組む専門病院にしたいと考えました。
そのためにがん末期患者さんの緩和ケア治療体制づくりとして、人員や設備の拡充に着手し、看護力のレベルアップと7対1看護体制を目指して2002年にはほぼ完全に産科から緩和ケア専門に診療科の転換を果たしました。
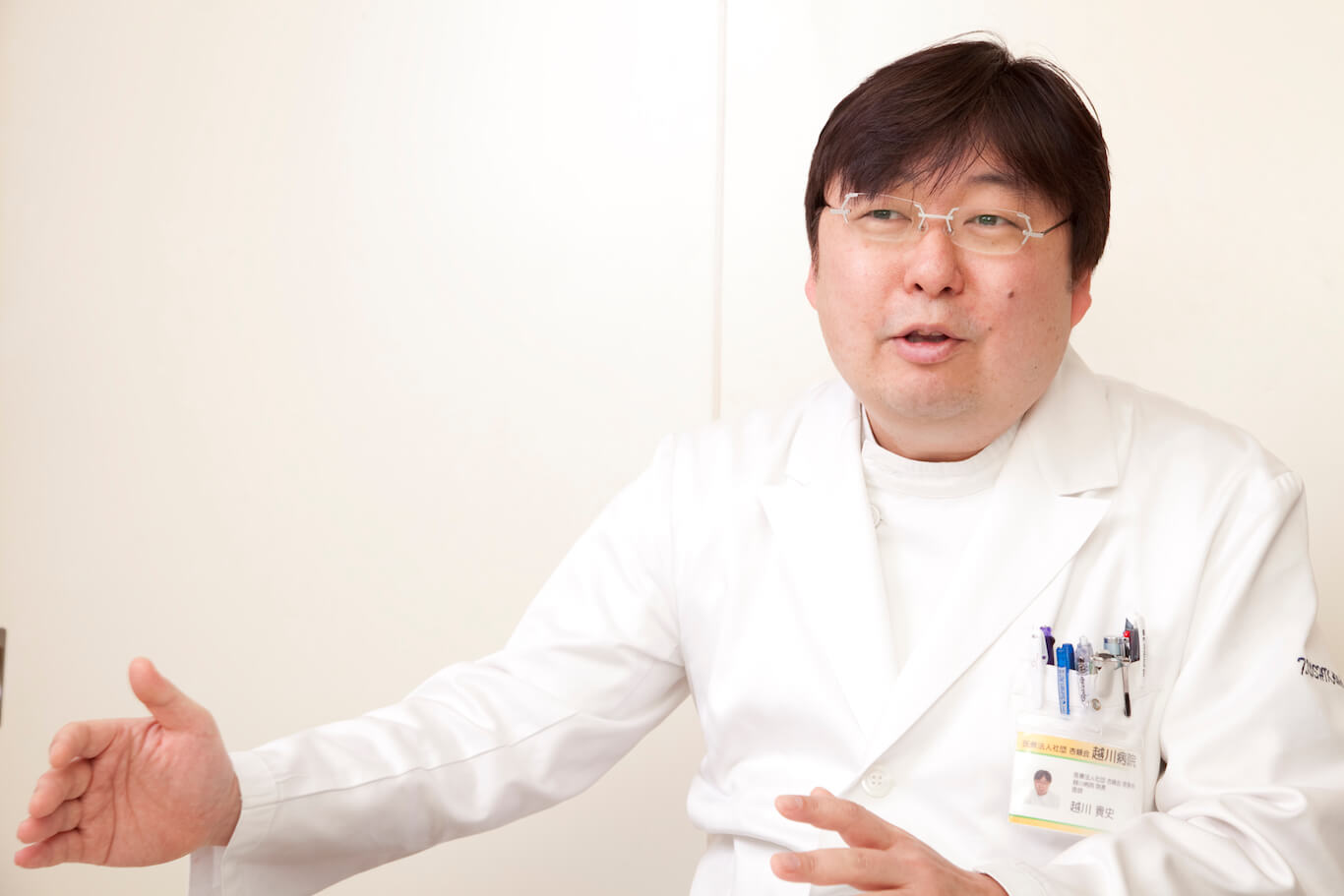
医療法人社団杏順会越川病院理事長・院長。
一般内科・消化器科 1995年日本大学医学部卒業、日本大学第三内科入局。2001年医療法人社団 杏順会 越川病院開設し院長に就任。2003年から国立がんセンター中央病院緩和ケア科研修生(5年間)。
日本緩和医療学会指導医認定、日本緩和医療学会認定医、東京慈恵会医科大学緩和ケア診療部非常勤診療医長
自己完結型の医療連携にたどり着く
私が緩和ケアに取り組みはじめた10数年前と比較すると、今日では在院日数はますます減らされています。
在院日数は大きな課題です。在院日数を守り良い医療を行うためには、看護体制を上げることが一番で、今の7:1看護体制を維持し在院日数を無理なくクリアするためには、在宅支援が最も有効と考えました。
自分たちで訪問診療、そして訪問看護も行い 一人の患者さんを最後まで診れるようにしようと考えたわけです。患者さんは、必要に応じて一時入院し、帰れるようになったらまた在宅に戻れば良いのです。患者さんの一番の不安は、退院したら行き場がないということですから、それをこの病院で行おうと考えたわけです。
最近は医療連携がクローズアップされています。当病院でも10数年前から医療連携に関してはいろいろな取り組みやマネジメントを行ってきましが、最終的には訪問医療にしても訪問看護にしても、自分たちで全部できれば、それが究極の医療連携なのではないか。という結論に達しました。
2005年には訪問看護ステーションをつくり、翌2006年には訪問診療クリニック、さらには居宅介護支援事業所も立ち上げて、一つの医療法人内で医療連携の体制を実現させました。
越川病院では全員が緩和医療に従事している
病院がバックにあって訪問診療や訪問看護を行うことは、在宅医療に携わるすべてのスタッフにとっての負担軽減にもつながっていると思います。
現実には24時間、365日一人の医師が在宅に関わることは困難です。診療所の集合体で行うのも難しい場合があります。
当病院の場合、内科と外科の医師が常勤しています。全医師が緩和医療に取り組みたいということで入職しており、実際に全員が緩和医療に従事しています。
大学病院などから紹介された重い症状の患者さんの在宅支援においては、診療所の医師だけで看るということが難しいケースもあります。そういう場合は高い専門性を持った医療集団がマネジメントしたほうが良いと思います。
特に緩和医療は高い専門性が問われる分野なのです。現在では(当病院がこの分野の指導的な立場になっていて)私自身も医師会や講演会などで当病院の取り組みについて話をする機会も多く、その都度、在宅支援の連携を訴えています。
緩和ケアで重要なのは緊急性です
都内の緩和ケア病棟の状況では、まず最初の面談までに1ヶ月くらいかかります。さらにその後入棟できるまでに1〜2ヶ月かかります。
つまりがん治療で最後の抗がん剤治療を受けている最中からホスピス探しを始めなければならないということなのです。
一般的には今の緩和ケア病棟は看取りの場という認識ですから、患者さんからしてみれば、「治療しているのに、何で看取りの場を探さなければならないのだ」という矛盾と絶望を感じるでしょう。
緩和ケア病棟のなかにはでは入棟までに6か月もかかるところもあり、それではほとんどの人が存命中に入所できません。
当病院の場合、患者さん本人とご家族との面談の上、受け入れを決めたら約1週間で入院していただけます。私と病棟全体の状況を把握している看護師長とで直接判断し、諸々の調整に時間をかけないようにしており、救急を要する場合には即日入院も可能です。
つまり、緩和ケアでは重要なのは緊急性なのです。
今回の診療改定でも、がん診療拠点病院では緩和ケアの緊急体制の対応を求められていますが現実には困難なことが多いかもしれません。むしろ私どものような規模の病院がそれを担うような改正と捉えています。しかし課題は、緩和ケアの専門医が少ないことです。
今や日本人の2人に1人ががんになり、全死亡者の1/3(約36万人)ががんで亡くなっています。つまりそれだけの人が緩和医療を必要とするといっても過言でない状況にもかかわらず、専門医が足りないのです。
何故かといえば、重篤で亡くなる患者さんも多いですから、看取るために医者になったわけではないという思いが、緩和ケアに進む医師を少なくさせているのだと思います。まだまだネガティブな捉え方をされていますね。
「帰るホスピス」とは
私自身は、看取るために医師になったつもりはありませんし、患者さんにも「お看取りするためだけに入院するのではありません」と説明します。今の流れは、緩和ケア病棟でも患者さんを在宅に帰す方向に進んでいます。しかし、まだ多くの緩和ケア病棟はそうなってはいません。
私としては、看取る方もいれば在宅に帰す方もいる、つまり「帰るホスピス」、そんな緩和ケアを実現させて今ある現状をブレークスルーさせたい、と考えています。
海外と日本では緩和ケア病棟、ホスピスのあり方に違いがあります。海外では両者は分かれていて緩和ケア病棟(PCU)には急性期を症状マネジメントする専門医がいるのに対して、ホスピスでは「家庭医」が看ます。
一方、日本の緩和ケア病棟はというと、ケアミックスになってしまっていて「急性期の症状マネジメント」も「看取り」も区別なく混然としています。
在院日数のしばりはない、しかし在院日数に関していえば2年前の診療報酬改正は、入院日数が長くなると診療報酬が減額になるため、緩和ケア病棟も「患者さんをできるだけ在宅に返すように」という国のメッセージだったのです。
しかし、この2年間、患者さんを在宅に返すことはあまり進んでいません。もし『帰るホスピス』が現実となると、患者さんとその家族からすれば「何で返すのだ」という反発もあるでしょう。その大きな要因は、ホスピスは受け入れる際の連携はあっても、患者さんを退院させた後の連携ができていないからです。
これからは、症状マネジメントをきちんとして家に返してあげた上で、在宅医療、在宅看護を私たちのような緩和ケアの専門集団が厚くサポートする、そして緊急時には再入院もできる、そのような『帰るホスピス』へと変わらざるを得なくなっていくでしょう。
こうした体制をどの地域でもできるだけ早く確立しなければならないと感じます。

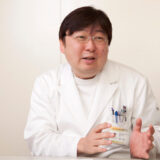

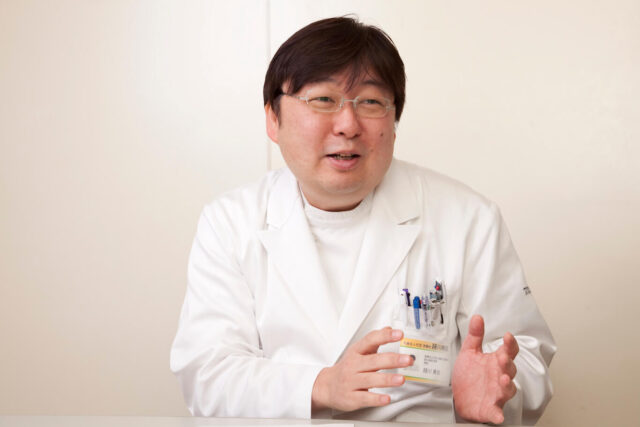






























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)



![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)


森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター