#02 光免疫療法の課題や応用可能性、実臨床からの知見について
連載:“その人らしく” 生きるためにーー光免疫療法という選択肢
2025.03.15
最新のがん治療である「光免疫療法」について、国立がん研究センター東病院の篠﨑剛先生が語る本連載。2記事目となる本記事は、光免疫療法の課題や応用可能性、実際の臨床現場からの知見についてです。
今回取り上げるのは、楽天メディカルが開発した薬剤「アキャルックス」と「BioBladeレーザシステム」による「頭頸部アルミノックス治療」です。頭頸部アルミノックス治療は臨床試験によってその効果が証明され、現在は保険診療として受けることができます。
なお、民間治療として行われている光免疫療法に関する内容ではないためご注意ください。
アルミノックス治療の概要(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会のWEBサイトより)
https://www.jibika.or.jp/owned/toukeibu/topics/alluminox.html
光免疫療法の課題
光免疫療法にはいくつかの課題も見られます。
- 痛み・腫れなどの副作用
- 腫瘍が頸動脈に浸潤していると治療が選択できない
痛み・腫れなどの副作用
光免疫療法では、レーザー光を当てた当日や翌日に痛みを感じる患者さんが多くいらっしゃいます。この痛みは数日以内に引くことがほとんどです。また、患者さんによってはレーザー光を当てた部分が腫れてしまうことがあります。中には、喉がかなり腫れてしまい窒息につながる恐れがあったため、気管切開によって対処したという症例もありました。
腫瘍が頸動脈に浸潤していると治療が選択できない
頸動脈に浸潤した腫瘍に対して光免疫療法を使用すると、血管が破裂することで死に至ることがあります。ですので、頸動脈に腫瘍が浸潤している場合は、光免疫療法を行うことができません。
[コラム3] 光線過敏症
ーー「光線過敏症」について教えていただけますか。
篠﨑:はい。光免疫療法では、レーザー光に反応する薬を投与する関係上、手術後に光を強く浴びることが発赤(※1)などの副作用につながることがあります。これを「光線過敏症」といい、光免疫療法の副作用として良く取り上げられます。よって、治療後1ヶ月ほどは直射日光などの強い光を避けて生活する必要があります。
※1 発赤(ほっせき)…皮膚や粘膜の一部が充血して赤くなること
ーー「光線過敏症」による副作用は防ぐことができますか。
篠﨑:はい。直射日光など強い光に当たらない工夫をすることで防ぐことができます。ここで、日焼け止めは全く意味がなくて、肌が露出しないような服装(長袖、長ズボン、帽子、手袋)を身につける必要があります。私は今まで数十例の症例を見てきた中で、光線過敏症のことを理解し対策してくださった患者さんが光線過敏症による副作用を発症したことを見たことがありません。この点でも、光免疫療法は他の治療より副作用が少ないと言えます。
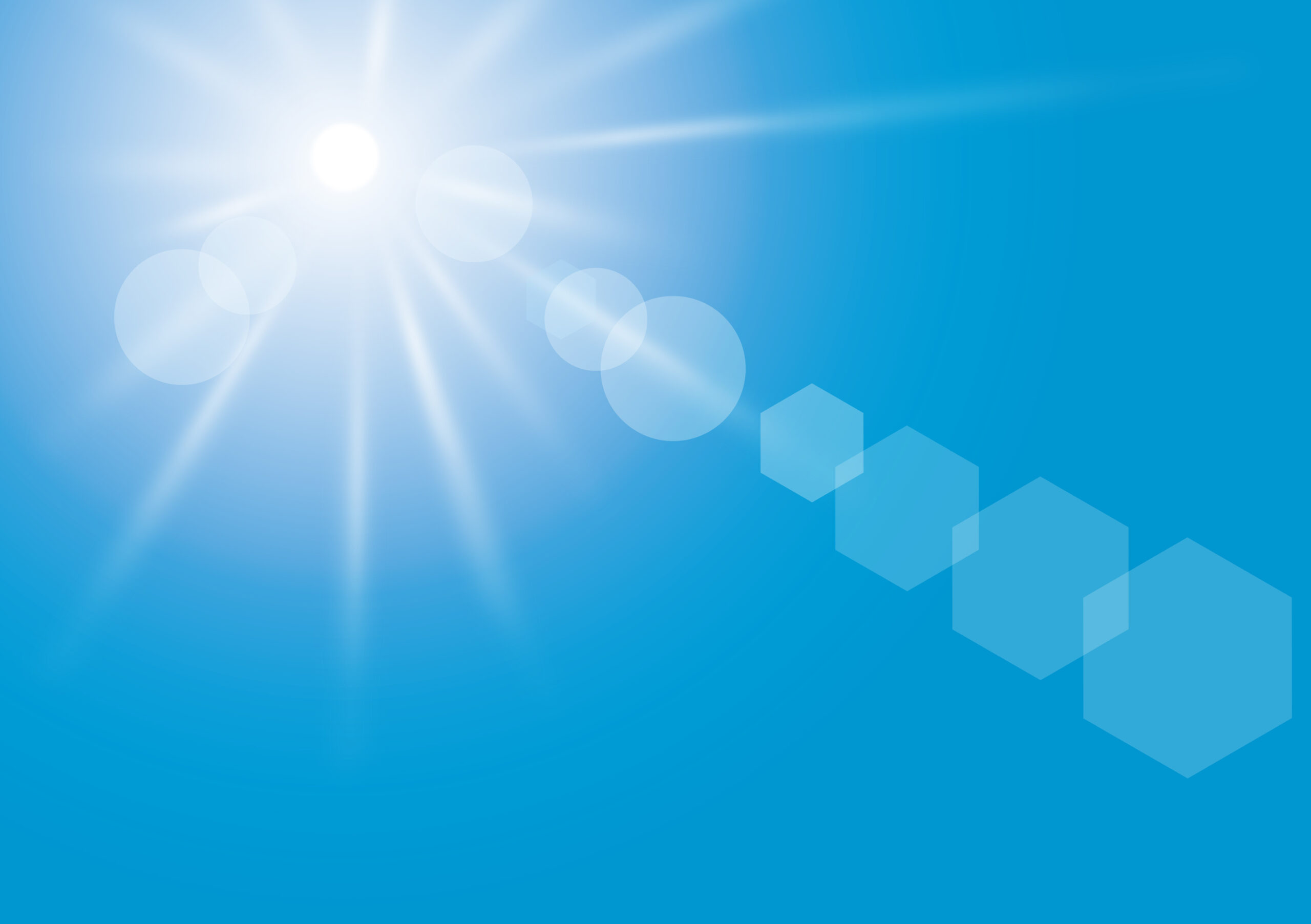
光免疫療法の応用可能性
前記事 # 1 で記した通り、光免疫療法が使える条件
- がん細胞で高発現しているタンパク質に特異的に結合できる薬剤がある
- がん細胞にレーザー光を照射する技術がある
が満たされていれば、頭頸部以外の臓器に対しても光免疫療法は理論上応用可能です。現在は頭頸部がんでのみ光免疫療法が行われていますが、食道がんや婦人科がん、肝転移を有する固形がんなどで治験が行われており、他の臓器に応用されようとしています。
他の臓器に応用するにあたって重要なのは、①EGFR以外にも特異的に結合する薬剤の開発や②デバイスの開発です。
① EGFR以外にも特異的に結合する薬剤の開発
頭頸部がんの光免疫療法(アルミノックス治療)で用いられている薬剤はEGFRというタンパク質に特異的に結合するセツキシマブという薬剤です。現在国内で治験が進行している食道がんや婦人科がんに対する光免疫療法でもこの薬剤が使われています。しかし、がん細胞ないしがん細胞の増殖に関わる細胞の表面に存在するタンパク質はEGFRだけではありません。その他のタンパク質に対して特異的に結合する薬剤が開発されれば、より他の臓器に応用できるようになると期待できます。
現在は、CD25というタンパク質に特異的に結合する薬剤が開発され、「肝転移を有する進行または再発固形がん」に対する光免疫療法として国内で治験が進んでいます。CD25は、制御性T細胞の表面に発現するタンパク質です。制御性T細胞は、がん細胞を攻撃する細胞障害性T細胞の働きを抑制します。光免疫療法によって制御性T細胞を破壊することで、がん細胞が適切に攻撃されるようになります。このように、新たな薬剤の開発が光免疫療法の応用に繋がっていきます。
② デバイスの開発
光免疫療法では、薬剤の投与後にレーザー光を照射します。がん細胞のみを狙って照射する必要があるため、狭い部分や体の深部にある臓器に対しては、治療が難しいとされています。レーザー光を当てるデバイスの改良(焦点距離を短くする、照射径を小さくするなど)により、他の臓器に応用できるようになると期待できます。
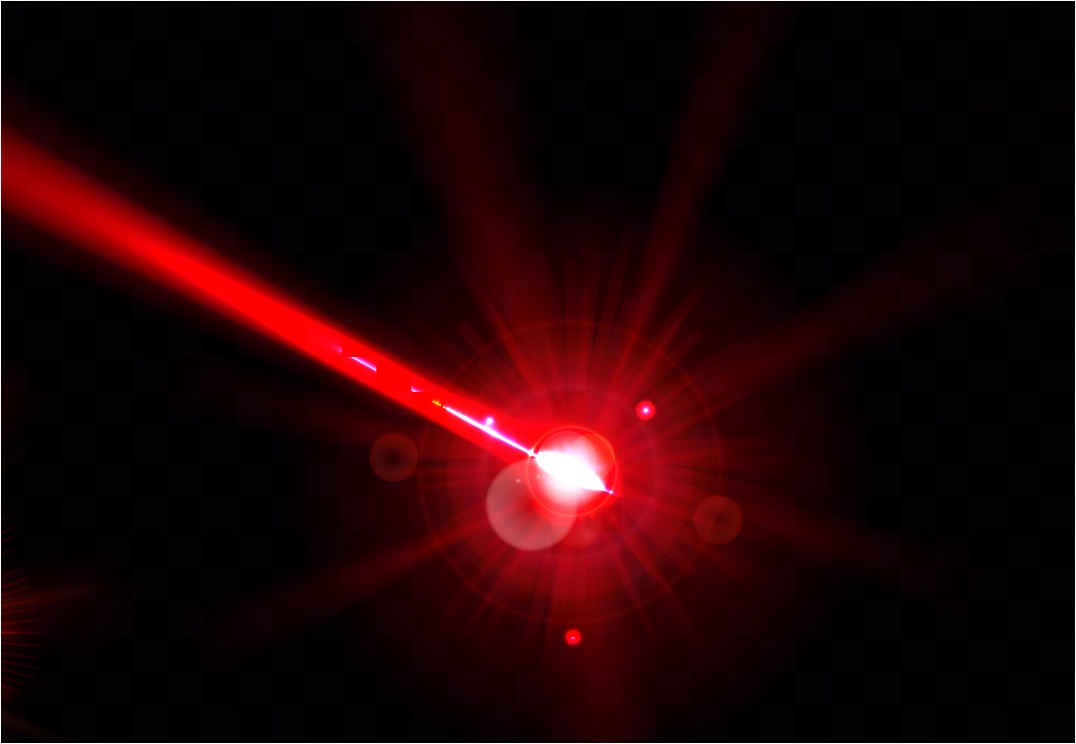
ここからは、実際の臨床現場からの知見についてです。
光免疫療法の選択基準
現在、頭頸部アルミノックス治療は、切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がんにのみ使用でき、化学放射線療法等の標準的な治療が可能な場合には化学放射線療法等を優先することが条件となっています(※2)。我々医師としても、患者さんの病状と全身状態に応じて既存の治療も含めた選択肢の中から最適なものを提案しています。「生きてなんぼ」という考えもとても大事ですが、患者さんが患者さんらしく、豊かな時間を過ごせるために最適な治療を常に考えています。光免疫療法の場合は、侵襲性が低いのは強みですが、他の治療に比べて根治性が低いと言われています。それぞれの治療の特徴を考慮し、「その人らしく」生きられるように、治療を選択しています。
※2 国立がん研究センター東病院「がん光免疫療法全般に関する Q&A」より
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/topics/2024/rakutenQA_20240828.pdf
光免疫療法の治療効果
頭頸部がんに対する光免疫療法(アルミノックス治療)において、がんが完全に消失するのは3割ほどと言われています。他の治療(手術、放射線療法など)に比べて治療効果が高くはないので、標準治療である手術や放射線治療を行った上で治らなかった患者に対して光免疫療法を行っているというのが実臨床の現状です。
患者のQOL
現在は、頭頸部がんの中でも口腔がんや中咽頭がんに対して光免疫療法が使用されることが多いのですが、これらの患者に関してQOLは下がっていないとの報告が出ており(※3)、身体的・精神的負担を抑える上で優良な治療だと分かっています。
※3 東京医科大学 岡本伊作「頭頸部アルミノックス治療(光免疫療法)によるQOLへの影響」より
https://doi.org/10.2530/jslsm.jslsm-45_0019
成功例から得られた知見
他の治療では治らなかった患者さんが、光免疫療法を受けることでQOLも落とさず年単位で生活できたことがありました。この方は残念ながら亡くなりましたが、従来の治療では手の施しようがなかったがんに対する有効策となり得る治療法が生まれたことの重要性を感じました。また、特に上咽頭がんにおいては、綺麗に治る症例を多く見ていますので、全員に効くわけではなくとも一部の患者にとって効果的な治療を手に入れることができたのはとても良かったと思っています。
患者様に伝えたいこと
まずは、ちゃんと成績を出していて、保険診療として認められている治療を受けて欲しいというのが一つあります。その上で、専門家に相談しながらご自身に最適な治療を選択して欲しいと思っています。我々医師は、「がんになってもちゃんと暮らせる社会」を目指して、がんになってもその人がその人らしく生きていけるように治療を選択することで協力していきたいと思っています。ですので、なんでもかんでも光免疫療法を進めるわけでもありません。そして、光免疫療法は「魔法の治療」ではありません。これまでの手術や放射線、薬物療法の方が良い効果が期待できることがよくあります。総合的に判断して、患者さんにとって一番良い治療を選びます。

<国立がん研究センター東病院>
ホームページ:https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/index.html
所在地:〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1
TEL:04-7133-1111(代表)
<日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会>
ホームページ:https://www.jibika.or.jp/



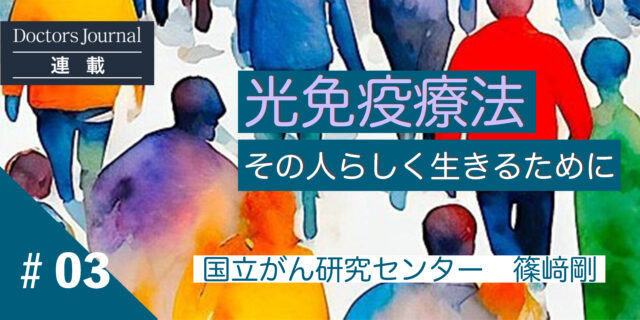
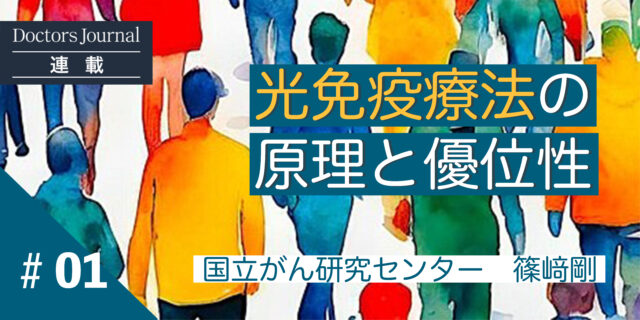
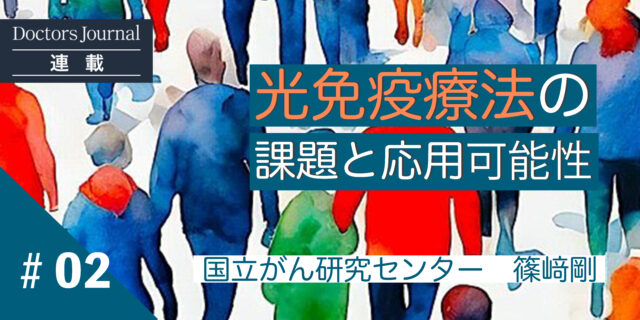
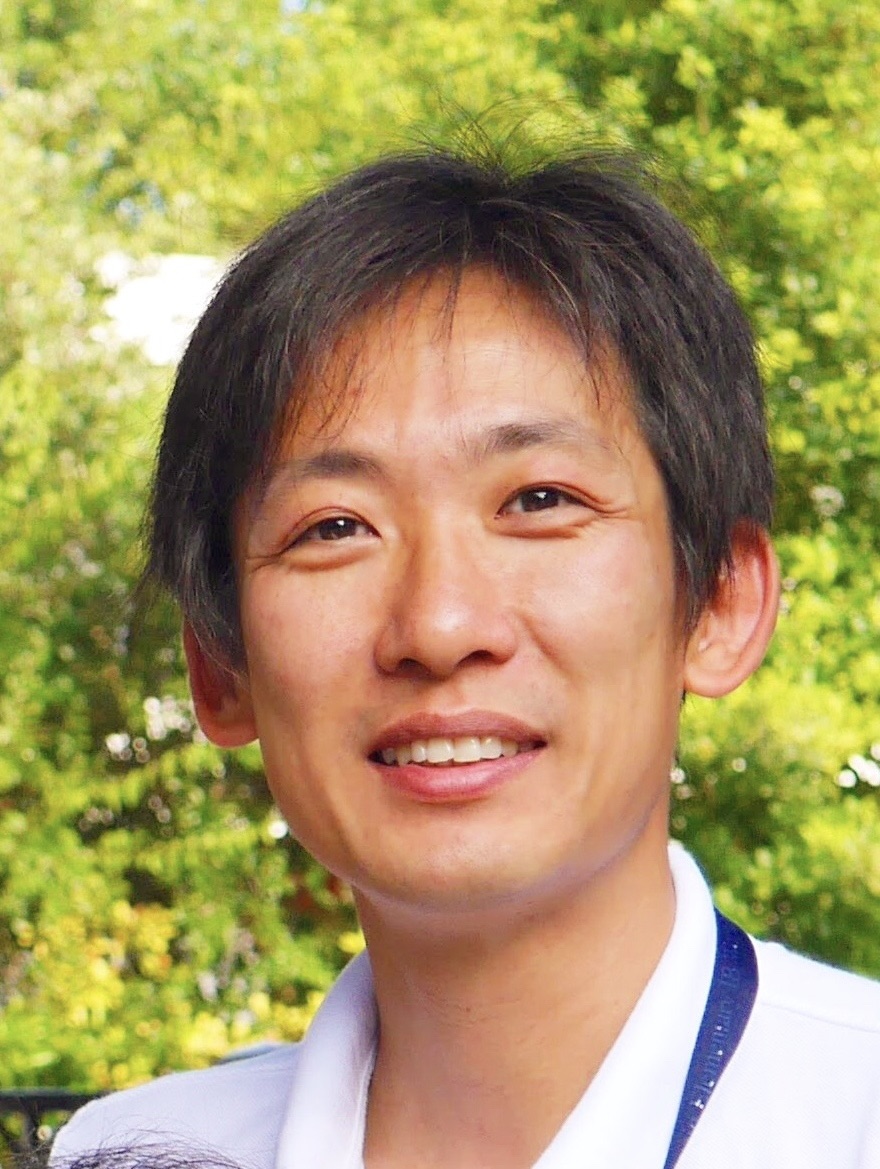





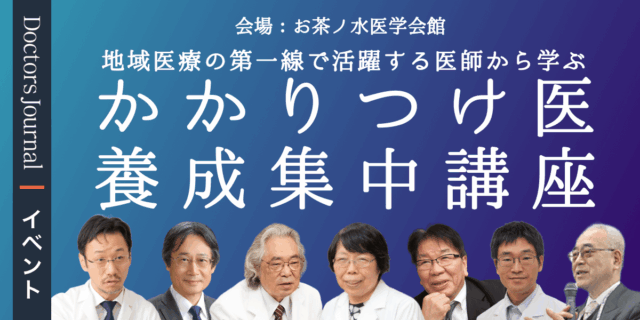
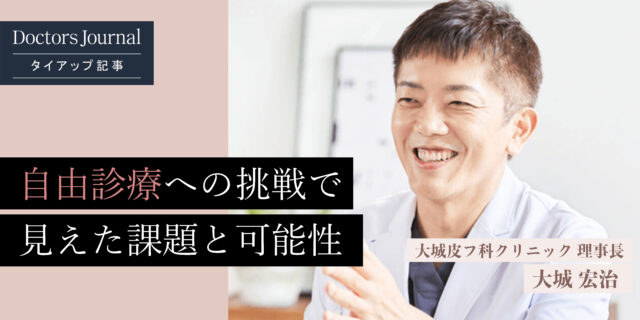
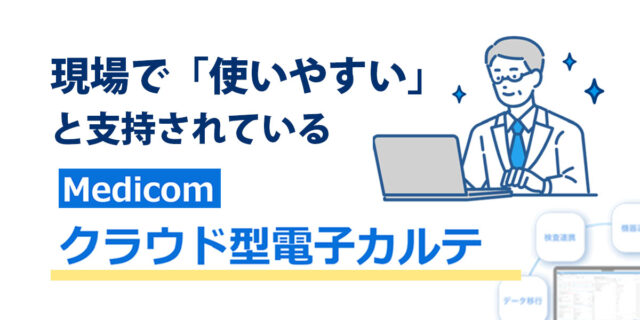
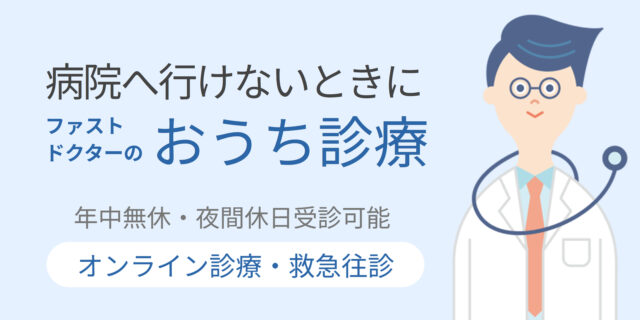























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

