#03 在宅医療における薬剤管理の重要性とは
2024.12.14
前回記事「治療の真髄。家族関係が患者の治癒を導く」に続き、本記事では在宅医療クリニックの開業によって得た認知症治療に関する気づきについて伺いました。
(記事内容は2021年に公開されたものです)
大田区に在宅医療クリニックを開業
その後、東京都荒川区の病院で院長を務めていていた際に、在宅医療と出会いました。そこでは外来診療に加えて往診も行っており、ある高齢者の在宅医療を担当し、私は初めて患者さんの看取りに立ち会うこととなりました。(当時、話題になったプロスポーツ選手のご祖父でした)
その患者さんは、ご家族の手厚い介護のおかげで最後まで大切にされ、穏やかな最期を迎えました。元来、小児科医療に携わっていた頃から、患者と家族の関係が病状に影響を与えることに注目していましたが、この看取りの経験を通じて、医療と家族の間で良好なチームワークが築かれる様子を目の当たりにし、在宅医療への思いが一層深まりました。
在宅医療は、継続的に生きる意味や在り方、そして死ぬということの意味について、私に問いかけてきます。
2004年9月、大田区の現在の地で在宅医療専門の「たかせクリニック」を開業しました。
もともと家族療法による診療を志向していた私には、一人の診察に時間を取れる在宅医療が向いていると考えていましたし、外来クリニックでは患者数が増えると診療時間を十分に取れなくなることもあり、外来と在宅医療を両立させるのは難しいと考えたからです。
また、近隣には高校時代の友人たちが経営する病院がいくつかあり、在宅医療における病院との連携が見込めることも大きな理由でした。
大田区は、田園調布から蒲田地区まで、住民の経済格差が大きい区で、日本の縮図のようなものが見られるかもしれないと思いました。
開業当時は、大田区で在宅医療に取り組む医師はまだ少なかったですね。

認知症は避けて通れないことに気付く
在宅診療を始めてみると、認知症の高齢者の患者さんが非常に多いことに気付きました。さらに、その患者さんを支える家族の中にはうつ状態の方が多いことも分かりました。
診療を続けていくうちに、在宅医療では認知症は避けて通れないことに気付いたのです。
在宅医療のキーワードは、「フットワーク」「チームワーク」「ネットワーク」です。そして、現場をきちっと見る目配りの「アリの目」、木を見て森を見ないことにならないように客観視する「トリの目」、それと魚眼レンズのように広角視野で見る「サカナの目」の3つの目が必要です。
薬を整理することで症状をコントロールする
在宅医療では、薬(医療)が2割、ケア(介護)が8割というのが、私の考えです。
薬を整理し、時には減らすことで高齢者の生活の質(QOL)と身体機能が上がる経験を何度もしました。歩けなかった人が歩くようになるケースも珍しくありません。
患者さんが症状を訴えるたびに薬が増える。医師も専門領域でない薬の副作用には気付きにくいということがあります。
また、高齢者には注意が必要な薬も種々ありますが、慎重に投与すべき薬が安易に処方されていたり、分量が多すぎたりするケースも多くあります。
特に睡眠薬には注意が必要です。効果が切れるとき、高齢者は意識混濁や幻覚が出やすい傾向があります。眠れないのには必ず原因があります。
認知症の診断による不安や家族関係の悩みなど、まずご本人から話を聞いて眠れない原因を探り、カウンセリングをしながら対処していくことが必要なのです。
抗認知症薬の服用はできるだけ早期のタイミングが望ましいですが、多剤服用による症状がある場合は、薬剤を整理して症状が安定してきた後に抗認知症薬を始め、継続することで認知症の症状が安定する傾向が多くあります。
多剤服用の状況から、薬で症状をコントロールするのは難しいため、時には処方内容の見直しも考慮します。特にレビー小体型認知症では抗精神薬に対する過敏性があるため、注意が必要です。
処方の見直しや薬を減らした直後は注意深い観察を要します。在宅医療の現場では、家族や介護者の協力と共に医師・看護師・薬剤師・ケアマネジャー・ヘルパーなどを含めた多職種での「チーム・モニタリング」による協働が必要です。
在宅認知症高齢者の実例
高瀬義昌氏の在宅認知症高齢者の実例として、80歳の方が1日に15種類27錠の薬を処方されていましたが、5種類7錠に変更したところ、数日後には歩けるようになり、夜もよく眠れるようになりました。
せん妄や徘徊もなくなり、それまで激しかった暴言や暴力などの認知症の周辺症状(BPSD)だと思われていた行為もおさまり、デイサービスにも通えるようになったといいます。
この高齢者は50代から慢性疾患も抱えており、ペインクリニック、内科、精神科、整形外科など、診療科が増えるたびに薬も増えていき、最終的には計15種類の薬を処方されていました。驚くべきことに、これらの薬剤を1つの調剤薬局で受け取っていたそうです。
薬の減量による結果は症状の改善だけでなく、1日分の薬の価格差額が704円、年間で約26万円もの医療費の節約にもつながりました。髙瀬義昌氏によるこの事例は、国会議員も取り上げ、大きな話題となりました。
(続く)





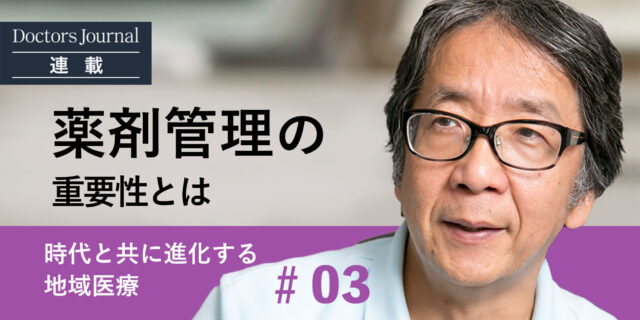

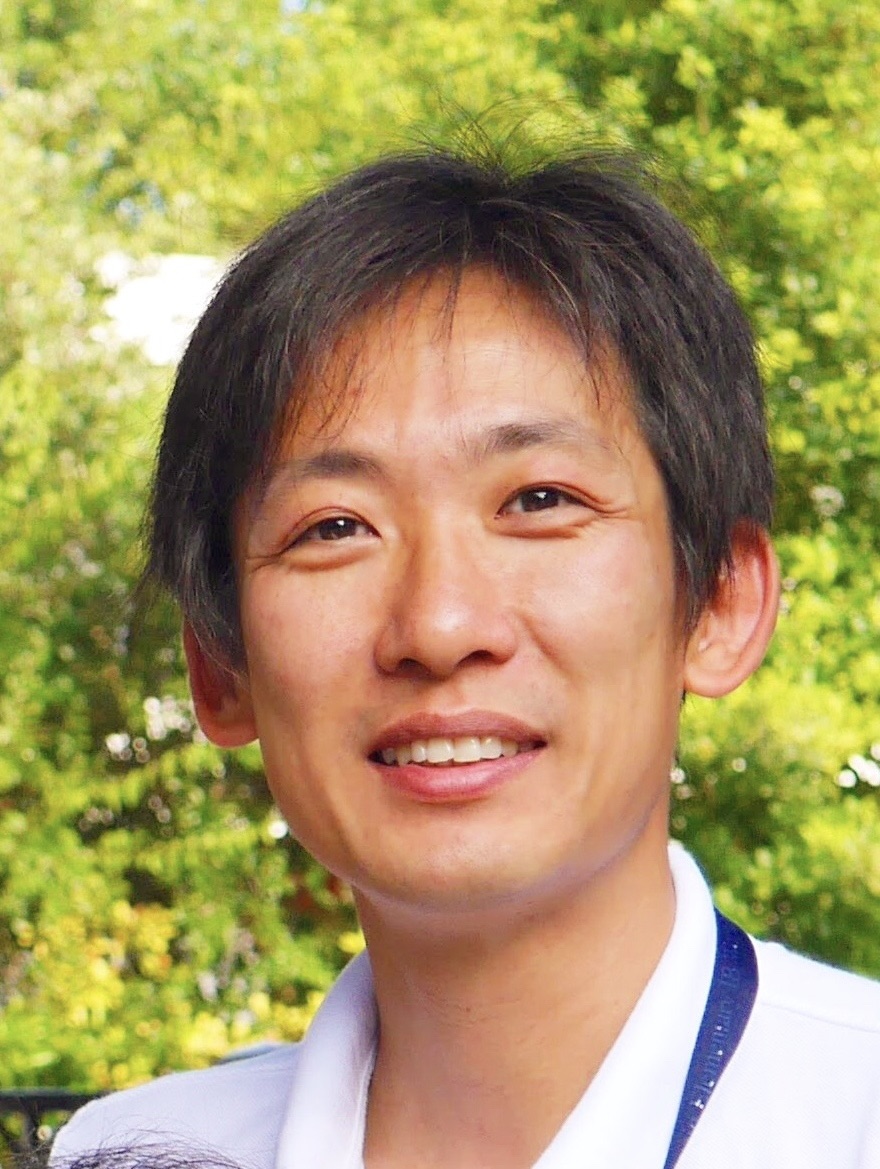





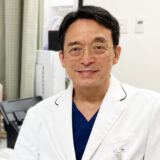



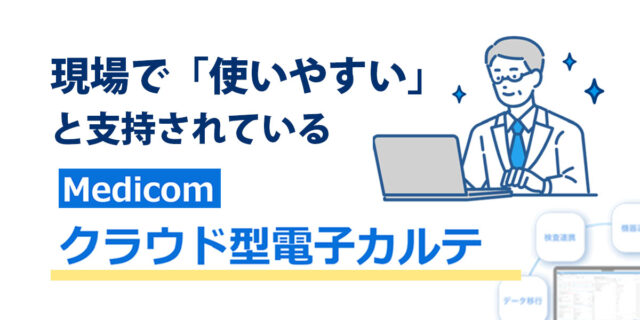
























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

