#03 認知症の人達に関わることは、本当にやりがいがあり、とても楽しいこと
連載:生まれ故郷をこよなく愛し、大好きな慢性期医療に取り組む
2021.12.23
当時は認知症の患者さんに対して、どうしたら良いのか分からなかった。
内田病院に勤務した当初、私は最初から認知症の専門医ではなく、内分泌や糖尿病が専門でした。
認知症に取り組むようになった理由は、ここに認知症の患者さんが大勢おられたからです。
慢性期医療の患者さんでは9割近くの方に認知症があります。当時は、拘束されて騒いでいる認知症の患者さんがいたりして、現場の看護師や介護スタッフは困り果てていました。私はその姿を見て本当に驚きました。
食事の時にお味噌汁を上履きの中に撒けてしまうような人がいて、誰も拘束など望んでいないのに、どうしていいか分からない。それを皆、当たり前と思って何も考えずに縛っていた。
本当にどうにもならない状況がありました。尋常ではない世界です。みんな疲れ果てているし、こんな状況が長く続くはずもないと感じていました。
当時の多くの老人病院ではそれが当たり前でしたが、私には抵抗があり、この状況をどうにかしなくてはいけないと考えました。
そこで私は、縛られている患者さんをほどいて回りました。看護師やスタッフの抵抗もありました。私が毎朝ほどいて回っても、夕方にはまた縛られている。それをまたほどいて回る。そんなことを半年間、一人で泣きながら繰り返していました。本当に悔しくて仕方がありませんでした。
ところが半年目くらいから、患者さんの目に光が出てきて、目が合うと「ありがとう。」と言われるようになったりして、実は心が通じることが分かってきました。そのうちにスタッフからも賛同者が出始め、1年後には全く身体拘束がなくなりました。
そうであれば、お味噌汁を上履きの中に撒けてしまう患者さんにもきちんと話したら心が通じるのではないだろうか、と思うわけです。
そのような症例を一例ずつ手探りで積み重ねていきました。そのような関わり方の中で、「この人たちはどうにもならない人ではなくて、一人の人なのだ。」と思うようになってくるのです。
当時はまだ痴呆と言われていて、患者さん達はただ迷惑な対象としてしか扱われていない、そんな時代でした。
身体拘束をやめてから、病棟全体が明るい雰囲気に変わりました。
拘束を外してゆくと、面会がとても増えました。面会が少ないのは、実は私たちのせいだったのだと気づきました。今は病院だけでなく特養などの施設にも面会の家族が足しげく通ってこられます。そんなケアを行っていることでスタッフも変わっていきました。
認知症の人達に関わることは、本当にやりがいがあって楽しい。
しかも、まだ認知症の薬もなかった時代です。そんな中で、自分たちが認知症の患者さんにしっかりと関わりケアすることで症状が良くなるということが体験できると、面白くなってくるのです。
そうしているうちに、拘束がどんどん外れていきました。拘束が外れると今度は、起こしたり、食べさせたりする方向に向かっていきました。そうすると、まるで未開の
荒れ野原だったところに、いろいろなことができるようになっていきました。
食べられるのなら食事を良くしていこう。拘束しなければ褥瘡も治るよね。アクティビティは何ができるだろうか。とか、私たちが取り組めることがたくさん出てきました。
ですから、早い時期から食事にも取り組んできましたし、排泄にも取り組んできました。
褥瘡も2004年の褥瘡患者管理加算のはるか前から、数多くウォーターベッドやエアマットを導入していました。アクティビティも、アートセラピーや音楽療法など、世の中で話題になる前から取り組んできました。
それらは全て、一人の患者さんが快適に過ごせるためにはどうしたら良いのかと考えた結果から出てきた取り組みでした。
そんな取り組みを続けていると、それまで見放されてきた人たちの目が生き生きしてくるのです。さらにその姿に接するスタッフが輝いてくるのです。認知症の人達に関わることは、本当にやりがいがあり、とても楽しいことだと感動しました。















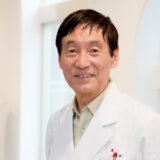
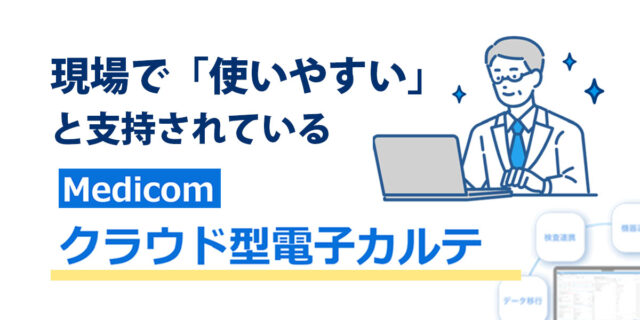

























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)


