#04 地域包括ケアにおけるシステム・スタビライザーの役割
2024.12.21
前回記事「在宅医療における薬剤管理の重要性」に続き、本記事では在宅医療における本質的な支援の重要性について伺いました。
(記事内容は2021年に公開されたものです)
在宅診療の卒業式
私たちは、在宅医療を受けている患者さんが一人で歩けるようになったり、自分で食事ができるようになった場合に、在宅診療の卒業式を行っています。
この式では、患者さんを表彰し、お花を贈呈して、在宅医療からの卒業を称えます。このような取り組みをしているのは極めて珍しいのではないでしょうか。私たちは在宅医療の在り方を示す時代のモデルルームでありたいと考えています。
医療者として、特にプライマリ・ケアでは、患者さんの行動変容を促すことが真のプロの役割だと考えています。
患者さんの行動変容や認知の変容ができない場合、それは医療側の力量不足を意味します。医療者は常にカウンセリングとコーチングの質をブラッシュアップしなければならないと思っています。
支援の本質とは何か
日本のキャリア研究の第一人者である神戸大学大学院の金井壽宏教授が監訳された本に、エドガー・H・シャインの『HELPING』(邦題『人を助けるとはどういうことか 本当の「協力関係」をつくる7つの原則』)があります。
エドガー・H・シャインは、組織心理学者として世界的に高名なマサチューセッツ工科大学の名誉教授です。
彼は組織行動論におけるクリニカル・アプローチやプロセスコンサルテーションを考案した組織論の第一人者であり、私が尊敬する学者の一人です。2011年には渡米してご本人と面会しました。
エドガー・H・シャインは『HELPING』の中で、援助の本質とは何かを「支援学」として以下のように解説しています。
相手のためになりたいと思って接するのに、それが意外と難しいことに気付かされることが多い。親切が仇になることもよくあるが、それは、助けを求める側が助言に耳を傾けないから生じることもあろう。だが、助ける側が、相手の要望に耳を傾けることなしに、頭ごなしに答えめいたものを押し付けているせいであることも多い。
援助の本質は、何でも全部してあげることではありません。在宅医療における支援の在り方の答えがここにあるように思います。まずこのことを、医療を提供する側が理解していなければなりません。

在宅医療はレスキューシステムです
厚生労働省の新オレンジプランでは、2025年に認知症の人口が700万人に達すると言われています。この増加により、地域包括ケアは人手不足などの理由で不十分な面があり、多くの人々が支援を受けられなくなる可能性があります。病院ではこの問題に対応できません。
その人たちのレスキューシステムこそが在宅医療だと思っています。在宅医療に取り組んでいる医師はキャッチャーボート(捕鯨船団の中で、母船に付属して鯨を捕らえる役の船)のような存在です。
地域の医療現場で活動しているため、在宅医はさまざまな患者情報に触れます。それにいち早く対応し、患者さんを地域の中で見守ります。
当然、リスクもありますから、緊急時には安全に病院に繋ぐなど、いわば懐深い病診連携が大切です。しかし対応できる病院が少なくなっているのが現状です。
これでは、キャッチャーボートがあっても母船がないのと同じです。
システム・スタビライザーが私の役割
在宅医療や地域包括ケアを効果的に機能させるためには、システムを安定化させるためのカギがどこにあるのかを探り、時間と費用の効率化を図り、最大限の成果を出すための方法を見つけ出し、実行する役割が必要です。
私はそのような役割を「システム・スタビライザー」と名付けています。私の役割はまさにそれだと思っています。
そして、最大限の効果を生み出すカギはチームワークやネットワーク、フットワークにあります。これらをシステムの中で効率的に動かしていくことが、私の仕事の醍醐味でもあります。
ホメオスタシス(生体の 内部や外部の環境因子の変化に関わ らず生理機能が一定に保たれる性質)のように、人間の体は様々な機能を持った異なるパーツが無駄なく集まり一個の総体となって効率よく機能し生体の状態が保たれています。
社会においても、同じことが言えるのではないでしょうか。
社会もまた一つの生き物と考えられます。地域包括ケアや厚生労働省、医師会などの組織も、一つの生き物と言える。それぞれにシステム・スタビライザーは必要だと思います。

在宅療養空間システムを如何に安定させるか
地域のシステム・スタビライザーを自称する私にとって、在宅療養空間というシステムを如何に安定化させるかが重要なテーマです。
そのためには、在宅療養の継続を阻害する種々のリスクを明確にし、それに対してのリスクマネジメントのプログラムを作り、参加者たちが各々の役割を果たすという、全体がサイコドラマ(シナリオのない即興のドラマを用いて心理的葛藤の整理や解決を図る治療教育的方法)のような形で、トータルで在宅療養空間が安定して継続できるような仕組みをデザインすることが重要だと考えています。
同時に、在宅医療空間が破綻することもあります。在宅の患者さんが、せん妄が起こしたり、骨折したり、感染症や合併症を起こしたりする場合です。これは認知症に限らず、老化によっても生じます。
その際には、薬とケアを最適に組み合わせることが重要です。
それをチームでモニタリングしながら、患者さんにとって最適な在宅医療のPDCA(Plan・計画 → Do・実行 → Check・評価 → Action・改善)サイクルを回すことを、それぞれの医師や看護師、ケアマネジャーがデザインできれば素晴らしいと思います。
(続く)


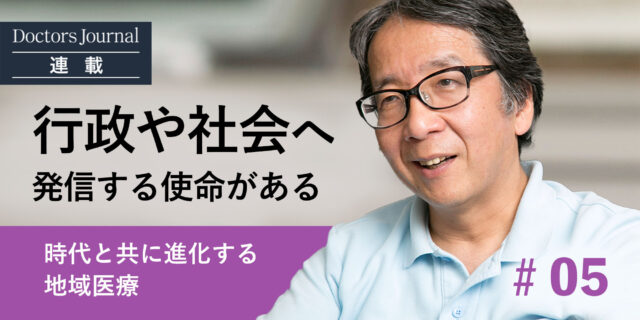
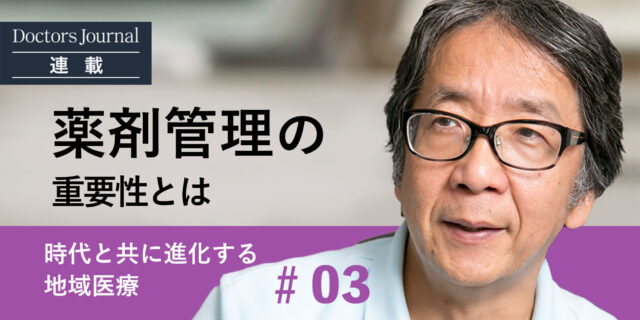
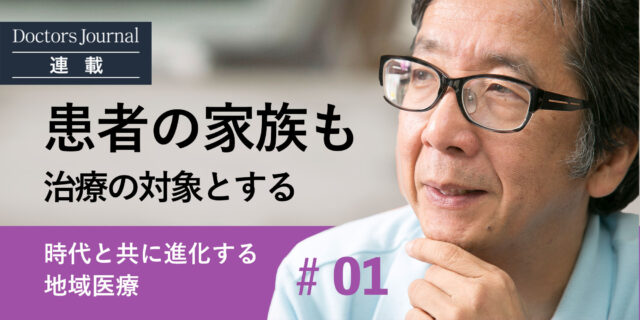


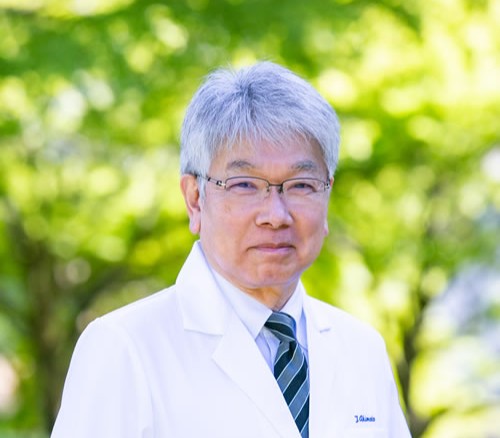

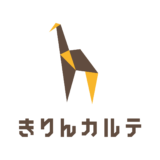
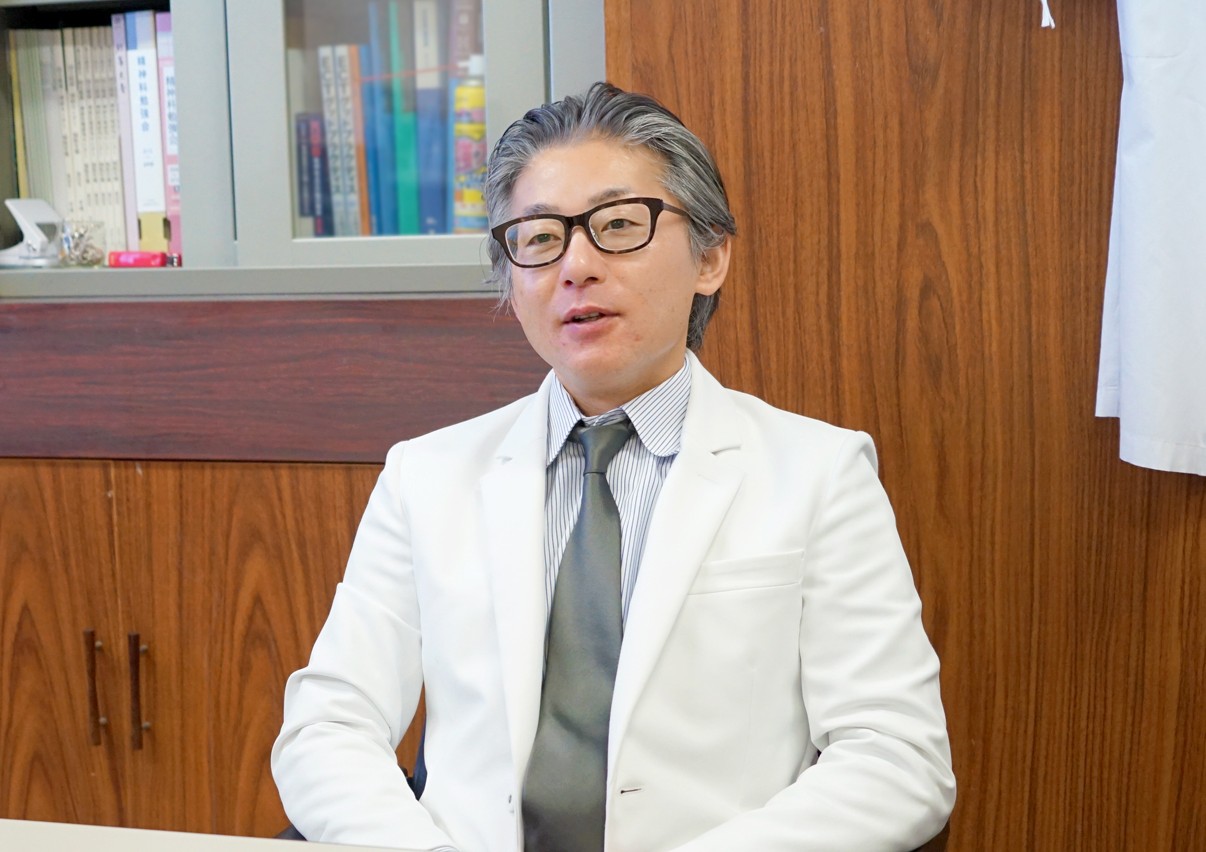



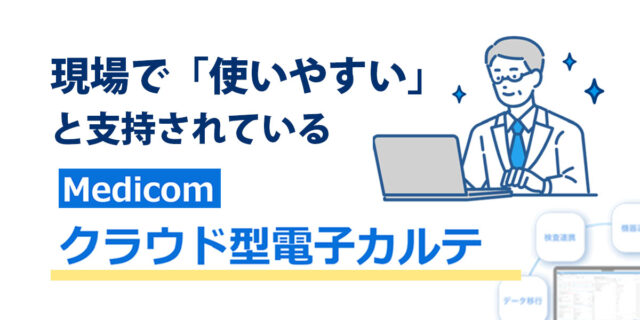
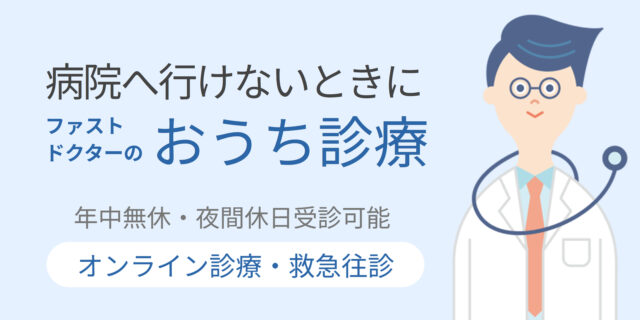

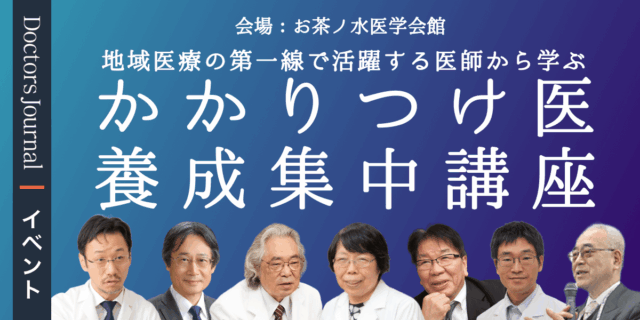



















![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)



![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)
