ターニングポイントになったキューブラー・ロス『死ぬ瞬間』との出会い
連載:在宅のホスピス緩和ケアで、 安心して看取りができる地域づくりを目指す
2023.05.19
日本におけるホスピス運動を語るうえで欠かせない名著『病院で死ぬということ』の著者である山崎章郎氏は、船医時代に医師人生の転換点となる出会いを果たしたといいます。本記事では、山崎氏に医師を志したきっかけから医師として目指すべき姿を見つけるまでの経緯を伺いました。
取材協力:山崎章郎氏
在宅緩和ケア充実診療所 ケアタウン小平クリニック 名誉院長
- 1947年:福島県郡山市出身
- 1975年:千葉大学医学部卒業、同大学病院第一外科
- 1984年:国保八日市場(現・匝瑳)市民病院にて消化器科医長を務め、院内外の人々とターミナルケア研究会を開催
- 1990年:著書『病院で死ぬということ』刊行
- 1991年:聖ヨハネ会桜町病院ホスピス科部長
- 1997年:聖ヨハネホスピスケア研究所所長を兼任
- 2005年:在宅診療専門診療所(現・在宅緩和ケア充実診療所)ケアタウン小平クリニックを開設し、訪問診療に従事
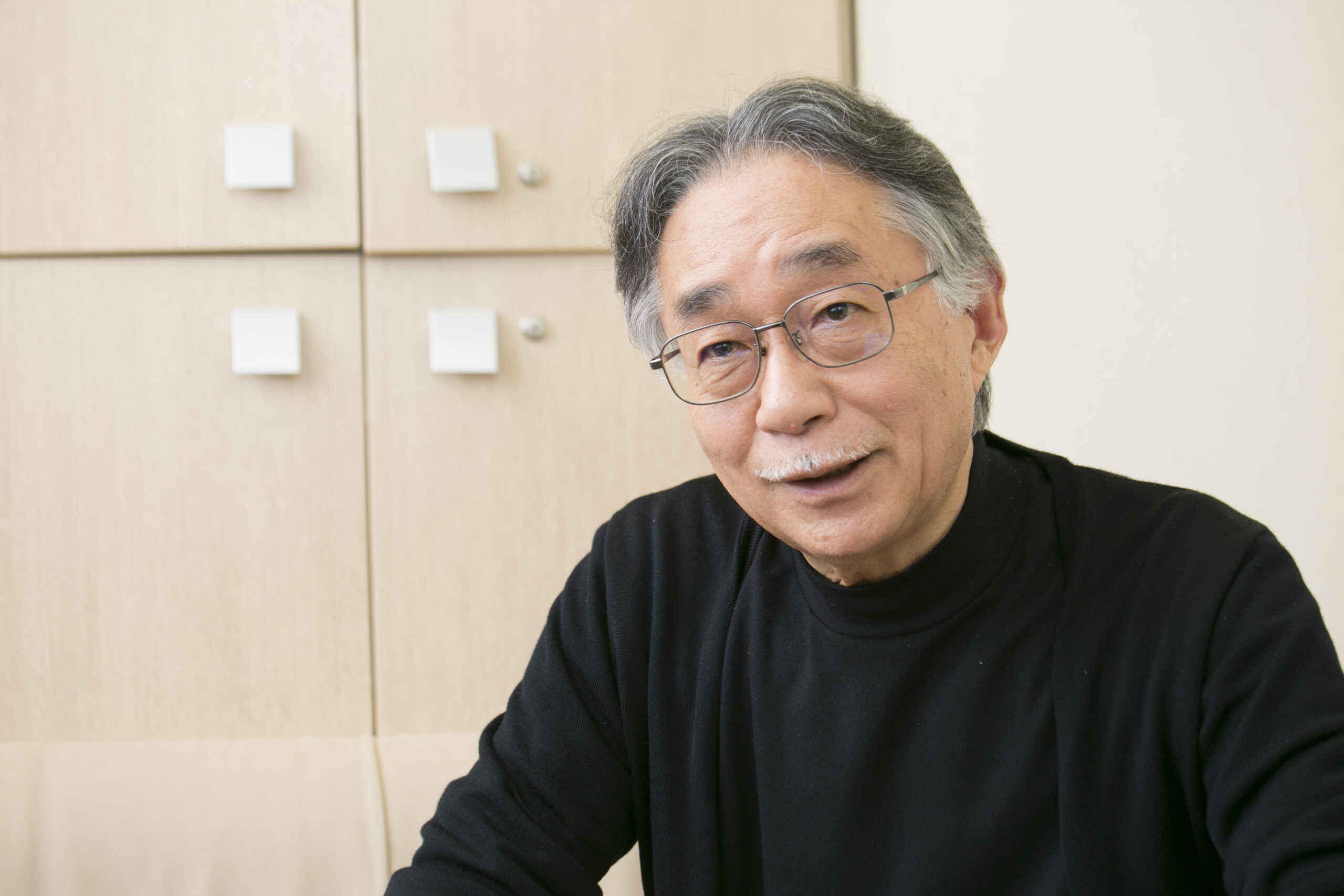
制度ができ報酬がつくと増える「緩和ケア病棟」
1990年に『病院で死ぬということ』を発刊した当時は、多くの患者さんが病院医療の枠組みの中に取り込まれて、自分の意思を明確に表明することもできないままに亡くなっていました。
当時、読者の看護師や医師達からは「同じことを考えていました。」とか、「よく言ってくれました。」というような共感の手紙をとても多く頂いたのを覚えています。私と同じように疑問を感じていた人たちが多くいたことと、それでも具体的にどう取り組んだら良いのか分からず悶々としているということが、よく分かりました。
それから28年が過ぎ、今では環境や状況も随分と変わってきました。例えばこの間に、緩和ケア病棟(ホスピス)、緩和ケアチーム、在宅緩和ケアの制度上の後押しも整備されました。その結果、緩和ケアに取り組む医療機関や医師達も増えてきました。
1980年代に、聖隷三方原病院や淀川キリスト教病院が社会的使命感からホスピスに取り組んだ頃は制度が無かったので、多くの寄付により運営されていたと思います。
1990年に、緩和ケアに関する診療報酬上の初めての評価として「緩和ケア病棟入院料」が設定されました。その後、緩和ケア病棟(ホスピス)数は診療報酬が上がるたびに増えるという広がり方を見せます。そこには、「病院経営上の戦略としての緩和ケア病棟」もあるかもしれません。どれだけの施設で、ホスピスケアの本質が踏まえられているだろうか、という懸念はあります。

子供の頃に感じた世の中の不条理や不公平
福島県で子どもの頃を過ごした昭和30年代は、日本が今ほど豊かではなく、クラスには貧しい級友が多かったのですが、我が家は父が中学校の校長だったので、経済的には恵まれていたほうでした。
当時の私は、彼らとの境遇の違いに引け目を感じていました。例えば、級友の質素な弁当とは違う、少し贅沢な自分の弁当が恥ずかしく、隠しながら食べていた。というような子供でした。
同じ人間のはずなのに、親の職業という自分とは関係のない理由で、格差や貧富の差が生じていることに、子どもながらも不条理や不公平を感じていたのだと思います。そのような社会意識の芽生えは、その後の人生に大きく影響していると感じます。
建築家を目指し受験勉強をしていた高校3年の夏休みに、当時大きな社会問題となっていた、薬害によるサリドマイド児たちの整形手術のために北欧から医師が来日した、という新聞記事を読んで、進路を医学部に変えました。
何の責任もない子供たちが、薬害のために生まれながらに障がいを持たざるを得ないという悲惨な事実にショックを受け、その子供たちのために海外の整形外科の医師が来日したことに対して非常に感動し、自分も整形外科医になって、少しでもそのような人たちの役に立ちたいと思ったことが理由でした。
外科医を経て船医になる

進学した千葉大学では、当時の学生の多くがそうであったように、私も学生運動に参加しました。その学生運動に挫折し、それまで目指していた医師像が崩れてしまいました。
自分が整形外科医になり、障がいがある人たちを何とかしてあげようと思ったのは、動機は純粋だったとしても、健常者の自分の単なる同情心からで、それは傲慢ではないだろうか。と、目指していた整形外科医になる理由がわからなくなってしまったのです。
その後の私は職業人として外科医を選び、大学の医局に進んで外科の経験を積むことにしました。最初から学位を取るつもりはありませんでしたので、そのうちに医局での仕事にも限界を感じ、学生時代からの夢である船医を経験してから、一般の病院に勤めてみようと思いました。実は愛読していた北杜夫氏の「どくとるマンボウ航海記」の影響でした(笑)。
1983年の5月から3ヶ月間、船医として北洋サケマス漁船団の母船に乗りました。 さらにその後、南極の海底地質調査船に4ヶ月間乗りました。
キューブラー・ロス『死ぬ瞬間』との出会いがターニングポイントとなる

南極の地質調査船の中で読んだ、E・キューブラー・ロスの著書『死ぬ瞬間』が私の医師人生の転換点となりました。
『死ぬ瞬間』の中に描かれたある農夫の死の場面で、生の終わりには、鎮痛剤よりブドウ酒、輸血より家のスープのほうが患者には、はるかにうれしい。という一節を読んだ時には、鳥肌が立つほど感動しました。
それまで医師として、多くの人の亡くなる場面に立ち会ってきましたが、臨終宣言の前には必ず心臓マッサージを行い、人工呼吸を行い、それが終わってようやくご臨終ですと言ってきたわけです。
押せば心臓は動きますが手を離せばまた止まるわけです。心電図のモニターを見ながら、その繰り返しをしばらく行った後、臨終宣言を行うのです。患者さんは、治らないのにそんな苦しい医療を受けてしまうわけです。
それまで当然の如く行っていた延命治療への疑問
つまりそれらは医師が臨終宣言をするための儀式のようなものでした。
『死ぬ瞬間』の中の、患者さんが家で家族に囲まれて穏やかに死んでいく場面に、すごいショックを受けたわけです。こんな風にして人は死ねるのかと。自分がそれまで看取ってきた人たちの最期の場面と比べてみたら、想像もつかなかった。自分がこれまで行ってきた延命治療を振りかえざるを得なかったのです。
患者さんの命が助からないことを誰もが分かっているのに、延命のために行ってきた心臓マッサージや人工呼吸は、本人のためではなく、医師や看護師たちの自己満足だったのではないか、と。ようやく自分が目指すべき医師としての姿が見えた気がして、船を降りたら今までと違う医師になれると思いました。
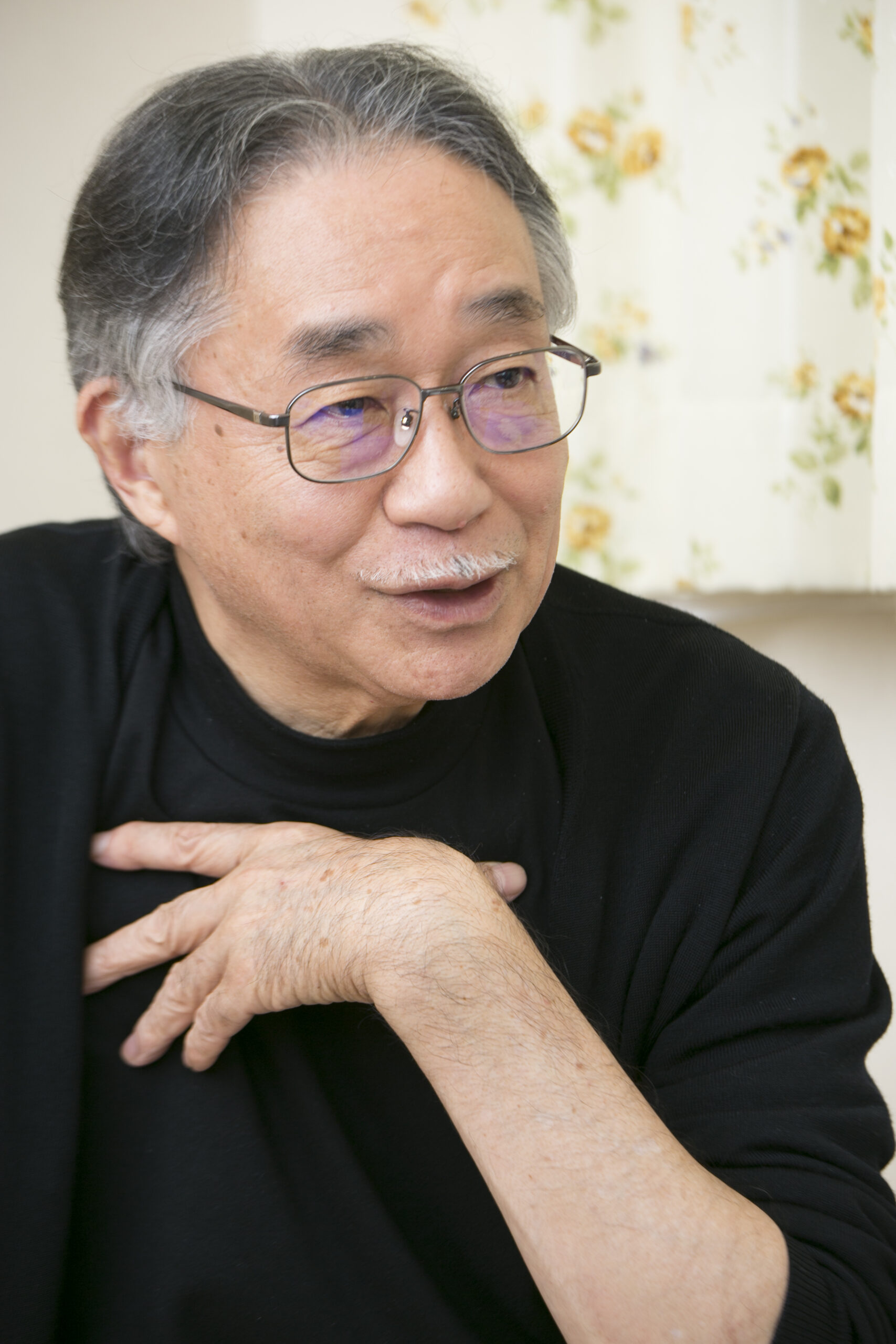
家族に聞けば断られる延命医療としての蘇生術とはいったい何なのか
船を降りて、1984年から外科医として勤務した八日市場市民総合病院(現匝瑳市民病院)では、患者さんが亡くなっていく時には、自分の判断だけで蘇生術は行わず、必ず家族に聞くようにしました。
亡くなられていく患者さんの家族に対して、「残念ではありますが患者さんは最期の時間を迎えられようとしています。私は医師として、若干ではありますが命を延ばすために心臓マッサージや人工呼吸もできますが、どうしますか。」とお尋ねすると、9割以上の家族から「それはしなくて結構です。」「ここまで頑張ってきたのだから 静かに見守りたい。」と断られました。
この経験から、家族に聞けば断られるようなことを、これまで確認もしないで行ってきたということに気付き、終末期患者への蘇生術が医師の自己満足だったということを確信しました。
それでも、そのような蘇生術は当時の医療の現場では当たり前のことで、このような疑問を持つ医師はほとんどいなかったと思います。
キューブラー・ロスの著書に出会わなかったら、私も疑問に思わなかったかもしれません。しかし疑問に思って確認してみたら断られたことで、これまでの間違いが分かったということが私にとっての第一歩でした。
続く

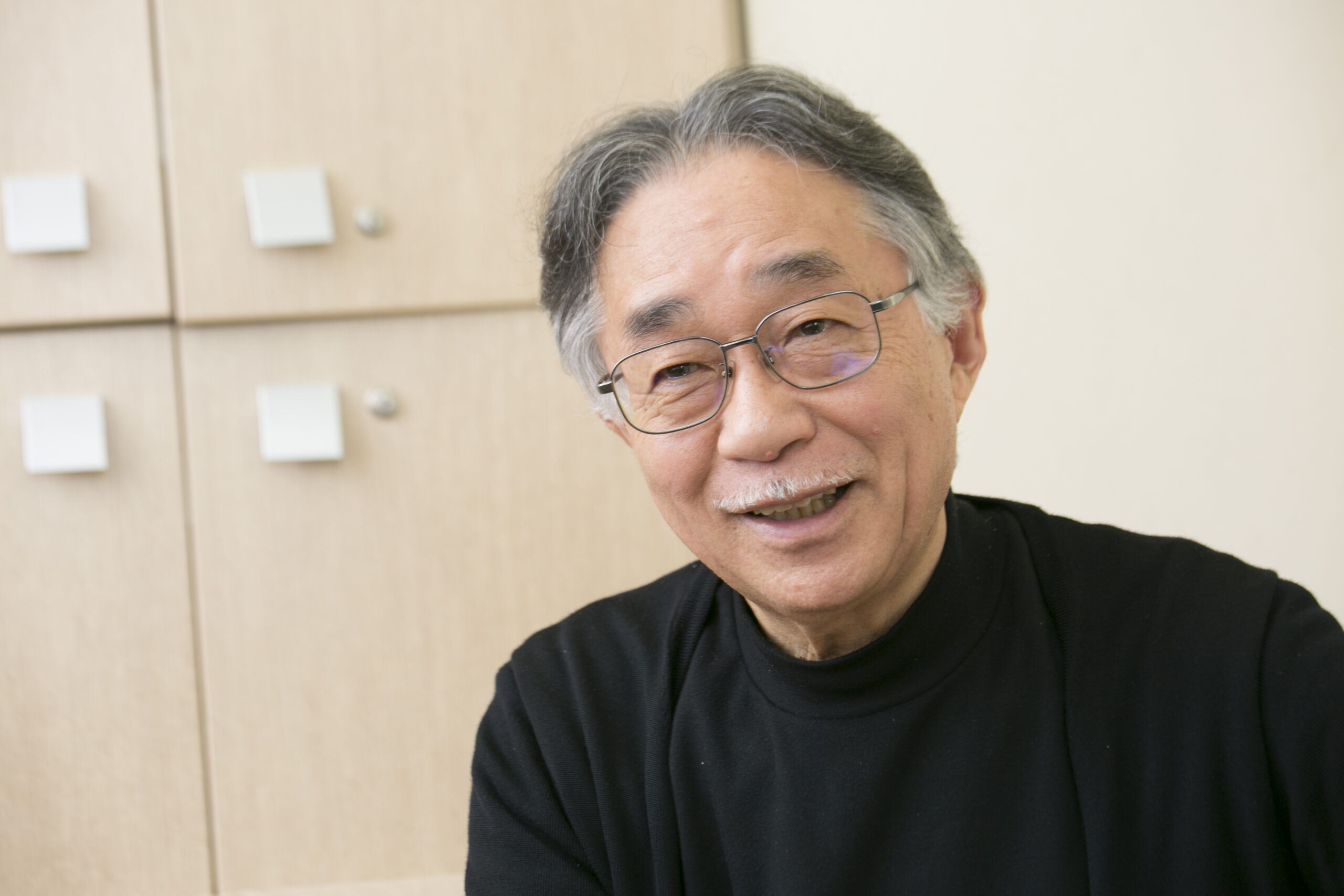








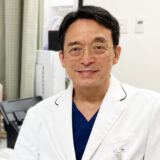




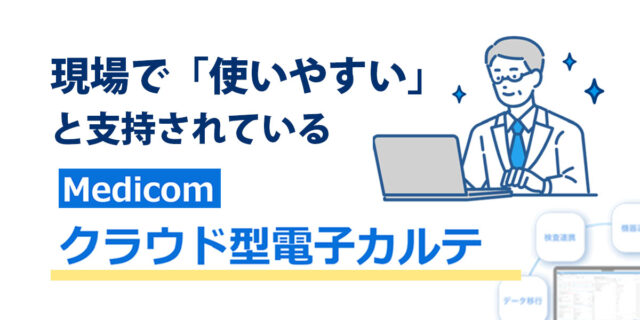
























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

