#03 革命的なICF(国際生活機能分類)の考え方
連載:「その人の尊厳を尊重しながら、病気は家で治す。最期まで寄り添う。」
2020.01.08
ICF(国際生活機能分類)の考え方とは。
― リハビリテーションに関連したテーマとして、最近では、個人の障害に対する考え方や捉え方が大きく変わってきていると伺いました。どのようなことなのでしょうか。―
WHO(世界保健機関)が定めている障害に関する国際的な分類としては、1990年代はICIHD(国際障害分類)だったのですが、最近ではICF(国際生活機能分類)に考え方が変わってきています。
私は以前より、ICIHD(国際障害分類)の考え方には疑問を持っていました。
ICIHD(国際障害分類)では、障害を生じさせている個人の機能が改善しなければゴールは達成できないという考え方です。
しかし、ICF(国際生活機能分類)は、障害は障害として受け入れて、例えば歩けないのなら車いすを使って移動すれば仕事場にも行けるという考え方です。
呼吸障害のあるALSの患者さんにとって必要な人工呼吸器は、一般の人からは、たいそうな医療機器に見え、でそれだけで大きな障害だと思われがちです。
しかし、人工呼吸器があたかも眼鏡と同じような感覚で使えるようにテクノロジーが進歩すれば、ALSの患者さんで呼吸障害があっても普通に生活ができる、仕事もできるようになります。そういう時代を目指すべきではないかと思うのです。
そのためにはテクノロジーの進歩と同時に障害に対する考え方の進歩も重要で、障害がICF(国際生活機能分類)の考え方に変わったということは、一つの革命にも匹敵するものではないかと思っています。
―ICF(国際生活機能分類)とICIHD(国際障害分類)―
障害に関する国際的な分類として、従来は世界保健機関(WHO)が1980年に「ICD(国際疾病分類)」の補助として発表した「ICIHD(国際障害分類)」が用いられてきたが、その改訂版として、2001年5月に「ICF(国際生活機能分類)」が採択された。
「ICIHD(国際障害分類)」では、障害を「機能障害」「能力障害」「社会的不利」という3段階のレベルに分類している。
しかしICIHD(国際障害分類)の考え方では、障害をハンディキャップとし「できない」と言ったマイナスで否定的に捉えられてしまうなどの問題点があり、障害を持つ人の社会復帰を目指すものではなかったといえる。
それに対して、「ICF(国際生活機能分類)」とは、人間の「生活機能(人が生きていくこと)」と「障害(何らかの理由で人が生きていくことが制限されている状況)」を判断するための「分類」方法を示したもので、障害があっても「こうすれば出来る」と言ったような、ポジティブな考え方で捉えようとする見方である。
人間の生活を障害の有無のみではなく、日常活動や社会参加の状況、また周囲の環境など広い視点から理解し、サポートにつなげることを目的としていて、障がい者への偏見や差別を無くすものであると考えられる。
これまでは人間の障害や生活機能を考える際に、「医学モデル」と「社会モデル」という考え方が主流だった。
「医学モデル」とは、障がい者が受ける社会的不利はその障がい者個人の問題だとする考え方で、病気やけがなどが障害を引き起こすものとして理解される。そのために障害への対応には医療が必要不可欠なものとされている。
一方で「社会モデル」では、障がい者が受ける社会的不利は社会の問題だとする考え方で、障害は周囲の環境によって作り上げられるものとされている。そのため社会の環境を変えることが障害をなくすことにつながるとの考え方である。
この「医学モデル」と「社会モデル」を統合するものが「ICF(国際生活機能分類)」といえる。
つまり、障害を個人と周囲の環境の双方からとらえ、人間の状況を全体的に理解することを目指している。




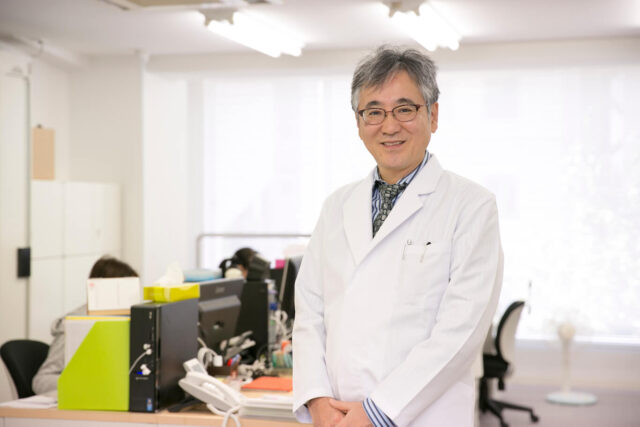













![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)



![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)



