【吉田智彦氏】医師として病気に立ち向かうことを理解させられた、ある患者との出会い
連載:大学病院とは違う立ち位置でリウマチ・膠原病治療の発信基地を目指すクリニック
2024.01.25
2006年に吉田智彦氏が開業した「世田谷リウマチ膠原病(こうげんびょう)クリニック」は、リウマチ・膠原病を専門とし、大学病院など高度医療機関と肩を並べる最先端治療を提供しています。本記事では、吉田氏に開業までの経緯について伺いました。
(記事内容は2012年取材日時点のものです)
取材協力:吉田智彦氏
世田谷リウマチ膠原病クリニック 統括院長
- 聖マリアンナ医科大学大学院卒
- 聖マリアンナ医科大学病院リウマチ膠原病アレルギー内科に入局しリウマチ膠原病の診療と難病治療研究に従事
- 日産厚生会玉川病院、児玉経堂病院リウマチ内科勤務
- 2006年:日本で初めてのリウマチ膠原病の専門施設として「世田谷リウマチ膠原病クリニック」を開設
- 2020年:新宿に「世田谷リウマチ膠原病クリニック」を移転
- 2022年:祖師谷に「世田谷リウマチ膠原病クリニック祖師谷」を開設
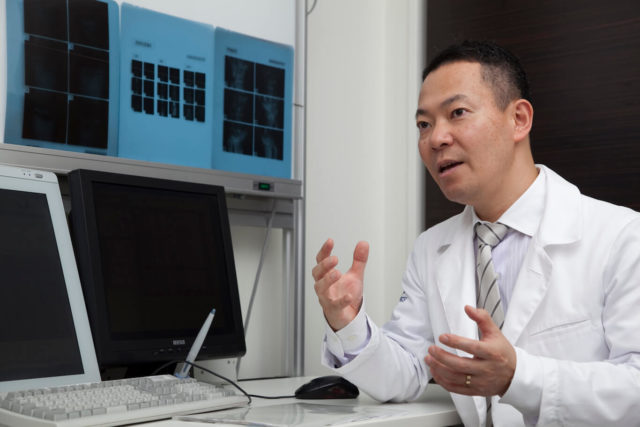
リウマチ・膠原病の専門クリニック
——2006年に開設されたのが「世田谷リウマチ膠原病クリニック」。
その名の通り、リウマチ・膠原病を専門として、大学病院などの高度医療機関と同等、もしくはそれ以上の最先端治療を提供しています。
吉田氏は、「研修医としてリウマチ・膠原病と出会いましたが、正直に言うと、最初はリウマチの診療や研究にあまり興味を持っていませんでした。」と笑いながら話し始めました。
ではなぜ、リウマチ・膠原病の専門クリニックを立ち上げ、運営するに至ったのでしょうか。
漠然と医学部に進み医師国家試験を受験
——吉田氏は、曾祖父や父親が医師という家庭に育ちましたが、大学受験までは医師という仕事をあまり意識せず、建築系を志望していました。
吉田氏:「建築学部にも行きたかったけど、聖マリアンナ医大しか合格しなかった(笑)。」
——医学部に進学しましたが、バブル期だったこともあり、サークル活動や学生での起業などに夢中になり、医師という職業について具体的なビジョンも描けないまま卒業し、医師国家試験を迎えました。
吉田氏:「思い返すと、今でも非常に反省しているのですが、当時は、自分には医師以外の可能性もあるのでは?などと漠然と考えながらも、しかし将来の目標もはっきりとしないまま医師国家試験を受けました。その頃の私は医師という職業を軽く見ていたと思います。」
ターニングポイントは二人の人との出会い

——医師としてのターニングポイントは二人の人間との出会いでした。
一人は、同クリニックで漢方内科医として勤務していた山本医師の存在です。山本氏は、大学時代からの親友でもありました。
医師国家試験には受かったものの、どの「専門」に進むか決めかねていた当時の吉田氏を、山本医師が自らも進んだ「リウマチ内科」へと誘ってくれたのです。
その後も西洋医学を軸に補完代替医療も取り入れた診療視点やクリニックの運営、ライフスタイルにおいても、山本氏から強い影響を受けてきました。
友人・山本氏の勧めでリウマチ内科に入局した吉田氏でしたが、リウマチ膠原病の診療や研究は難解で、当初は興味を持つのが難しかったそうです。
吉田氏:「今から20年くらい前のことです。ある患者様と出会ったことが、私が医師の仕事に目覚めるターニングポイントとなりました。その患者様は、研修医でしかない私を、きちんと一人前の医師、主治医として認め、接してくれたのです。しかし、その方は、皮膚筋炎に間質性肺炎を合併する難病を患っており、急激な呼吸不全に見舞われ、人工呼吸器を付けるまでになってしまいました。」
——この時、経験も知識もなかった吉田氏に対して、当時医局講師であった山田医師が治療だけでなく、患者様を診る医療の基本までも指導してくれました。
吉田氏:「残念ながら患者様は改善と増悪(ぞうあく)を繰り返し、最後には亡くなられましたが、この時に患者様の話しを丁寧に聞き、所見をとり、難病を治療するために文献を調べ、世界の最先端の治療法と現在の自分の治療の水準を合わせるというトレーニングもさせてもらうことができました。
この患者様との出会いによって、私を信頼し、身体を任せてくれる患者様に対する医師としての責任、病態を深く考える習慣、アグレッシブな治療を実践する勇気、その医療を支える仲間の存在、努力によって得られる結果など、決して諦めずに医師として病気に立ち向かう姿勢を、私なりに理解することができたのだと思います。
学生時代は、あまり真剣に勉強をしていなかったため(笑)、本気で学び、患者様と共に病気を治そうという意識を持つようになりました。同時に、この患者様との経験が、膠原病を専門にするかどうかの迷いを払拭し、その後は『誰よりも、しっかりと、患者様を救いたい』という気持ちで大学病院での医師生活を送ることができました。」
——吉田氏はこの出会いを通じて、自身の医師としての人生を「リウマチ」「膠原病」に専念する決断をしました。
(続く)



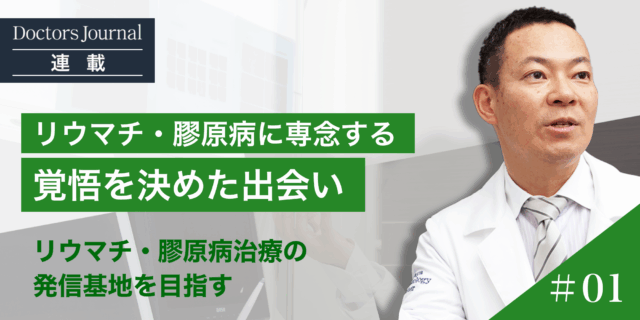


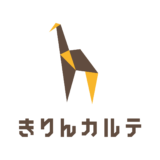














![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)



![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)




森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター