実際に臨床応用されている再生医療を知る
2023.08.26
本記事では、再生医療の中でも臨床応用が進んでいる皮膚の再生医療について、現在行われている治療法と治療に使う細胞の取得法、患者さんにかかる負担をお聞きしました。
肌の再生医療って何してる?
火傷に対する再生医療
—肌の医療においては、再生医療によってどのようなことが可能になったのでしょうか。
北條:人間が火傷した場合、まずは植皮術という方法があります。植皮術というのは健康な皮膚を火傷のところに持ってくるものです。しかしこの方法は、皮膚の半分以上が失われた場合にはできなくなります。対して皮膚の再生医療の場合は、健康な皮膚を切り取って必要な大きさまで培養・増殖してから患者さんに戻します。大体10,000倍に増やすことができますので、切手一枚ぐらいの健康な皮膚があれば体表面程の面積がカバーできるようになりました。
老化とそれに対する再生医療
—美容目的で行われる再生医療の場合、皮膚が失われているわけではないですが同様に培養した細胞を投与するのでしょうか?
北條:老化というのは一種の退行性変化・萎縮で、構成する細胞が少なくなってくるんですね。それが骨で起きれば骨粗鬆症になりますし、中枢神経も退行性変化します。皮膚の場合も同じで、厚さが薄くなってきます。そこに培養した細胞を補充するというのが美容目的の肌の再生医療です。
—再生医療では実際に細胞が若返っているのではなくて、皮膚の細胞を補充した結果、若返って見えるということですね。

若い時の細胞を利用できるのか
若い細胞をどう得るか(iPS細胞、細胞保管)
—セルバンクでは自身の皮膚から培養した細胞を利用するとのことですが、お肌の老化が気になる方の場合、理想論としては自身の若いときの細胞の方を使った方が効果があるように思います。そのような細胞を使うことは可能なのでしょうか。
北條:細胞は基本的に、iPS細胞のようにリセットすることはできるんですけれども、20歳の時の細胞を10歳の細胞にするというような途中経過に戻すことはできないんですよ。なので現実的には20歳の時に細胞をとっておいて40歳の時に注入するという方法しかないです。
—実際若い時の細胞の方が効果があるんでしょうか。
北條:これには議論があって、若いときの細胞を使った方が効果が良いというのは、予想できます。高齢であるほどタンパク質を作る能力が低いですし、増殖曲線もなだらかです。ただ、人体に移植したら効果があるかどうかという話は別なんですよ。やはり臨床実験をやって、統計学的に有意と言わないと、若い細胞が良いとは言えない。単に、想像としては良いんじゃないかという感じです。だから私は若い時の細胞の方がいいとは言いません。

—つまり患者様自身が「20代30代の時に細胞をとって保管しておいて、いずれ使いたい」と思えば、技術的には可能ということでしょうか?
北條:そうですね、可能です。我々の(提供する保管サービス)の場合は、-196℃で擬似的な絶対零度を作って保管しているので、10年20年程度のスパンでしたら細胞の劣化は医療に使うのには問題ない程度です。
—北海道から九州(福岡)まで提携クリニックがありますが、細胞を輸送するのにかかる時間による影響に対しどのような工夫をされていますか。
北條:例えば食品では、温度をかけたり負荷をかけて賞味期限を決めるじゃないですか。細胞も同じような感じで、こういう温度、こういう方法で輸送すると72時間後にどういうクオリティを示すかというデータをとります。バリデーションと呼ばれるこの試験によって、治療として使うことのできる範囲で品質を保っています。
患者さんの負担
—幹細胞治療を受けるにあたって患者さんにかかってくる負担にはどのようなものがあるのでしょうか?
北條:金銭的な負担はとても大きいですよね。金額が高くなる原因は主に二つで、一つは設備費、もう一つは人件費です。これは、機械などで自動化できないので全て手作業でやっていることが影響しています。
続く



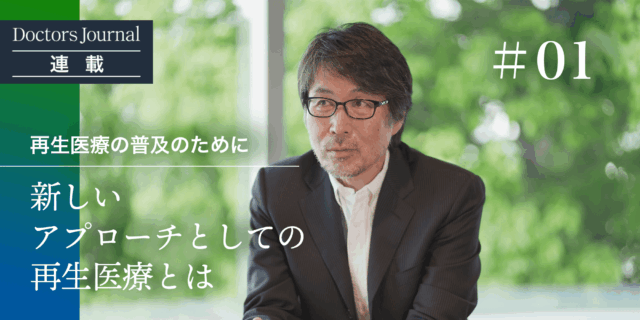
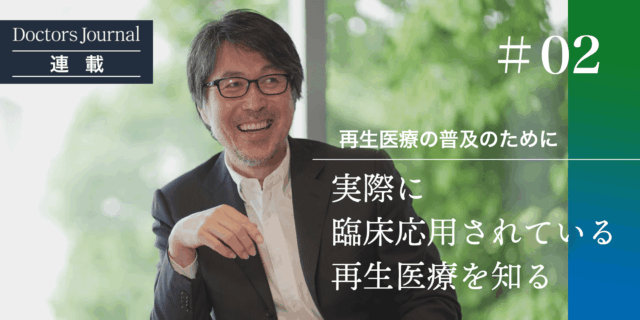



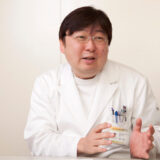





























専門家のコメント
ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター 2023年09月13日
現役東大生プロジェクトへのご協力、ありがとうございました。
メリットだけでなく、デメリットや他の選択肢も見据えながら、患者様目線で、語られている北條元治先生。
自分に対しても、相手に対してもフェアである、まさに紳士。
患者様にとって、医療関係者にとって、心強い存在です。
「日本の再生医療のデファクトスタンダードを構築する」というビジョン。応援しております!!