#03 主治医であれば患者さんの全てに寄り添える。それが開業した理由です。
連載:ホスピスケアをムーブメントと捉え、 患者の権利が基本の在宅ホスピスケアに取り組む
2021.03.01
麻酔科医は疼痛緩和以外では立ち入れない
病院で、他科の医師から依頼されるのは、麻酔科医として患者さんの痛みだけを取って欲しいということで、それ以外のことは拒絶されました。患者さんには手も口も出さない。ということです。
しかし、薬だけで治せる身体的な痛みとは実は少ないのです。心の問題が大きいのです。医師が患者さんの心の問題にも関わっていかないと、患者さんは痛みにも立ち向かえないのです。
当時一番大きな問題が、がんの告知をタブーとされていたことでした。悔しいことに麻酔医は、苦しんでいる末期のがん患者さんや家族を見ていても、疼痛緩和以外では立ち入れないのです。
夫が末期がんの奥さんを襲った後悔と悲劇
ある時、入院している患者さんの妻が、私のところに泣きながら飛び込んできました。彼女の夫は末期の肝臓がんで、私が痛みの治療で関わっていた患者さんでした。
その夫が大分弱ってきた中で、奥さんに手紙をくれたそうです。そこには最期を悟って奥さんへの今までの感謝の言葉がつづられていたそうです。しかし奥さんは、その手紙を読むなり「バカなことを言わないで!」と、くしゃくしゃにしてごみ箱に捨てたそうです。
それ以来、夫は心を完全に閉ざしてしまい、医師にも看護師にも、彼女にも一言も口を利かないで、暗い表情でそのまま10日余りで亡くなってしまったのです。
何故そんなことをしたのかと聞くと、担当医から、本人にがんだと気づかせるようなことは絶対に言ってはならないと繰り返し口止めされていたからと、私の前で号泣するのです。
「私こそありがとう。長いことお疲れさまでした。」と、ひとこと言ってあげられていれば、どれほど良かったでしょうか。
奥さんは大きな後悔を残して、精神的に立ち直れない状況でした。そんな悲劇が起きてしまったのです。

主治医として患者さんに関わりたい
そんな経験をして、苦しんでいる患者さんの、ただ痛みだけをとる技術者ではなく、主治医として患者さんに関わりたいと強く思いました。開業すれば自分が主治医として、患者さんの全てに寄り添えます。それが開業した理由です。
まだ勤務医だった1988年に、県民に広くホスピスを知ってもらおうということで、群馬ホスピスケア研究会を立ち上げました。最初は、ある会合で出会った看護師と二人からのスタートでしたが、その後、予想以上の人が集まって、現在でも続いています。
1991年に在宅医療と痛みの緩和のための「ペインクリニック小笠原医院」を群馬県高崎市で開業し、ホスピスケアを標榜しました。その後の2008年に「緩和ケア診療所・いっぽ」と名称変更し、地域緩和ケアの専門診療所として現在に至っています。









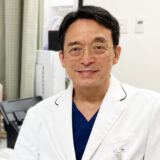


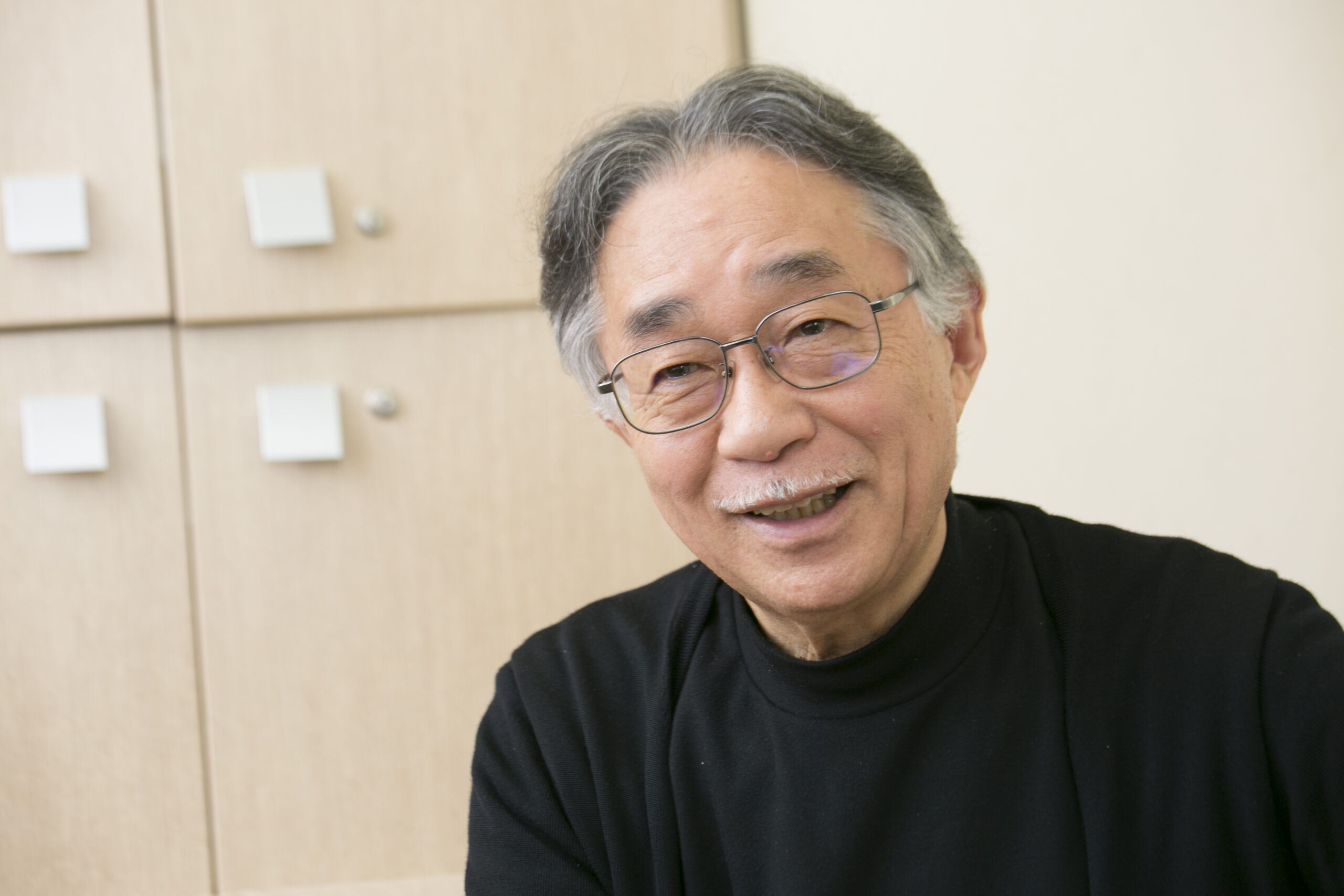





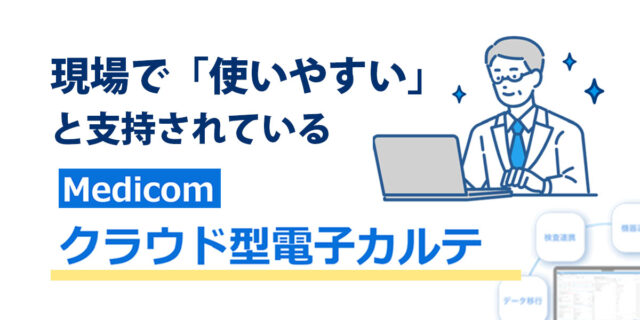






















![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

