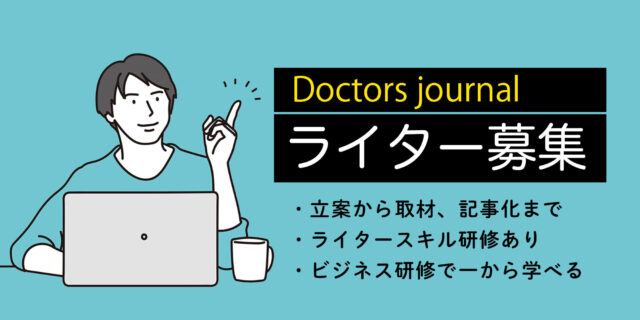#01 認知症の人を「人」として見ることのない文化の問題点
2021.08.19
司会: 平成24年6月18日に厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチームより「今後の認知症施策の方向性について」が発表されました。
また同年9月5日には平成25年度から29年度までの具体的な計画として「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」が発表されました。
ここには従来の認知症施策の反省を踏まえて、これからの日本における認知症診療のあり方を大きく変える指針が提示されました。
その中では特に地域における認知症ケアのあり方として、医療従事者に限らず本人、家族、地域も巻き込んだ取り組みが提示されています。
本座談会では、1回目で「パーソンセンタードケア」と「地域における連携ケアの重要性」について語っていただきました。
それを踏まえて、今回は特に地域のかかりつけ医が担うこれからの認知症医療について語って頂きます。
まずは認知症について考えるときにベースとなるべき「パーソンセンタードケア」についてから振り返りたいと思います。(以下敬称略)
座談会出席者
木之下徹氏(医療法人社団 こだま会 こだまクリニック院長)
本多智子氏(医療法人社団 こだま会 こだまクリニック看護師)
勝又浜子氏(厚生労働省老健局高齢者支援課 認知症・虐待防止対策推進室長)
加畑裕美子氏(「レビ-小体型認知症介護家族おしゃべり会」代表)
中野あゆみ氏(有限会社DOOD LIFE(高齢者住宅・訪問介護)代表 社会福祉士)
ファシリテーター
元永拓郎氏(帝京大学大学院文学研究科臨床心理学専攻・准教授)
司会
絹川康夫(一般社団法人 全国医業経営支援協会 代表理事)
※平成24年7月31日に開催。出席者の所属、役職は当時のものです。
(『ドクタージャーナル Vol.6』より 取材・構成:絹川康夫、写真:安田知樹、デザイン:坂本諒)
できる限り住み慣れた地域で暮らし続ける事
木之下: 日本は高齢化率が世界で一番高い。そしてそれが100年ほど続く。そのせいで認知症の人々は爆発的に増えることが予測できます。
たしかに我々の周囲には認知症の人々が多い、と感じるのは、いまや常識となっています。
私自身も近いうちに認知症なるのでは、と考えるのもいまや自然でしょう。そういった意味で、認知症は他人事ではなく自分事であるともいえます。
「認知症の人を人として見たらどうなのか」という視点が欠け落ちている現場に、違和感や衝突が生じるのは、「人」として当たり前です。しかし残念ながら、そういった状況があちらこちらで散見されれば、それは認知症の人を「人」として見ることのない文化であるということも指摘できます。
一方、今回の厚生労働省の発表は、まずは認知症の人は「人」である、といった気づきを得る大きなきっかけになると思います。
認知症の人には生活のしづらさがある。認知症の人が、そしてその人に繋がる人々が、共に「人」としての暮らしを作っていくためには、それにふさわしい文化や思想が必要です。
今回の厚生労働省発表のコンセプトは、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることをアウトカムにしています。
この意識の流れは、認知症の人も「人」であることを当たり前とするパーソンセンタードケア(「人」中心のケア)の視点と同じ気がします。

元永: 人の価値観とか考え方を軸に、人の暮らしを大事にしてゆくケアのあり方がパーソンセンタードケアと言えます。
パーソンセンタードケアという考え方を提唱したイギリス人のトムキットウッド氏は、認知症の人のケアにおいて、非常に多くのよろしくない働きかけを悪性の社会心理(MSP, Malignant Social Psychology)として17の事象にまとめ、それが認知症の人の存在を脅かして、更に悪い状態に追い込んでゆくことを実証しました。
それに対して認知症の人にプラスとなる3連構造のやりとり (Action, Reaction, Reflection )を、「人」を中心にした相互作用を整理して、ポジティブパーソンワーク(PPW, Positive Person Work)としました。そのような人間関係があれば認知症になっても希望をもって生きてゆけるということです。
木之下: 認知症の人も「人」であるといった文化を目指せば、この気づきが促され、気づきがあれば、指摘されたMSPは今よりは減っていくでしょう。今回の、人々に気づきを与えるような理念型の施策は、とても大切だと思います。
認知症への取り組みが切り拓く明日の日本
勝又: 今、最も実感しているのは、認知症医療は現場で接していなければ分からないことがあるということです。現在、看護職員の中でも、継続的に認知症の人々と関係している人はそれほど多くありません。同じように医師もそれほどいないと思われます。
これからますます増えてくる認知症の人たちの医療を、今後、継続的にどうしていかなければならないかということが重要なテーマだと考えます。
木之下: 今の医療では認知症は治せない。薬で少し進行を遅らせることができるようになっただけです。根本治療薬はありません。
予防できるエビデンスもありません。たとえあったとしても、今の病勢に対して焼け石に水でしょう。寄り掛かるにはあまりに頼りない。
だとすれば「認知症になっても人として生きてゆく希望は失われない」という状況に変えるしかない。
そういった形で、これからの認知症の医療モデルを考えるしかない。この新たなモデルは魅力的です。
なぜなら、生活習慣病など他の状況にも、生きづらさを感じる様々な局面において、同じことが言えることに気づけるからです。
認知症が新しい時代を切り拓く上で重要な素材になると考える理由はここにあります。
本多: 私は認知症の在宅ケアに十数年携わってきました。その関わりの中で、医療面よりもむしろ、生活の中で困っている事柄に関係する相談が次第に増えていきました。
そのうち、それらの気づきと医療とケアを上手く繋げない限り、受診者のためにならないと考えるようになりました。気づきを与え医療とケアと福祉を近づけ繋げるためのものが、「人」として考えるといったパーソンセンタードケアの考え方であると思い始めています。
木之下: 認知症のテーマ性とは、限られた誰かが語るのではなく、いまや全員が問題意識を持たざるを得ないということです。何故ならば誰もが認知症になる可能性があるからです。
パーソンセンタードケアのパーソンとは、認知症の人のパーソンであり、これから認知症になるかもしれない私たちもパーソンでもあり、ケアする人もパーソンでもあるという、全ての人を指し、そしてみな平等な価値、そして誰もが侵犯できない絶対的な価値を有していると考え、そういった「人」という視点を導入したケアであることを意味しています。
勝又: パーソンセンタードケアは認知症のケアの基本になり、認知症のケアだけでなくて全ての人に対する医療にも言えることですね。それは病気で無い人にも、普通の人間関係にも言えることだと思います。
木之下: その通りだと思います。「パーソン」は「人」です。認知症の人はもちろん、ケアする人も人である。人を考える。人として関わっていく。我々も人として生きていく。そういうことをパーソンセンタードケアのコンセプトは与えています。
認知症になっても希望を持って生きていける文化になっていくことを望みます。いま認知症である人にとっても大切ですが、これから認知症になる自分のためにでもあるからです。