#01【新田國夫氏】在宅医療を求めている患者さんの多くが、高齢者と認知症の人だということに気づく
連載:高齢者と認知症の在宅診療で取り組む地域住民のための医療
2021.05.13

新田クリニック院長。一般社団法人 全国在宅療養支援診療所連絡会会長。日本臨床倫理学会理事長。
1944年岐阜県生まれ。1967年早稲田大学第一商学部卒業。1979年帝京大学医学部卒業、帝京大学医学部第一外科・救命救急センター勤務。1990年医療法人社団つくし会新田クリニック設立。主な著書/『生き方、逝き方ガイドブック 最期の暮らしと看取りを考える』(朝日福祉ガイドブック)2015年、『安心して自宅で死ぬための5つの準備』(主婦の友社)2012年、他
― 新田先生は4半世紀以上に及び在宅医療に取り組まれています。当時としてはまだ珍しかったと思われますが、そのきっかけとは何だったのでしょうか。 ―
今から30年ほど前になりますが、再発して入院していた末期がんの患者さんを訪問診療で看取ったことが、外科医の私が在宅医療に取り組むようになったきっかけでした。
当時の病院では、患者さんのがんが再発すると治療病棟ではなく個室で点滴を行っていました。モルヒネの点滴や筋注などしかない時代でしたから、患者さんには過剰な負荷をかけるために非常に苦しまれるわけです。在宅では、末期がんの患者さんを最後まで十分に看取ることはできませんでした。
そのような末期がんの患者さんの中で、自宅で最期を迎えたいと希望される方がいました。たとえ快復の見込みのないとしても、その人なりに人間としての尊厳を保ち、希望する自宅での看取りができないかと考えました。
当時は在宅医療という発想も全くない時代でしたが、自宅が病院の近くということもあって病院の外来看護師に協力してもらい、その患者さんを自宅で最期まで看取ったのです。
当時は、在宅で終末期の患者さんを診療することはありませんでしたし、訪問看護師もいない時代ですから、全てが手探り状態の中での診療でした。日常の介護は家族にお願いし、緊急時には病院が対応するようにしましたが、それが思っていた以上に上手くいったのです。
そこで感じたのが、「これからの地域医療では在宅医療が求められ、社会にとっても必要とされていくのではないだろうか」ということでした。
それまで私は、勤務している中規模病院で行っている医療が地域医療だと思っていました。しかし、「本当の地域医療とはもっと地に根の張ったものではないか」と考えるようになり、診療所も経験しましたが、そこも私が考える地域医療とは違っていました。そのような経緯から、自分が考える地域医療の実現のために開業に至ったわけです。
私が国立市に新田クリニックを開設したのは、1990年、46歳の時です。国立市での開業は、都心部ではなくて、人口が10万人以下で尚且つ住民の顔の見える地域という条件で探した結果です。それまで国立市のことは全く知りませんでした。
また現在の場所での開業に際しては、診療圏調査や、地域の在宅医療ニーズの調査もせず、自宅から20分以内を条件で決めました。コンサルタントからは、駅から遠く周辺環境を考えても、新規開業でこれほど不適切な場所は無いとまで言われました。それでも地域に根差した在宅医療の実現の思いのほうが強かったので、余り気になりませんでした。

在宅医療を求めている患者さんの多くが、高齢者と認知症の人だということに気づく
当初の在宅医療の目標は「病院と同じような医療を患者さんの自宅で提供したい」ということにあったように思います。当然、在宅医療といっても病院医療の延長線上にありましたので、当院でも病院と同じように患者さんにモニタリングを付けていました。
ところが外部の優秀な訪問看護ステーションにサポートを委託した折りに、そこの看護師から「患者さんにとっては邪魔なだけで、そのようモニターなどは全て必要ありませんよ。」という指摘を受けました。せっかく在宅診療用に用意した心電図モニターは撤収、そのまま倉庫に入ってしまいました。(笑)今でも使っていません。
開業当時は、社会的入院の是正のために「病院から在宅へ」という流れが起こり始めていた初期段階でしたので、無理矢理退院させられる患者さんも多くいました。
もともと外科医として、末期がんの患者さんの治療に当たっていましたが、彼らを地域で支えられるようにとのことで、外来と並行して訪問診療を手掛けはじめたのです。
ところが、そのようなカテーテルやいろいろな装具を付けられて退院する患者さんは、がんよりも高齢者の方が多かったのです。在宅医療を求めている患者さんの多くは高齢者なのだ、ということに気付きました。そこで、がんの患者さんだけでなく高齢者の在宅医療にも積極的に取り組むようになったわけです。
また当時としては、高齢者の在宅診療を行っている診療所は他にありませんでしたから、保健センターから来る高齢者の在宅診療の要請にも全て対応していました。ですから、難病やがん患者さんから高齢者までを全て診ていました。
さらには、在宅診療の現場ではなんと認知症の方が多いか、ということに驚きました。当時は認知症が「痴呆症」と言われていた時代です。私自身も外科医ということもあって、認知症に関しては十分な認識があったわけではありませんでした。
訪問診療に行くと、認知症の方が家の奥に閉じ込められたり、薬漬けになっていたりする。大量の薬の処方が当たり前に行われていた時代です。
宅老所を開設して「認知症のケアとはこういうものなのか」と気づく
ある宅老所を視察した時に、そこで暮らしている方々がとても和やかで良い顔をしていることに気が付きました。その宅老所は、それまでの施設ケアとは一線を隔す施設でした。日本でも北欧型の医療や介護にも注目が集まりはじめていました頃です。
そこで、1997年に国立市内で古い借家を改造して、私と主婦6人のスタッフで高齢者と認知症の方を対象とした宅老所“つくしの家”を開設しました。
朝来て、皆で食事を作り、昼間は自分のペースで「ごく普通の生活」を過ごし、夜は帰る。認知症の高齢者を自宅に閉じ込めるのではなく、この“つくしの家”で思い思いに過ごしてもらう。時には泊りも可能で、デイサービスとショートステイを併せた、今でいうグループホームの原型のようなもので、小規模多機能型居宅介護に当たるでしょう。
今のような専門のケアスタッフもいない時代で、介護保険も無かった時代ですから十分な報酬も払えませんでしたが、それまでの施設ケアの在り方に満足していなかったスタッフが集まってくれ、献身的に“つくしの家”の運営に尽くしてくれました。
そこでは多くの発見がありました。それまで在宅で薬中心に診ていた認知症の方が“つくしの家”に来ると状態が良くなるのです。中には薬を使わなくても済むようになった人が出てきた。「認知症のケアとはこういうものなのか」と、純粋な驚きと気づきがありました。
認知症のケアとは、薬に頼るのでは無く本人の生活を中心に置いたものなのだ。ということを、そこで働くケアスタッフから学びました。
それが後のグループホームとなり、さらには通所リハビリテーション、認知症グループホーム、介護付き有料老人ホームの開設へと続き、今は国立市からも専門の特
定施設としての認定を受けています。
国立市で、医師会立の訪問看護ステーションを立ち上げる
1990年代のことですが、私が国立市医師会の理事の時に、医師会立の訪問看護ステーションを立ち上げました。まだ東京都においても訪問看護ステーションが非常に少ない時代でしたし、医師会の中でも十分な理解があったわけではありませんでした。
理由は、当院で訪問看護ステーションを行うのではなく、それぞれの機能を有する医師会の医療機関同士で連携することが重要だと思ったからです。当時は、在宅医療も認知症も社会全体の認識は全く乏しく、まだこれといった動きも無かった時代でした。
今の在宅医療とは「治し支える」ことです
在宅の取り組みだした最初の頃の私には、在宅医療も病院医療も医療に変わりはない。在宅医療は病院と同質であるべきとの思いがありました。ですから、在宅で気管挿管も骨折治療も行い、時には虫垂炎の手術も行いました。若かったということもあり、所謂、在宅原理主義者になるわけです。
その後反動で、看護だけで他には一切何もしないという在宅医療にも取り組みました。ちょうどホスピス源流など多様な考え方が日本に入って来た頃で、それこそいろいろな在宅医療の在り方を試行錯誤しました。それらの取り組みを経て、私にとっては今が第4段階の在宅医療といえます。
何もしない在宅医療はないと思っています。患者さんに何かすることで苦痛を与えるから何もしないという誤ったホスピス系の考え方もありますが、何もしない在宅医療はない。今は「治し支える」在宅医療です。
在宅で治せる医療はしっかりと行う。認知症のBPSD、リハビリ、心不全などは、病院よりも在宅医療のほうが有効だというエビデンスもあります。在宅を行う医師はこれらのことを知らなければならない。
現状における在宅医療の問題点とは、各々の医師が個々の経験や判断によって独善的に行われているために、全体としては通用しない。そのような状況になっているということです。
個々の医師の知識、技量や考え方次第で患者に対する在宅医療の在り方が変わる?
現状はそのように感じられます。在宅医療に取り組んでいる若い医師達を見ていると、皆さんそれぞれに地域において実績もあり信頼されている方々ですが、個々の見識やレベルで在宅医療を捉えているように見えます。間違っているということではなくて、個々の医師によって在宅医療が変わってしまうのはいけないと思うのです。
病院における治療内容はほとんど決まっていますから、日本中どこでも同じ内容の医療を受けることができます。同じように在宅医療でも、求められる必要なことは日本中どこでも受けることができる。
いろいろな在宅医療の選択肢を医師個人の判断ではなくシステムとして決めていけるようになる。現在はそのようなステージに入ってきていると思います。過去から現在に至る在宅医療の歴史の中で、今は一つの転換期だと思います。




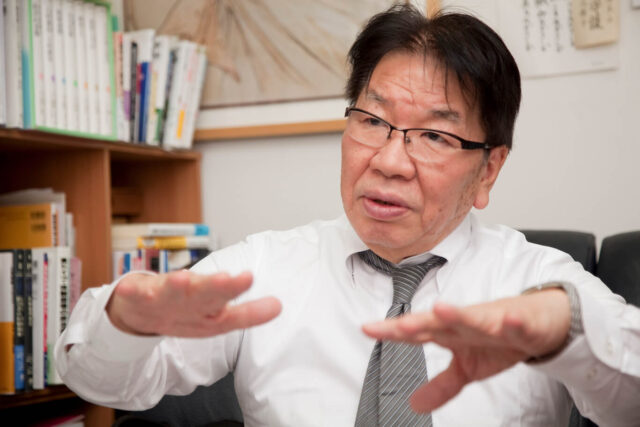



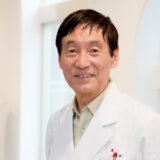










![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)



![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)






