クリニックM&Aのウソ・ホント①
2022.03.14
事業承継と聞くと、引退を迫られているようで前向きになれなかったり、何から着手すればよいのか分からなかったりで悩みや不安を抱えている方も多いと思います。本連載では「今日からはじめる事業承継」と題して、院長が抱える事業承継への不安を1つでも解消し、笑顔で事業承継を終えるために役立つ記事を発信していきます。
後継者不在の問題を解決する手法として、クリニックでもM&Aが注目されています。読者の皆様もメリットが意外に多そうだな!悪い選択じゃなさそうだ!とM&Aに対する印象が変わってきた方も多いのではないでしょうか。
ただ、某ドラマでは派手な演出でM&Aが敵対企業を買収するための方法として書かれることも少なくなく、「身売り」や「乗っ取り」というイメージを持つ方も多いと思います。本記事では定期的に理事長や院長からよく聞かれる質問をまとめ、「クリニックM&Aのウソ・ホント」と題してお伝えいたします。
クリニックのM&Aは「乗っ取り」⇒ウソ

M&Aという言葉を聞くと反射的に「身売り」「乗っ取り」を連想する方も多いのではないでしょうか。その昔、医療業界において病院を乗っ取り経営権を握って余分な検査や治療、診療報酬請求権の売買などにより利益を得ていた方々もいたのは恐らく事実でしょう。
経営コンサルタントを名乗りながら、経営に行き詰まっている病院に接近するブローカーと呼ばれる人もたくさんいたと聞いています。
ただ、私たちがお手伝いをしているM&Aはあくまで中立の立場であり、お相手は相談者自身が選ぶことができます。あるいは交渉の途中であってもM&Aをしないということも可能です。
「後継者へ継ぐことができない」「誰かに患者の治療を続けて欲しい」「職員の雇用と生活を守りたい」「建て替えて良い療養環境を作って欲しい」など、何かしら課題や希望を1つのボタンで解決できる、それがM&Aという選択肢なのです。
子供が継ぐからうちは大丈夫!⇒ウソ

日本医師会総合政策研究機構が2019年に公表した文献「医業承継の現状と課題」によれば、「後継者が決まっていない」と回答した割合は全体の約9割という回答結果が出ました。親の事業を継ぐのが当たり前だった昔とは異なり、今や「子供が親のクリニックを継ぐほうが珍しい時代」になりつつあります。
私がこれまで遭遇した事例では、「お父さんが精神科医で娘が皮膚科医、精神科クリニックの引継ぎはやはりハードルが高い」、「子供が急性期病院の外科で勤務しており経営には興味が全くなさそうだ」、「医学部入学から東京へ出てそのまま結婚、子供もできたし今さら田舎に帰ってこないだろう」というように子供から承継を断られてしまったという相談も年々増えてきています。
このような時代だからこそ、親族承継したいと思う方々はコラム#2〜4に書いた準備をして早めに家族会議を、継がないのであればコラム#5〜7に書いたように第三者承継の心構えをしておきましょう。
▼子供や従業員へ継いでもらう方法
#2 理事長と後継者の悩み編
#3 継いでもらうために必要な準備編①
#4 継いでもらうために必要な準備編②
▼第三者へ継いでもらう方法
#5 M&Aを検討するメリット編
#6 M&Aを成功させるポイント編
#7 M&Aで『後継者不在』の問題を解決した事例編
M&Aをしても法人名・施設名はそのまま?⇒ホント

M&Aをした際に「法人名や施設名が無くなる、変わってしまうのか?」というご質問は多いです。結論、法人名や施設名は多くの場合変わらずにそのままとするケースが多いです。
何十年もの歴史がありその地域で認知されている法人名・病院名を変えてしまうと集患にも影響するためといえばわかりやすいと思います。もちろんM&Aをした後は、法人名も施設名もすぐに変えて欲しいという要望があれば、そのようにお相手と交渉を進めることも可能です。
赤字だとM&Aができない?⇒ウソ
赤字でもM&Aはできますか?という質問も時々受けることがあります。結論、決算書で赤字であってもきちんと調べれば実態は黒字であるというケースが多々あり、一度しっかりと分析をすることをお勧めしています。
例えば、理事長が役員報酬で5000万円貰い、決算書上は1000万円の赤字となっているというようなケース。役員報酬を一般的な医師の年収2000万円と置き換えれば、3000万円のおつりがでるため、赤字は消え実態は2000万円の黒字を生み出しているクリニックとなります。
このように細かい分析をすることでクリニックが持つ本当の収益力を見ることができます。その上で決算書では見えないクリニックの魅力(立地や来院数、優秀な人材、設備など)をきちんとまとめることで、お相手が見つかりそうか否か1つの判断軸が見えてきます。そのため赤字だからと諦めず、まずは専門家の分析を依頼して実態を把握することが大切です。
まとめ
今日からはじめる事業承継8日目は、理事長や院長からよく聞かれる質問をまとめました。
上場企業のように公表する義務がないため、クリニックのM&Aは未知なる部分も多いです。M&Aを経験したことがある人などいませんので不安や心配があって当然だと思います。大切なことは、それらをそのままにせずに納得のいくまで情報収集をすること。いま悩まれている読者の皆様と同じような悩みを抱え解決してきた事例を私たちfundbookはたくさん持っています。是非お気軽に「M&Aってどうなんだ」と聞いてみて頂ければ幸いです。
株式会社fundbookの基本情報
| 会社名 | 株式会社fundbook |
| ホームページ | https://fundbook.co.jp/ |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24F |
| TEL | 03-3591-5066 |
| 事業内容 | M&A仲介事業 |
fundbookは最先端のテクノロジーとアドバイザーの豊富な経験を融合した新しい形のM&Aを提供する会社です。2021年に創設された「ヘルスケアビジネス本部」には、病院・診療所の事業承継・M&Aを200件以上成約に導いてきたメンバーが揃い、業界最大級の経験と実績に基に安心と成果を提供します。M&Aに関するコラムやM&A事例なども多数紹介しています。


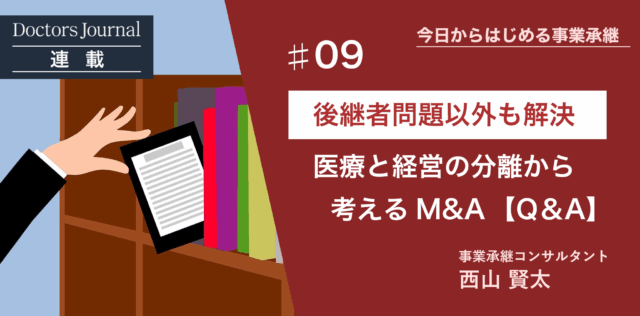
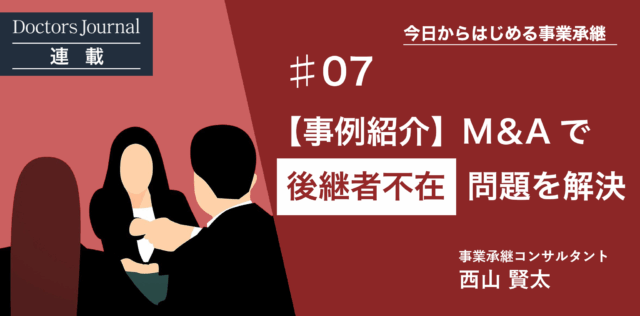
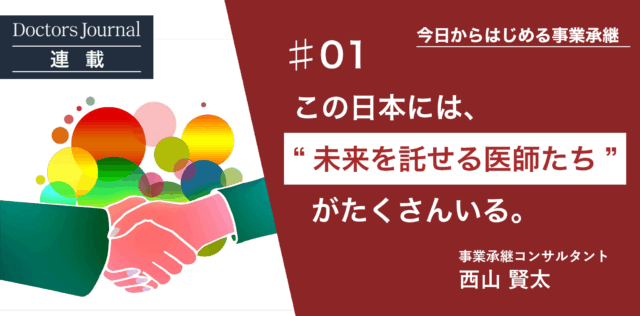
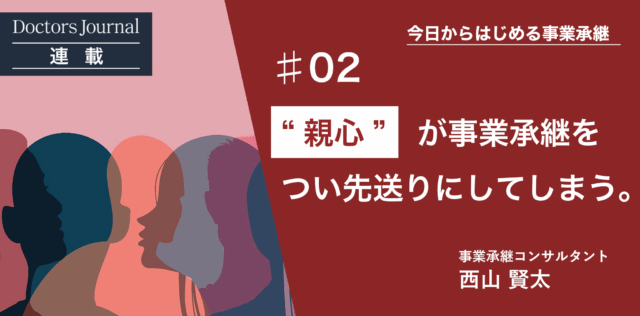
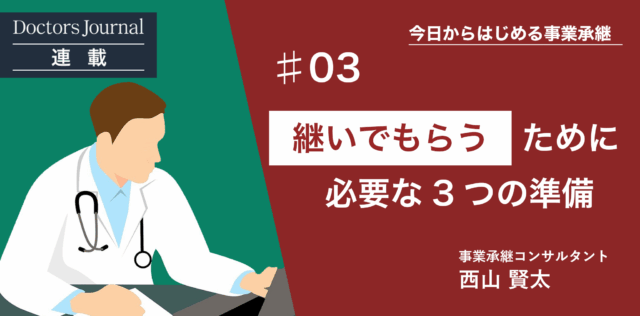
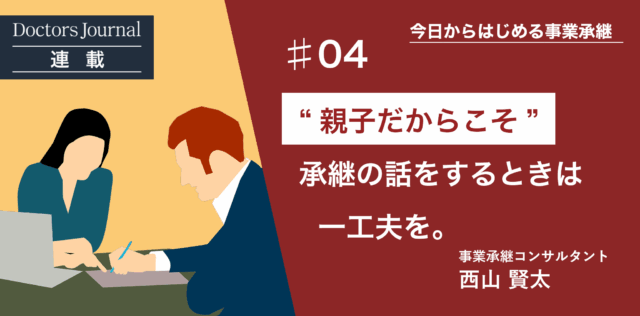
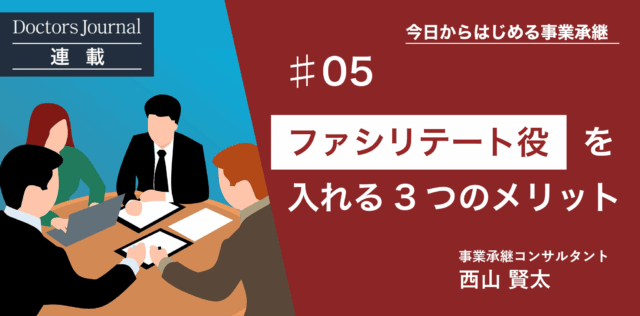
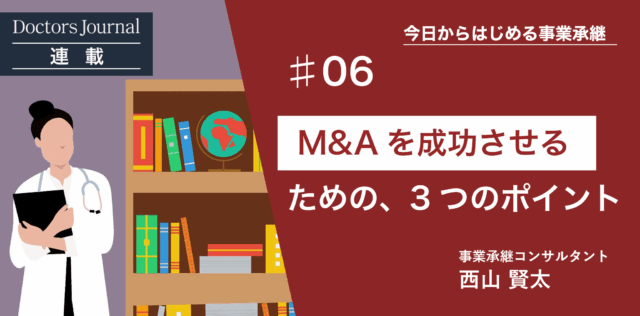
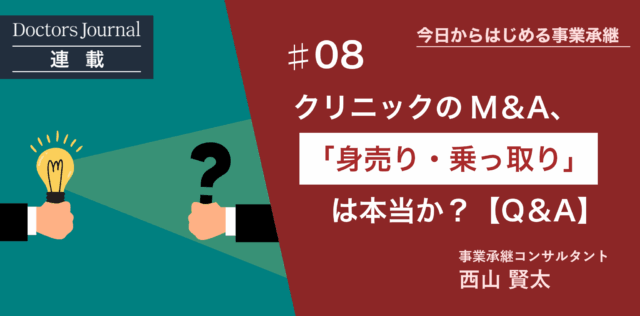





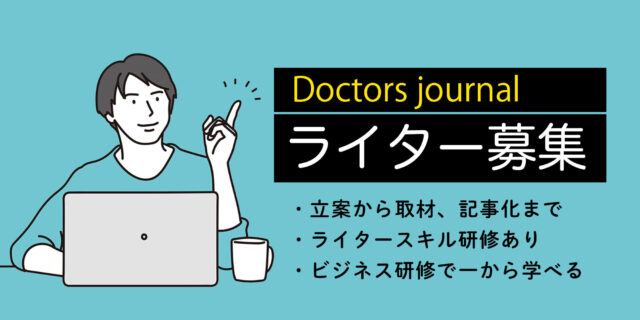


























森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター