電子カルテを使いこなすには?正しい使い方で得られるメリット
2022.02.08
全国の大規模な病院を中心に導入が進んでいる電子カルテ。一方で、中・小規模の病院やクリニックからは費用面の懸念や、本当に使いこなせるかという不安の声もあります。
今回は電子カルテを取り巻く現状やその特徴についてご紹介するので、導入を検討中の方はぜひ参考にしてください。
本当に便利?電子カルテの普及率

電子カルテとは、従来医師が紙に記録していたカルテを、パソコンやタブレットで編集・管理できる電子データに置き換えたものやそのシステムのことです。
厚生労働省の医療施設調査によると、平成29年時点の一般病院における電子カルテシステムの普及率は46.7%であり、クリニック(一般診療所)における普及率は41.6%です。9年前の平成20年の普及率はいずれも14.5%程度であり、比較すると数十%増加しています。
一方で、平成29年時点での病床に基づいた規模別の内訳を見ると、400床以上の一般病院での導入率が85.4%、200床以上400床未満では64.9%、200床未満では37.0%と、小規模な病院で電子カルテシステムの普及率が低い傾向にあります。
また、病院の規模が小さくなるにつれ、今後も電子カルテを導入する予定がないと答える割合が大きくなる傾向が見られました。現状の導入状況、今後の導入予定ともに、小規模の病院・クリニックほど電子カルテの導入が進んでいないと言えます。
電子カルテが普及しない理由

全体として電子カルテの導入率は向上しているものの、小規模の病院やクリニックにおける普及率は依然として低い状況です。小規模の病院・クリニックに電子カルテが普及しない主な理由は以下の3つです。
①コスト、費用対効果の問題
電子カルテが登場し始めたばかりの頃、電子カルテの導入費用は今よりもずっと高額でした。そもそも病院としてコンピュータを導入する必要があったり、システム開発に莫大なコストがかかったりしていたためです。当時は病院やクリニックごとにシステムをカスタマイズして開発していました。
電子カルテの使用が認められてから20年余り。以前に比べれば安くなりましたが、サーバーや関連設備を設置すると初期費用は一定額必要です。現在の相場は300~500万円といわれています。しかも、数年ごとに買い替えや更新もしなければいけません。これでは電子カルテの導入をためらうのも無理はないでしょう。
ところが、最近になってサーバー設置が必須のオンプレミス型とは異なるクラウド型電子カルテが登場しました。クラウド型はデータをインターネット上で管理できるので、コストは非常に低いです。初期費用がかからないものすら存在し、クリニックは月額費用の2~5万円を支払うというものが一般的になっています。クラウド型の認知度が上がれば、電子カルテの普及率は今よりもっと高まるでしょう。
②ITリテラシーの問題

個人経営の小さなクリニックは院長やスタッフの高齢化が進んでいるため、IT化が遅れています。電子カルテの操作方法を覚えるより、紙のカルテを使用し続けた方がかえって効率が良い場合もあるでしょう。電子カルテを導入しても上手く使いこなせなければ意味がありません。
また、導入にあたりカルテの電子化を行うスタッフが必要になることもあります。人材が豊富な大規模病院とは異なり、小規模の場合はITリテラシーの高いスタッフを雇用、あるいは教育することが難しいといった事情もあり、導入がなかなか進んでいません。
③必要性を感じられない
開業年数が長いクリニックから「紙のカルテの方が慣れていて便利だから、電子カルテは必要ない」という声をよく聞きます。紙のカルテの使用期間が長く、それが当たり前になっているのであれば、コストをかけてまで慣れない電子カルテを導入したくないと抵抗を感じるのは当然のことです。
とはいえ、電子カルテを不便に感じるのは最初のうちだけ。一般的なパソコン技能があればすぐに慣れますし、慣れた後は電子カルテの方がずっと便利なことに気づくはずです。
電子カルテがもたらすメリット3選

実際のところ、電子カルテを導入することによって、クリニック経営はどう変わるのでしょうか。電子カルテが持つメリットについて、代表的なものを3つご紹介します。
①カルテをどこでも参照できる
電子カルテで編集を行うとデータは瞬時に反映され、クリニック内の他の端末からも編集後のデータをすぐ参照できます。複数人で閲覧する時でも、紙をコピーする必要はありません。同時に同じカルテを閲覧できます。
また、クラウド型の電子カルテの場合、院外でも自由にカルテを参照・編集できます。場所の制限を受けることなく、端末一つで膨大なデータを持ち運びできるわけです。特に在宅医療を行っているクリニックにとっては、非常に利便性が高いツールと言えます。
加えて、地震や洪水などの災害が起こった時にカルテがなくなってしまうという心配もありません。電子カルテのデータを保存しているデータセンターは安全性の高い場所にあるため、クリニックが被災したとしてもインターネットに接続さえできればカルテを参照することができます。
②業務効率の改善・誤読の減少
クリニックに電子カルテを導入した場合、予約、診察、会計といった場面において、物理的に紙のカルテを持ち出し参照する必要がなく、受け渡しにかかる時間を削減できます。また、パソコンでの入力によりカルテ作成にかかる負担の軽減も可能です。
さらに、パソコンでの入力となれば、手書きの文字が悪筆で読めないということもなくなります。誰もが瞬時に分かりやすく情報を共有できるのは大きなメリットでしょう。
電子カルテの操作に慣れるまでは紙の方が速く記録できるかもしれません。しかし、初期であっても全体の生産性を考えれば、記録スピードが落ちてもなお業務効率化が期待できます。
③省スペース
紙のカルテだと、患者さんの人数に応じたカルテ保管場所が必要です。一方電子カルテを導入すれば、サーバーにデータが保存されるため省スペース化できるだけでなく、クラウド型の電子カルテにいたっては、サーバーのためのスペースすら必要ありません。
また、サービスによっては、既に保管している紙のカルテを電子データ化するものもあり、移行の手間も抑えることができます。
電子カルテを使いこなすには

電子カルテが持つさまざまなメリットを最大限活かせるよう、各メーカーの電子カルテには多様な工夫が凝らされています。たとえば以下のようなものです。
直感的に操作できるレイアウト
電子カルテの画面は、医師や看護師が使いやすいように設計されています。種類によっては、診療の種類等に応じてレイアウトを変更できるものもあるので、自院に合わせたカスタマイズをしましょう。より直感的に操作できるレイアウトの電子カルテを選ぶことで、さらなる業務効率化が見込めます。
検索機能
電子カルテでは、過去の診察データを瞬時に検索することができます。一人の患者さんのデータに限らず、これまで蓄積してきたデータの中から探せるので、今まで以上に正確な診察・診断が可能です。誤診の予防にもなるので、患者さんとの信頼関係を築きやすくなります。
電子カルテの導入メリットは使い方次第

今回は電子カルテの機能や導入に対する懸念点とメリットについてご紹介しました。クリニックで電子カルテを導入する際には、自院の状況や医師のリテラシーに合わせた検討が重要です。一度導入したら長く使うものなので、どの電子カルテを選ぶのかは慎重に決めましょう。
電子カルテについての知識をさらに深めたい方は、ぜひ下記リンク先もご覧ください。電子カルテの主要メーカーがそれぞれの立場から電子カルテについてご紹介しています。


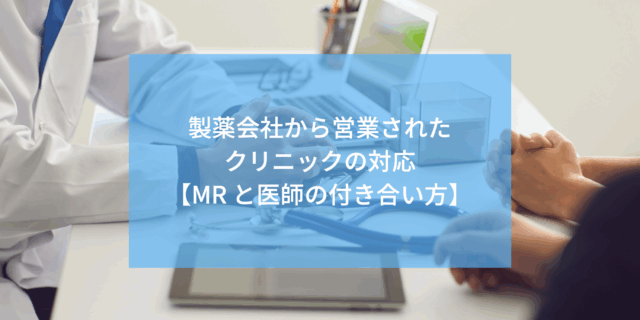
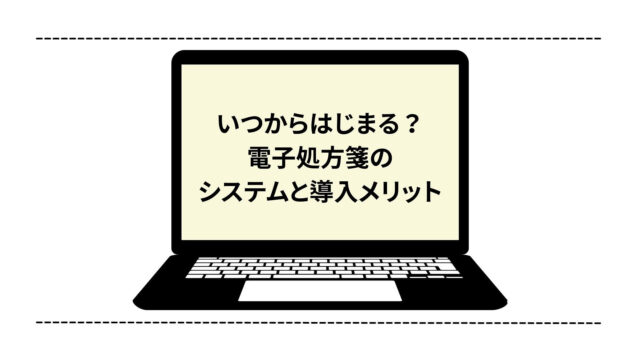
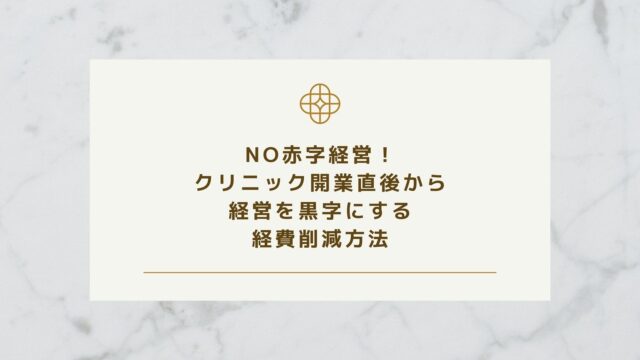
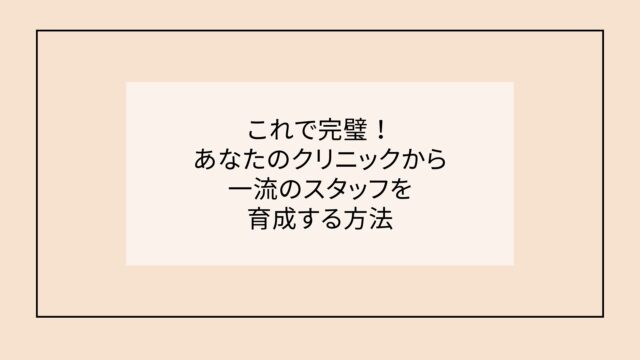
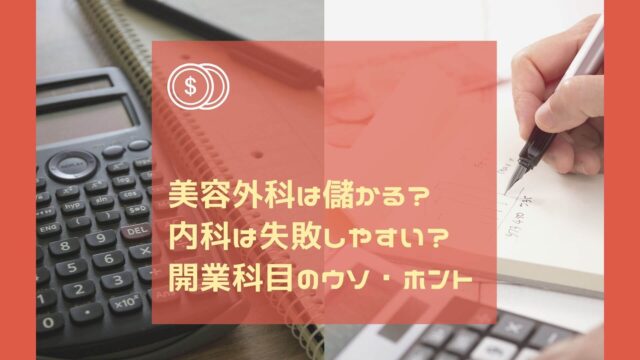
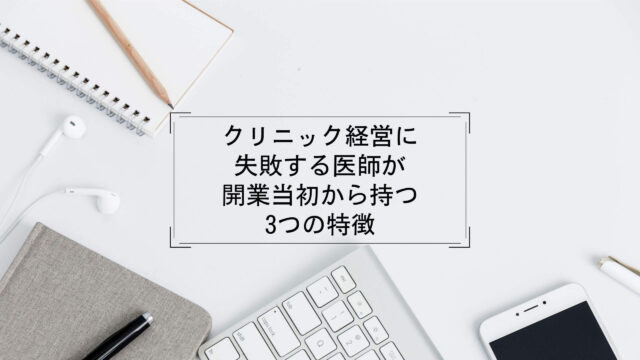
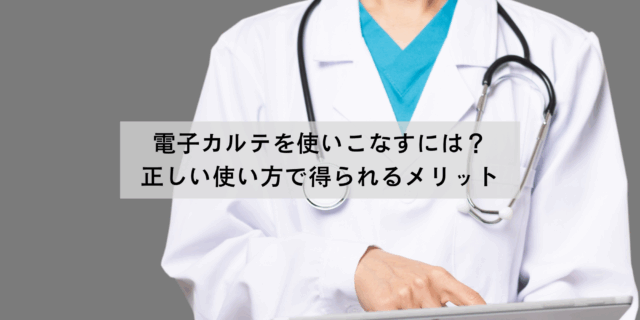
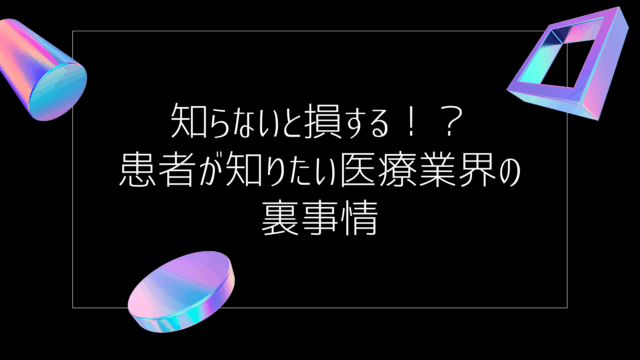

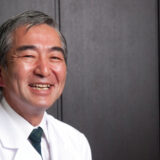


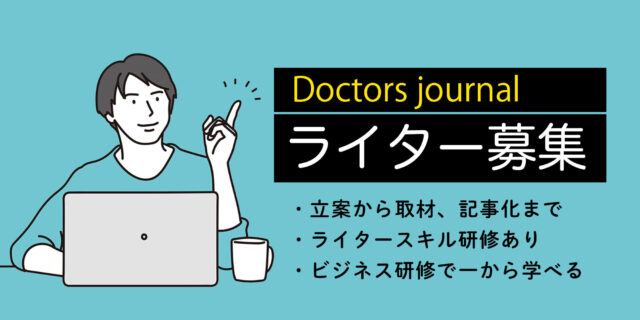


























森口敦 ドクタージャーナル東大生チーム・コーチ兼メンター