#03 認知症の臨床現場では、エビデンス通りの画一的な治療が多いように思われます。
2020.08.26
紙とペンでできる認知症診療術
現時点では認知症の根本治療薬はありません。しかし、2016年現在で認知症を抱えて困っている患者さんは全国で約500万人、更に2025年には700万人を超えるとの推計が出ています。
これらの患者さんに適切な医療を提供するには、認知症の専門医に限らず、あらゆる分野の臨床医が認知症の診療術を理解・習得し、認知症の診断・治療・ケアを行えるようなることが必要です。
そのために、臨床現場で役立つ診療のコツとその背景となる補足知識を記し、認知症の実践医療を解説したいと思い執筆したのが、高度な診断機器がなくてもできる「紙とペンでできる認知症の診療術」です。
エビデンスは大切ですが、臨床で培った経験に基づく診療も大切だと考えています。特に認知症医療では対症療法による実践医療がより重要と考えています。

山口晴保 著
協同医書出版社 2016年5月31日発行
本書 まえがきより
「エビデンスに基づく○○医療」という本が多い中で、本書のタイトルは『紙とペンで出来る認知症診療術』としました。
エビデンス一辺倒の医療への警鐘を込めてつけた・・・と述べると格好良すぎるのですが、エビデンスという「集団での根拠」に配慮しながらも、臨床経験を加味して「個々の症例に対応」していくことの大切さを本書では訴えたいのです。
何故なら、認知症の医療が基本的には対処療法ですし、また、認知症が脳の老化現象であり、完治を望めない病気だからです。
多くの医師が、「認知症の医療は面倒で嫌だ」「治らないからやりがいがない」と感じているようです。そこで、本書を読むことによって、「認知症の医療は面白い」「生活改善に役立ち感謝される」と変わることを願って執筆しました。
なお、日々の臨床経験により診療術が進化していくので、本書に書かれた内容は絶対ではありません。読者の皆さんの経験に基づいて、さらに進化させていただきたいと思っています。
私の目指す医療のアウトカムは、「患者本人とその家族が、笑顔で穏やかな在宅生活を続けられること」です。その願いを込めて、『笑顔の生活を支えよう』という副題をつけました。
病院や診療所という現場で、認知症の診療に関わるあらゆる分野の医師に役立つ本を届けたいという思いで原稿を書きました。
本書は、一度全体をお目通しいただき、その際に使えそうな診療術に赤線を引いてください。その後は診療机の片隅に置いて、時々確認しながら、診療術のレパートリーを広げるようにご活用いただければ嬉しいです。
内容
第1部 ● 認知症の初診
日頃の診療の中で医師やスタッフが認知症に気づき、生活状況を把握して認知症かどうかを判定し、さらに症状に基づいて臨床病型を明らかにした上で治療を工夫していく過程を詳しく説明しています。
第2部 ● 治療とフォローアップ
認知症という長い経過の疾患を抱える患者本人、そして家族・介護者をどのように支えたら、笑顔で穏やかな生活を継続することができるのかという、診断後の治療を解説しています。
第3部 ● BPSDと生活障害への対応
代表的な行動・心理症状(BPSD)や生活障害について、うまくいった方法を交えながら、対応のヒントを紹介しています。どのような内容であっても、まず原因を探り、患者本人の気持ちを踏まえた上でその原因に対処するという原則を理解できるようになっています。
第4部 ● ステージアプローチ
第 1 部から第 3 部までの知識を体系的に関連づけるため、ステージ(認知症の進行過程)という概念を意識しながら、認知症の医療・ケアを整理しています。また、穏やかな最期を迎えるための認知症の終末期医療についても解説しています。
第5部 ● 地域連携
「地域包括ケア」や「医療・介護連携」が提唱される中、認知症の人とその家族が地域の中で穏やかに暮らし続けていけるように支援することが求められています。これを踏まえ、地域のリソースを知って連携し、介護保険サービスを有効利用し、インフォーマルサービスも活用していく際のポイントを解説しています。

エビデンスは絶対ではない。
医療にとってエビデンスは重要で、それは間違いなく正しいのですが、とりわけ認知症の臨床現場では、あまりにもエビデンス通りの画一的な治療が多いように思われます。そのためにいろいろな問題も生じています。
確かにエビデンス通りにやると、7割位はうまくいきます。しかしエビデンスというのは多人数における確率値でしかないので、当然外れる人が出てきます。
しかし外れていてもその通りにやらなくてはいけないというのが今のエビデンス医療の問題点なのです。エビデンスはあくまでも確率であり、これが一番確率の高い治療法ということにすぎません。
アメリカでは、確率が高い治療法から順番に試していきながら本人に一番合ったものを見つけるという考え方ですが、日本では確率の高い治療法が絶対という考え方が強いのです。エビデンスを唯一絶対と信奉し、エビデンスに沿った医療を患者さんに強制する医師も多くいます。
医療の現場で医師の目の前にいるのは一人の患者さんです。その人にとって重要なのは、エビデンスという集団をベースにした治療法が有効か無効かいずれかということです。
集団で70%の人には効果があっても、その患者さんには当てはまらないこともあります。そうなると個別にその人に合った治療法を見つけていかなければならない。ですから認知症治療の現場では試行錯誤の繰り返しです。
私は臨床で積み重ねて来た数多くの経験を基に、認知症の患者さんの様々な状況に応じて、その都度エビデンスに捉われず最適と思われる治療を考え行ってきました。
エビデンスを基本として、そこに経験が加わることで、良い結果を得られる確率が上がるのです。
薬効には個人差が必ずあります。
特に認知症の治療薬に関しては、最低投与量まで決められています。
例えばドネペジルは5mg以上と決められています。しかし経験上、5mg以下の少量投与でもよく効く人や、副作用も出ず怒りっぽくならないでうまくいく人がいます。
でもその人たちは全体の中で見たら一部なので、そのエビデンスを作れといっても不可能なのです。理論的に考えれば当然のことで、薬剤の感受性には必ず個人差があります。
体重が80kgの人もいれば30kgの人もいます。勿論、血中濃度も変わってきます。そういうことは無視して、一律に、5mgだと効くというエビデンスがあるが、3mgだと統計学的有意差が無いから5mgを使わなければだめだ、というのがエビデンスの論法です。
例えば、酒の適量には個人差がありますが、「酩酊するにはお酒を5合飲ませてください。3合ではだめです。酩酊するためには必ず5合飲ませてください。」という規定です。私は、それはおかしいと思うのです。
また、規定通りの5mgであっても1割位の人が、イライラして怒りっぽくなってきます。それは薬の副作用と考えるのではなくて、薬の効き過ぎ症状と考えるべきなのです。ですから効き過ぎ作用であれば量を減らせばよいのです。
以前から厚生労働省に働きかけた結果、ようやく2016年6月に、添付文書に示された規定量以下でも医学的な根拠があれば認めるという通達が出てドネペジルの長期少量処方が容認されました。
エビデンス至上から抜け出せない医師。
エビデンス至上の典型的な医師は、診察で画像を見て海馬が萎縮しているとか、VSRAD(前駆期を含む早期アルツハイマー型認知症の診断を支援するためのソフト)の値が2だとかでアルツハイマー型認知症と診断すると、ドネペジル5mgを処方し、その後も頑なに変えようとはしません。
例えば、ドネペジルを使っていて怒りっぽくなっているアルツハイマー型認知症の患者さんがいるとします。
A医師はドネペジルに加えて抑肝散を併用します。確かに少し穏やかになります。
B医師はドネペジルに加えて抗精神病薬を処方します。
C医師はドネペジルを一時止めてみて、その間の症状を見ます。それで穏やかになれば、その後はドネペジルの処方量を少なく調整します。
私はC医師を支持します。
この場合、A医師とB医師は患者さんの症状は見ていますが、アルツハイマー型認知症にはドネペジルは絶対に必要な薬だというエビデンスに捉われていて、それを止める判断はしません。
患者さんが怒りっぽくなっても、これは進行を遅らせるために必要な薬だから飲むようにと、食欲がないと言ってもこの薬は治療薬として一番大切な薬だから飲み続けるようにと指導します。
進行を遅らせることだけが認知症医療のアウトカムだと信じて疑わず、エビデンス至上という価値観から抜け出せないのです。
ここがC医師(私)との決定的な違いです。















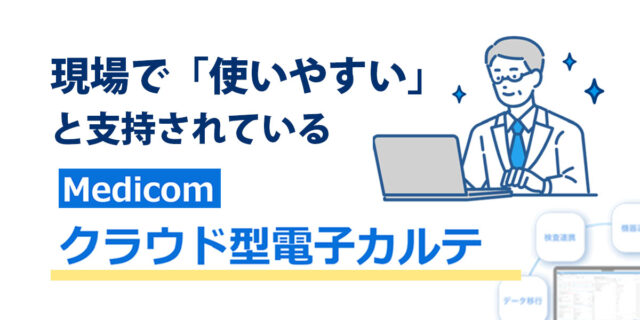
























![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)
![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)



![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)