#01 不安なく使いたい先生のための手厚いサポート
連載:業界主要プレイヤーがリレー形式で語る電子カルテの本当の選び方
2021.04.29
多くの先生方が1日の中で最も長い時間触れられるクリニックにある機器といえば「電子カルテ」ではないでしょうか。現在はありとあらゆる種類の電子カルテが登場しています。 一方、選択肢が多くなったことで電子カルテ選びが複雑になったことも事実かと思いま す。 本連載では「これから電子カルテの導入を考えている先生」や「すでに電子カルテを使われている先生」あるいは「先生に代わって電子カルテの入力をされているクラークさん」に 向けて、電子カルテメーカーを取り扱っている各社からそれぞれの会社の特長、思いなどを リレー形式でご提供致します。(PHCメディコム株式会社 小川誠一郎)
この記事について
これまで十数年以上、電子カルテの新規導入に関わってきた熊谷千鶴子さんから、PHCの電子カルテブランド『メディコム』の特長を伺いました。(ドクタージャーナルオンライン編集部)
メディコムはサポートがしっかりしているね、と言われますね。
-メディコムの電子カルテの特長は一言で言うなら、どのようなことでしょうか?-
よく言われるのは、導入後のアフターフォローですね。うちは全国41の販売拠点に加え、それ以上のメンテナンス拠点がありますので、何か不具合が起きた際も近くの拠点から駆けつける事が出来ます。
-サポートが手厚いんですね。メディコムといえばレセコンのイメージもあります。-
日本で最初のレセコン「メディコム」の販売から約50年という事もあり、診療報酬の部分については長年の知見を有していると思っています。当たり前と思われるかもしれませんが、行った診療をしっかりと診療点数として請求出来るという事は非常に重要です。そのひとつとして、電子カルテのレセプト機能は大事であると考えています。
そういった機能に加え、診療報酬に関するご質問も受け付けておりますし、社内にはレセプト関連等の専門のスタッフも在籍しております。ご希望のあった先生にはレセプトの点検サービスや、新規個別指導対策や医療事務のオンラインセミナー、クラーク講座なども行っております。このあたりも含めて、「メディコムはサポートがしっかりしているね」とよく言われるのかもしれませんね。
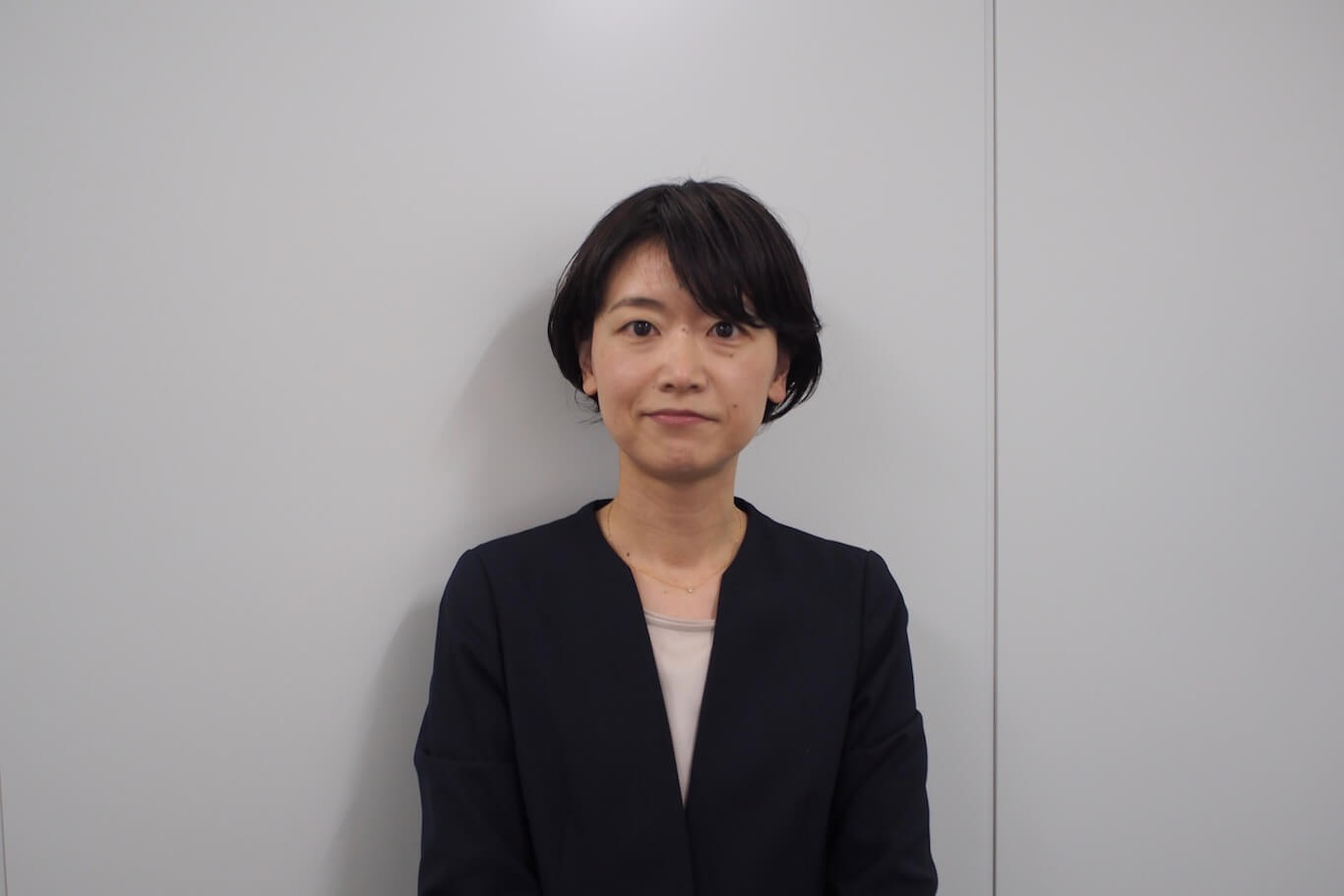
PHCメディコム 営業戦略本部 戦略企画部プロダクトマーケティング課所属。
栄養士。認定登録 医業経営コンサルタント。
医療機器販売会社において医療機関向けシステムの導入・サポートに従事。
その後、PHCメディコムに入社し、インストラクターとして導入・サポートを経験し、開業支援や製品の提案に携わる。
不安なく使いたい先生には良いかもしれませんね。
-メディコムの電子カルテはどのような先生のお力になれるのでしょうか-
診療科目で言えば、どの診療科の先生にでもお使いいただけると思っていますが、大事になってくるのは「安心して電子カルテを使いたいかどうか」だと思っています。例えば、メディコムの電子カルテはオンプレミス型になります。つまり、院内にサーバーが常にある状態なので、通信状況に左右されず安定して使うことができますよね。
また、医療機器に限らず予約システムなどの他のシステムともに幅広く連携ができますので、先生の目指している診療スタイルを叶えやすい、というのもあるのではないでしょうか。ただし、何でもできるということは裏を返せば、担当者に聞いたり尋ねたりしないと使えないシステムではないかと思っています。
-逆に、メディコムを必要としない先生もいるのでしょうか。-
弊社の場合、ハード故障時にはお電話1本でメンテナンス会社が代替機を持って伺います。また、システムの操作だけでなく、運用のご相談や診療報酬の質問などにもお答えしております。有料ではありますが、レセプトの点検サービスであったり、エリアによっては人材派遣も行っております。初期費用や保守料金等決して安くはありませんので、そういったサポートを望まれない場合は向いていないかもしれません。

導入サポート実績の多さと蓄積されたノウハウから運用のご提案
-今後のメディコムの展望を聞かせてください-
システムももちろんですが、今後はいろんな方面からのお客様のニーズに答えられるようなサポートを行っていきたいと思っています。開業支援や継承サービスなどがこれに当たります。
昨年から院内システムをトータルでコーディネートする役割として電子カルテの導入サポートをする職種名を「インストラクター」から「コーディネーター」に順次変更しているのですが、これも電子カルテやレセコンだけにとどまらず院内の運用やシステムをコーディネートしてお客様のニーズに応えたいという気持ちがあるためです。
開業や個別指導など全社を通じて多くの立会いを経験しているからこそ提案できる幅も増えていると思いますので、これからもいろいろな提案をしていきたいですね。





















![[がん治療の現状と課題]放射線治療の課題、秋元先生の取り組み #03](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/02/06e0d7d2282c5b5f17ff718a92ca8b70-80x80.png)



![[がん治療の現状と課題]患者の懸念、医療制度の課題 #02](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2024/01/f921745e9e011d0f14238fc3803310b9-80x80.png)

![[がん治療の現状と課題]日本最大のがん治療センターから #01](https://doctor-journal.com/wp-content/uploads/2023/12/44cbbfe318163c500ed08498f8d602c8-80x80.png)







ログインするとコメントすることができます。
新着コメント